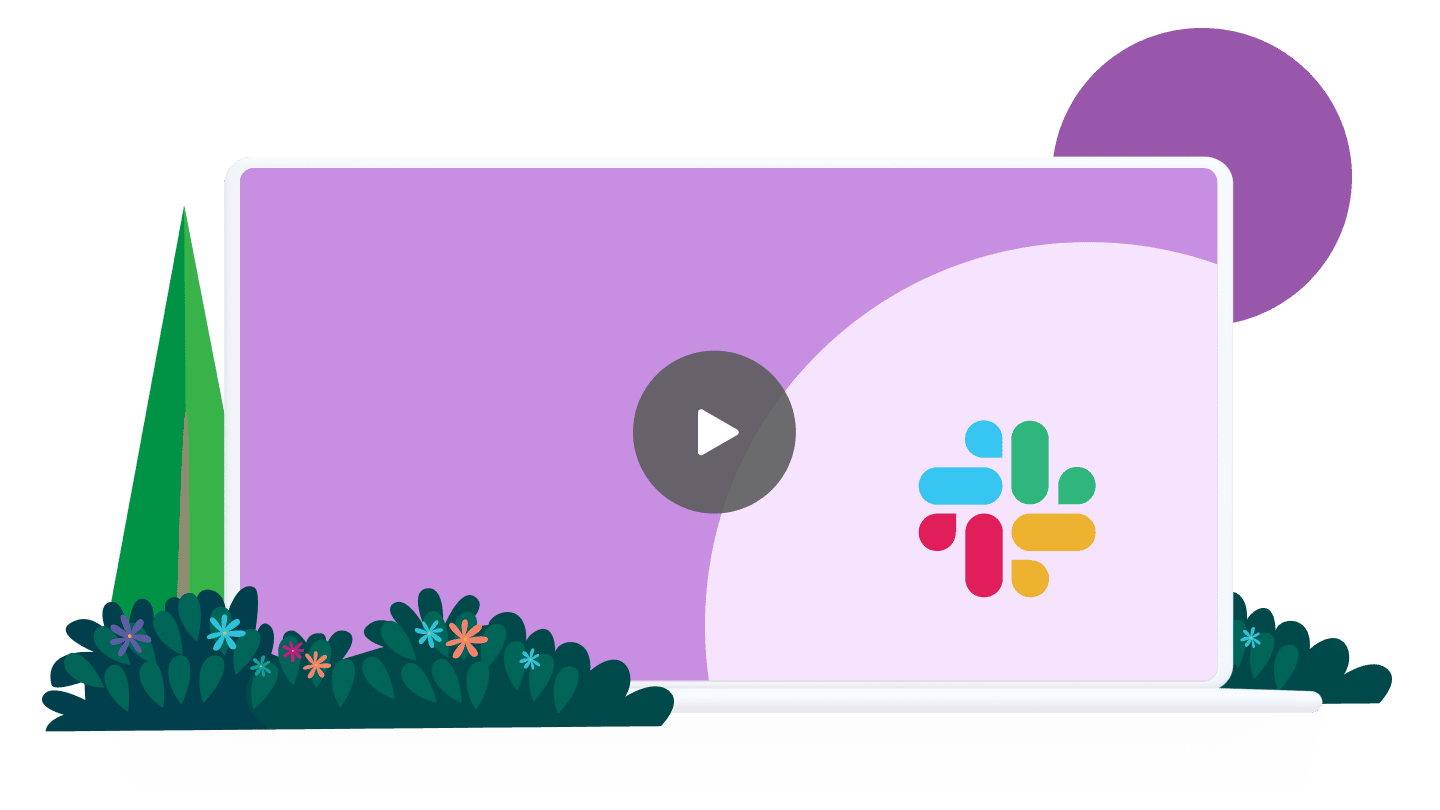100年以上の歴史を持つグローバル企業、荏原製作所でIT部門やDE&I(Diversity Equity&Inclusion)を通じた企業変革を推進し、日本のチェンジマネジメントの第一人者として活躍する入江哲子さん。グローバル組織の経営陣を巻き込み現場を動かすリーダーシップ、人を動かす極意をお聞きしました。
Key Takeaways
目次
「人財開発」がキャリアの原点
──日本ヒューレット・パッカード(現・日本HP)と花王、ソニー、そして荏原製作所へと歩んだこれまでの道のりを教えてください。
入江:日本HPで担当していたのは、人財開発、特にコーチングでした。
20代の私が、当時の日本にはまだ馴染みがなかったコーチングの概念や手法を米国本社で学び、それを日本の組織の部長クラスに研修する。今思えば恐れ知らずのチャレンジでしたが(笑)、プロフェッショナルとして振る舞うことの重要性を叩き込まれた、濃密な時間でした。

株式会社 荏原製作所 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進部長 兼 CIOオフィス / 情報通信統括部 / 人財戦略部
慶應義塾大学卒業後、日本ヒューレット・パッカード(現・日本HP)や花王にて、アジアERP導入教育(E&C)、アジア・スイスなどでの半数以上海外メンバーで構成されるグローバルリーダーシップ開発研修の企画立案/推進、欧米ASEAN中華圏での新規事業創造プロジェクトに従事。
その後DX推進組織を経て、ソニーグループのグローバルHRプラットフォーム推進。現職ではダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)、ERP導入グローバルチェンジマネジメントなどの推進に従事。2023年9月にDE&I推進部を設立後、以下受賞:JAPAN HR DX AWARDS 2024 特別賞、第13回~第14回HRチャレンジ大賞奨励賞2年連続受賞、他。
その後、第一子の出産を機に、働き方を見直す中で、ご縁があったのが花王です。当初は前職の経験を生かしたグローバルトレーニングの担当として入社したのですが、
そこで当時の人事役員に、「ERP導入をやってみないか」と意外な声をかけていただいたのです。
その時の配属先の上司が、後に荏原製作所に導いてくれた小和瀬さん(*)でした。まだ、チェンジマネジメント(*)という言葉が聞かれない頃でしたが、そこで初めてその真髄に触れ、システム導入に伴う変革における、教育とコミュニケーション戦略の構築、推進の円滑化を担当しました。
*小和瀬 浩之氏: 荏原製作所 執行役CIO(情報通信担当)兼 情報通信統括部長(「日経クロステックが選ぶ CIO/CDO オブ・ザ・イヤー2023」の大賞を受賞)
*チェンジマネジメント:組織が『現状』から『目指す姿』へ移行し、期待する成果を得るための変革推進手法。
その後、家族の海外赴任に伴いニューヨークに帯同し、一度は花王を離れましたが、
帰国後に再びキャリア入社しました。その後、スイスやアジア各国の教育機関と次世代グローバルリーダーの育成を行う立場として経営層と接する機会も多かったため、花王がDX専門組織を立ち上げる際、社長直下のような形で活動しました。
気づけば、マーケティングやR&D、M&Aなど、あらゆる機能が集結する組織で
、組織の枠を超えて「なんでも屋」のように働いていました(笑)。
── そこから、ソニーを経て、荏原へ転職されます。
日本HP時代の先輩が声をかけてくれて、ソニーに移りましたが、先の小和瀬さんから
再び縁をもらいました。
当時の荏原製作所は、これからERPをグローバルに導入しようとするタイミング。私のチェンジマネジメントの経験とスキルを少しでも役立てられたらと思い、荏原製作所に入社したのが2022年です。

“三足の草鞋”という稀有な役割
── 現在の役割は、DE&IとCIO-Office、情報統括部の兼務。極めてユニークです。
はい(笑)。入社当初は、CIOの小和瀬さんに呼んでもらった経緯もあり「情報通信統括部」というIT部門に所属し、グローバルERP導入プロジェクトにおけるチェンジマネジメント、特にエデュケーションとコミュニケーションチーム(E&C)のCoE(*)のリードをさせていただきました。
*CoE(Center of Excellence):組織全体で活用すべき専門知識、技術、ノウハウなどを集約した、組織横断的な部門・チーム
海外のメンバーとも日々やりとりし、充実した日々を送っていたのですが、入社から1年半ほど経った頃、全社的に大きな組織変革が行われることになりました。そこではDE&Iを推進する部門も新たに設立されることに。
人事でのバックグラウンドもあることから、経営層より「人事部門に来てDE&I推進の責任者を務めてほしい」と依頼頂きました。
「ERP導入のチェンジマネジメントをやり遂げるために来たのに……」という葛藤がなかったわけではないですが、大きな変革の当事者として、白羽の矢を立てていただいたことは大変光栄なことでした。現在は、人事を主務としながら、ERP導入のチェンジマネジメントやCIO-Officeにも引き続き2〜3割のリソースで携わっています。
──「CIO-Office」という組織形態も日本では珍しいですね。何を手掛けている組織なのですか。
荏原製作所のグローバル経営体制は、従来の日本本社を中心とした経営ではなく、コーポレート機能と地域をマトリックス化し、CxOがグローバル全体を統括する組織構造です。
その一環で、CIO直属のグローバル横断組織として設立されたのがCIO-Officeで、私は主に、人事関連とチェンジマネジメントを支援する役割で参画しています。
この組織形態のメリットは、リソースやコストの最適化と効率化、そして適切な情報の連携です。
その中でも、例えば今年5月には、グローバル各国のディレクターレベル約60人が日本本社に集結し、3日間にわたって対面での議論を行いました。普段はリモートでのコミュニケーションが中心ですが、このような機会を設けることで、「リアルなコミュニケーションの機会を開催してくれてありがとう」という声が多数聞かれました。
事務局の皆さんにも心から感謝しましたが、グローバルの仲間たちが、物理的な距離を超えて一体感を持って働ける環境を作ることも、CIO-Officeの重要な役割の1つです。
製造メーカー向けサービス体験DXガイド
本ガイドは、顧客とビジネスパートナーが製造メーカーと付き合う中で得る「体験」を変革する方法について、製造業界のリーダー向けにご紹介いたします。

「グローバル統一」の難しさをERP導入で経験
── 複数の役割を担いながら企業変革に携わる中で、印象に残っているプロジェクトは何でしょうか。
グローバルERP導入におけるチェンジマネジメント、人的資本経営に貢献するDE&I戦略や施策の立案・推進、外国籍人財の採用・定着支援、多様な働き方の推進など、幅広いテーマに携わってきました。
そうした中、印象深いプロジェクトは、やはりグローバルERPの導入です。荏原製作所グループの10年後を明記した長期ビジョン「E-Vision2030」の一環として、全社のインフラ基盤を整備しグローバル一体経営を実現するべく、国内および欧米・アジアのグループ会社を対象に、2020年にプロジェクトが立ち上がりました。
各国で多くの前提や状況が異なる中、多言語・多文化の環境下で進めていく難しさがありました。
特に印象的だった欧州導入先では、現地法人が他の地域より先行してSAPを導入していたのに対し、私たちがグローバル統合でのERPを導入するために必要なさまざまな調整事項が多々ありました。
そこでは、欧州導入先のメンバーの理解度や粒度に合わせて変革の意義や期待を語りかけてもらうよう、現地法人のトップマネジメントにも協力頂きました。
「背景や状況が異なる」という意味では国内でも同様です。私個人が関わった、過去の変革プロジェクトでは、社員に対してシステム導入の背景や目的が十分共有されず、社員にとって「自分事化」されないまま「導入することがゴール」というマインドでプロジェクトが完了し、目指す姿が語られることもなく、期待した成果が得られないことがありました。
その教訓を踏まえて、荏原製作所では、経営層の支援を仰ぐことに加えて、「Prosci ADKAR® Model」などチェンジマネジメントに関するフレームワークを活用しました。
社員一人ひとりが変革の意味を腹落ちさせながら取り組むことで、少しずつ懸念や疑問が払拭され、個人にも組織にも、変化の波が確実に広がっている実感がありましたので、とても印象に残っています。
── Prosci ADKAR® Modelとその活用方法を教えてください。
「Prosci ADKAR® Model」は、米国のチェンジマネジメント研究機関「Prosci」が提唱するチェンジマネジメントのフレームワークです。
組織の変革を進めるうえで、個人が心理的にどのような変革の段階にあるのかを継続的に調査、分析して、その心理的な段階に応じた支援を行うという考え方です。このモデルでは、個人が変化を受け入れ、実践し、定着させるまでの心理的プロセスを以下の5つの段階に分けて示しています。
①Awareness(認知):なぜ変革が必要なのかについての認知
②Desire(欲求):変革に参加・サポートしたいという欲求
③Knowledge(知識):変革の方法についての知識
④Ability(能力):必要なスキルや実際に実行するための能力
⑤Reinforcement(定着):変革を維持するための定着
私たちがプロジェクトを開始する際には、まずこの「ADKAR分析」を行い、対象となる社員一人ひとりが今どの段階にいるのかを把握し、そのうえで各段階に応じたコミュニケーションや支援を実施していきます。
また職場や導入先ごとに異なる「なぜこの変革が必要なのか」は、個人が自分事として納得できるように働きかけて、「聞いていなかった」「突然だった」「良いことが何もない」などの不満が現場から生まれないよう、丁寧な情報提供によるAwarenessを心掛けています。
ADKARを活用することで、変革に対する心理的バリアや停滞ポイントを可視化し、個人や組織に寄り添ったマネジメントを実現することができます。
実は、私が入社する以前から、荏原製作所では小和瀬さんがチェンジマネジメントの重要性を説いており、数人の社員がADKARの研修を受けてプラクティショナー資格を取得していて、土壌はすで整っていました。
また、私がソニー時代からお付き合いのあったProsciのご担当者が、チェンジマネジメントを実践する代表的な日本企業2社のうちの1社として荏原製作所の名前を挙げてくれていました。
私自身、小和瀬さんからは「20年前からADKARのようなアプローチを実践していた」と言っていただきました(笑)。
ただ、体系的には学んだことはなかったため、まず社内の共通言語を持つために、私もADKARの研修でフレームワークを学びました。さまざまな社内のケースにADKARのメソッドを当てはめることで、効果をより最大化できます。また、経営層にもADKARを理解していただくことで、組織全体で変革に取り組むことが可能になります。

経営層から現場まで。組織を動かす入江流リーダーシップ
── 経営層や組織を動かすための入江さん流の秘訣をお聞きしたいです。
20代の頃、米国のコーチングを学び、自分よりはるかに年上の部長などの幹部にトレーニングを行うことになって、初めの頃はどうしたら良いのかわからず悩みました。
その時、上司から「あなたはプロなのだから、相手が部長でも社長でも、絶対にプロとして振る舞いなさい」というアドバイスをいただいて覚悟を決めました(笑)
その言葉を受け、テレビを⾒るときでも、出演者の⾃信に満ちた振る舞いを参考にするなど、試行錯誤を重ねました。そうしていくうち、「相手が社長や役員でも、私が伝えられることもあるだろう」と自信を持てるようになってきまして。
そこからは、相手が誰であれ、お伝えすべきことはプロとして伝えて、あとは相手の判断に委ねる。そうした姿勢を貫くことで、経営層の方と対話する機会も増えていきました。
── 組織全体を動かすうえで、新たなルールや考え方やツールを導入・浸透させるのは至難の業です。大切なことは何でしょうか。
各部署のトップやメンバーが理解できる言葉で伝えること、そして、立場によって欲しいメリットが異なることを理解し、それぞれに応じた「ベネフィット(利益)」を伝えることです。
例えば、同じSalesforceのツールでも、人事で使う場合、経理で使う場合、他の部門で使う場合では、活用方法が異なると思います。それぞれの立場やビジネスの状況を深く理解し、その人たちの言葉で「このルールやツールが、あなたにとって、あなたの部門にとって、こんな良いことにつながるんですよ」と語りかけます。
また、課題への理解がまだ深まっていない人たちには、「どのようなお困りごとがありますか」(または潜在的なニーズは何か)、「このツールをあまり活用されていないようですね」といった基礎的な対話から始めて、相互的な解決策を導き出したうえで、メンバー同士で話し合いながら実行していただく。そうした細かい粒度でのアプローチも行います。
変革において特に重要となるのは、各部門のトップの方々から、現場のメンバーに向けて「この変革はこのような意味とメリットがありますよ」と語っていただくことです。私たちがCoEとして発信する内容と、それぞれの事業部のトップやマネジメントが語る言葉では、現場への伝わり方が全く違いますので、現場のトップに理解頂くことも大事です。
いまどきの部下を動かす「サーバント・リーダーシップ」入門
いま企業の間で大きな注目を集めているのが自律的に組織を動かす「サーバント・リーダー」という 新しいリーダー像です。詳しくは、無料eBookで解説しています
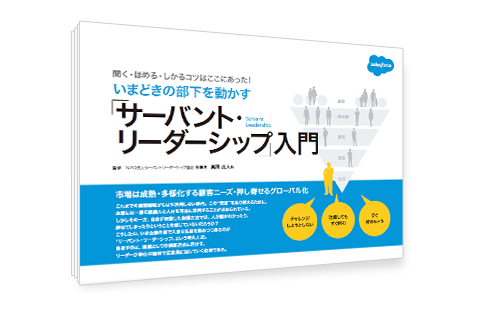
成功するリーダーの「3つの視点」
── 相手の目線に合わせて、相手にとって何が得かを、わかりやすく相手の立場で話すことで、仲間になってもらうということですね。
まさにその通りです。相手のメリットが何かを意識して提示することが非常に重要です。この考え方は、私が理想とするリーダーシップ論にも繋がっているのですが、変革を成功させるリーダーに必要なことは、次の3点だと感じています。
1. スポンサーとの連携: スポンサーとは、全社に影響力を持つ経営層のことです。彼らの強力な発信力を借りて、変革の目的や重要性を組織の隅々まで浸透させることが不可欠です。
2. 膝詰めのコミュニケーション: 現場の社員に直接的な影響力を持つマネージャーやリーダー層を通じて、一人ひとりに変革の意義を伝え、腹落ちしてもらうことです。HOW(どうやるか)だけでなく、WHY(なぜやるのか)を丁寧に伝え、相手の困りごとにも真摯に耳を傾ける姿勢が重要です。
3. 伝道者(エバンジェリスト)の育成: プロジェクトに賛同し、私たちの代弁者として現場にメッセージを伝えてくれる「仲間」を作ることです。彼らの存在が、現場の隅々まで「理解できる共通言語で」「プロジェクトを成功させよう」というポジティブなマインドを広げてくれます。
テクノロジーと人の心を深く理解し、共感を得ながら変革を進めていく。これこそが、これからの時代のリーダーに求められる姿だと信じています。
DE&Iはビジネスに直結して貢献する
── DE&Iについても同様でしょうか。ITツールの場合は、使うと楽になる、売り上げが上がるなど、具体的なメリットがありますが、DE&Iは二の次、三の次になりがちです。社内に根付かせるための考え方があれば教えてください。
先日も、「HRチャレンジ大賞」奨励賞を、DE&Iの取り組みでいただいたのですが、受賞の理由を私は主に2つだと分析しています。
1つ目は、DE&Iがビジネスに貢献することを証明し、経営層に向けて徹底的に情報発信をしていくこと。2つ目が証明の方法。さまざまな切り口で、データでDE&Iの成果を見せることを地道に続けていくことです。

CIO、IT部門の役割も「人と組織の可能性」の最大化
── 入江さんが2025年以降に強化したい分野は何でしょうか。
CIO組織とCHRO組織もそれぞれが協働する形での、人的資本経営の進化が必要であると考えています。
私自身、人事部門とIT部門の両方に身を置いていますと、両方の資産が生きる場面に出会います。
人事だけでは実現できなかったことを、データ活用やプロトタイピングなど、ITのアプローチと連携させることで解決する。たとえ小さな事例でも、そうしたトピックをCIO組織とCHRO組織がすぐに話すことで、非常にスピーディーにさまざまなことが解決できます。
2025年以降は、これまでよりもさらに「従業員を中心とした人財戦略」の重要性が高まり、会社と従業員がお互いに選び選ばれることが必要になります。そのためにも、私が強化したいと考えている領域は以下の2点です。
①組織のアジリティの強化
変革を阻む最大の壁は、技術的な問題や人事制度などではなく、「変わらない組織文化」と「人の不安」です。この壁を少しずつ打破するためにチェンジマネジメントを活用し、現場とも密に連携しながら「変化に強い組織文化」の醸成に注力したいと考えています。そのためには以下のような戦略が必要だと考えています。
・スキルの可視化と自律的キャリア形成を支える仕組み作り
・心理的安全性を前提としたチーム運営の改善
・変革をリードできる人財の早期発掘・育成
②人財中心のDX
デジタル投資のROIを最大化するためには、従来のシステム導入を中心としたDXだけではなく、従業員視点での業務や意識の変革が必要です。CIO/CHRO組織と連携しながら、業務データ×人事データを活用し、以下のような、より効率的/効果的な変革を進めることが必要だと考えます。
・人財データ分析を踏まえた最適配置/業務設計
・様々なデータ分析に基づく従業員エンゲージメントの向上
・DE&Iやウェルビーイングを踏まえた仕組み作り
これからのCIO組織は「テクノロジーの責任者」ではなく「人と組織の可能性を最大化する変革の設計者」であると考えています。
私自身は人事とITに籍を置く立場として、その変革を支援していきたいと考えています。CIO部門の役割には、全社的なデジタル変革の推進もあります。ただそこでは、単にシステムを導入すれば良いというものではなく、チェンジマネジメントの視点が重要で、変革の意義やベネフィットを組織に対し積極的に呼びかけていくことが必要です。
新しいシステムやプロセスを導入する際に、最も大きな障壁となるのは技術ではなく、「人」なのです。人は変化を恐れる生き物ですから、いかにその抵抗を最小限に抑え、むしろ変化を前向きに捉えてもらえるか。 これがチェンジマネジメントの本質ではないか、と思っています。

AIエージェントの台頭で見つめ直す人の役割
── AIの進化は予測から生成へと移り、現在はセールスフォースも注力するAIエージェントに至っています。入江さんは、AIエージェントが今後どのように進化し、企業はそれにどう向き合っていくべきだとお考えでしょうか。
実は、私はAIエージェントという存在が大好きで(笑)。私たちのすぐそばに寄り添うパートナーのような存在になっていくと考えています。私自身、CIO組織とCHRO組織に身を置く立場として、両者が近づいていることを実感していますが、AIエージェントは、その2つの領域を繋ぐ架け橋のような役割を担ってくれる存在だと感じています。
また労働力という観点では、その貢献は計り知れません。人件費や人員数を考える上でも、これまでのような単純な人員増強ではなく、AIエージェントの存在が無視できないものになると思います。
── AIエージェントが「労働力」となる未来に、人でなければできない仕事は何だとお考えでしょうか。
人間は曖昧で複雑な感情や人間関係をうまく咀嚼し、人々の心を動かし、行動へと繋げていく役割を担うべきだと考えています。
ADKARのフレームワークの中でも「Desire」を喚起すること、つまり「やろう」という気持ちにさせることが非常に重要なのですが、これはAIには難しいことです。人々の感情を動かし、モチベーションを高める。
そして、誰が、どのタイミングで、どのようなメッセージを発信すれば最も効果的かを見極め、指示を出す。そういった、現場の隅々まで変革の意図を浸透させていくためのコミュニケーションは、やはり人間の役割ですね。
──入江さんの仕事における信条があれば、お聞かせいただけますか。
必ず「Have a Fun」と答えています。仕事の中に「面白さ」を感じてもらうことが、何よりも非常に重要だと考えています。相手にとっても、限られた人生の時間を使って仕事に携わるのであれば、「面白いね」「こうやって工夫できるね」といった発見があった方が良いですよね。
AIエージェントが定型的な業務を担うようになる未来で、人間の役割として重要になるのは、AIに適切なプロンプトを出して「こうやったら効果が出るし、面白い」と探究をしていくことではないでしょうか。そうした探求心は、自らが仕事の中に喜びを見出してこそ生まれてくるものだと考えています。
以前、当社の女性社員たちと対話する機会があったのですが、その時も、仕事の中に「面白さ」を見出すこと、そして、その人なりのストーリーを紡いでいくことの重要性をお伝えしました。
どんな仕事も、自分自身の物語として捉え直すことができれば、限られた人生はもっと豊かなものになるはずですから。
企画・執筆:池上雄太
撮影:佐藤新也
インタビュー・編集:木村剛士
AIエージェントをあなたのチームの一員に!
動画で見る「Agentforce in Slack」の革新的チームコラボレーション
本デモ動画では、CRMデータや外部情報を統合し、複数のAIエージェントが連携して提案からタスク実行まで一気通貫でサポートする様子をご紹介します。