パナソニックやファーストリテイリングといったグローバル企業でデジタル変革を推進し、「武闘派CIO」の異名を持つ国内屈指のCIO、フジテック株式会社の友岡賢二氏。長年にわたり、CIOの重要性を説き続けるその姿勢の裏には、日本のデジタル変革の推進とCIOの地位確立に対する強い使命感と情熱がありました。友岡氏がCIOとして貫いている哲学、フジテックでの挑戦、未来のCIOたちに向けたメッセージを紹介します。
10分でおさらい、DXの「ナゼ」と「ナニ」
本動画では、DXの本質やDX時代における収益性向上のポイントをおさらいします。DXの定義を再確認し、あらためて理解を深めたい方はぜひご覧ください。
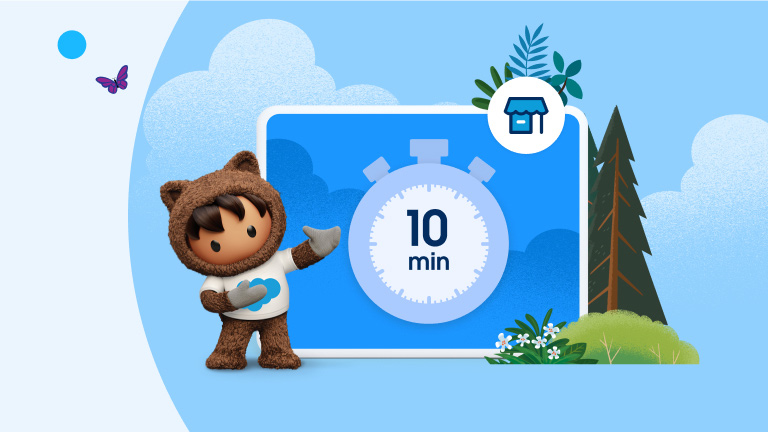
「武闘派CIO」誕生の裏に同士あり
──「武闘派CIO」という呼び名が定着していますが、そもそもなぜそう名乗るようになったのですか。
友岡:いや、私が名乗りたくて名乗ったわけではないんです(苦笑)。
きっかけは、2010年頃の社外のITコミュニティでの活動でした。私は2006年からパナソニックの米国法人でCIOを務めていたのですが、ちょうどその時期に「AWS(Amazon Web Services)」が登場し、「iPhone」が発売されました。
クラウドとモバイルの大きなうねりを現地で体験したわけです。米国では多いに盛り上がり、私は「これは企業のITを根本から変える」と確信しました。
ところが、日本に戻ると「クラウド? そんな危ないもの企業に導入できるわけがない」「モバイル? ガラケーで十分」という雰囲気で、そのギャップに驚き、クラウドとモバイルによる変革を社内で進める難しさを感じました。
そんな時に、社外に目線を移して、「JAWS-UG(AWS User Group- Japan)」というAWSのユーザーコミュニティに参加したところ、当時東急ハンズCIOを務めていた長谷川(秀樹)さんや、日清食品ホールディングスのCIOだった喜多羅(滋夫)さんなど同じ危機感を持つ仲間たちと出会ったんです。
みんな、日本企業のデジタル変革を促進したい、もっと多くの経営者にCIOの重要性をわかってもらいたいという使命感を持っていて、「挑戦するCIO」のようなイメージを持ってもらうために一緒にコミュニティ活動しよう、と。そこで「せっかくだから何かユニット名つけようか」と盛り上がり、当時の日本のAWSコミュニティの表彰制度にあった「サムライ」という称号にちなんで、「武闘派」はどうか、となって。これがきっかけで「武闘派CIO」という呼び名が生まれました。
これを機に、JAWSイベントでのセッション名に「武闘派CIO」を使ったら、その時たまたま取材していたメディアの方が見出しに武闘派CIOを入れて、大々的に紹介されてしまったんです。内輪の呼び名くらいのつもりだったのですが、その後いろいろなかたちで武闘派CIOと紹介されることが増えてきて、まぁいいかという感じで(笑)。

フジテック株式会社 専務執行役員 デジタルイノベーション本部長(CIO/CDO)
1989年、松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社。独英米に計 12 年間駐在。株式会社ファーストリテイリングの業務情報システム部部長を経て、2014年にフジテック株式会社入社。一貫して日本企業のグローバル化を支える IT 構築に従事。早稲田大学商学部卒業。
日本はCIOが少なすぎる。配置企業はわずか5.7%
──そんないきさつがあったのですね。積極的にメディアに出たり、講演されたりし始めて十数年経ちますが、今の日本のCIOを取り巻く環境をどのように受け止めていますか。
率直に言って、依然強い危機感を抱いています。
JUAS(日本情報システムユーザー協会)の調査によると、2023年度時点で専任のCIOを設置している日本企業は、わずか5.7%。2019年の3%からは微増しましたが、依然として低い水準です。この調査対象は大企業が中心ですから、全体ではもっと少ないはずです。

──5.7%……。驚くほど低いですね。経営にはテクノロジーが欠かせなくなって久しいですが、なぜこれほどCIOの重視性がいまだに理解されていないのでしょうか。
経営層のITに対する認識の問題があると考えています。以前、調査会社のガートナーのアナリストが「ITは文房具ですか? それとも武器ですか?」と問いかけていました。文房具程度の認識であれば、専門のCIOは不要でしょう。しかし、「事業を成長させる武器」と捉えるならば、CIOを自然と配置するでしょう。残念ながら、多くの日本の経営者にとって、ITはまだ「コストのかかる文房具」なのかもしれません。
私が講演などで「武闘派CIO」を名乗り続ける根底には、日本にCIOという職業を確立したいという強い想いがあります。経営者にはCIOの役割と重要性を正確に理解してもらいたいし、現場のシステムを開発・運用するIT担当者にはCIOを目指してほしい。その一心で、私はさまざまな場所に立って喋っています。
一方で、IT部門にも課題はあります。IT部門のリーダーやマネージャーが経営課題に寄り添った戦略やDXプランを作成できていないことです。
ITリーダーの方々と話しをすると、「トップがテクノロジーを理解してくれない。投資の価値をわかってくれない」と嘆く声を頻繁に耳にしますが、それは経営者の目線に立って話ができていないからです。
経営とは詰まるところ、売り上げを伸ばしてコストを圧縮し、利益を増やすこと。その文脈に合わせて、テクノロジーの重要性を語らなければ理解してくれないのは当然です。経営とIT、それぞれが歩み寄ることがデジタル変革には欠かせません。

AIは「目と耳」を獲得した
──対外活動を活発に行う中、フジテック在籍期間は10年を超えました。どのような方針で変革を推進してきたのでしょうか。
前半と後半に分けると、前半はモバイルとクラウドを活用して、主に社内改革。従業員の働き方を変えてきました。その当時はリモートワーク環境が整っていなく、直行や直帰ができないなど今では信じられない状態だったので、どこでも仕事ができ効率的に仕事ができるワークスタイルの確立を進めました。これは、結果的にコロナ禍の時にもあたふたせずに業務を進められたことにもつながりました。
後半は、IoTとAIの活用によるイノベーションの創出。今私がリードしている組織も2019年に「情報システム部」から今の名称、「デジタルイノベーション本部」に改組し、より一層デジタルを活用したイノベーションを強化しています。
フジテックが開発・販売するエレベータやエスカレータがより快適で”安全・安心”にご利用いただけるようなサービスの開発を、IoTやAIなどの先進テクノロジーを活用して生み出そうとしています。
──今のAIを友岡さんはどう分析・評価していますか。
今、AIは「目(視覚)」と「耳(聴覚)」を獲得し、生成AIによって非構造化データを扱えるようになりました。画像から状況を認識したり、異音から故障の予兆を捉えたりすることが可能になりました。さらに、企業が持つ情報の8~9割を占める非構造化データをAIが理解し活用できるようになったことで、自動化や業務支援の可能性が爆発的に広がりました。
こんな魅力的なテクノロジーを使わない手はありませんから、フジテックでも取り入れていく動きを始めています。例えばフィールドエンジニアの支援。経験の浅いエンジニアがウェアラブルデバイス(スマートグラス)を通じてAIの支援を受けることで、ベテランのノウハウを効率的に伝承できます。
また、地震発生時には、停止した昇降機の調査・復旧に向けて、どのフィールドエンジニアがどういう順番で現場に駆けつければよいかという最適なルートをAIが提案することも可能になります。
AIの導入にあたっては、チームを組んでプロジェクトを進めていますが、既存の完成度が高いツールを活用し、RAG(検索拡張生成)で社内にしかない情報を生成AIに学習させる取り組みも行っています。

中期経営計画を支えるDX戦略の主要テーマ
──2024年から2028年までの中期経営計画「Move on 5」を展開中です。この計画におけるデジタル変革の主なテーマは何ですか。
私たちがお客様に提供する最も重要な価値は何か。突き詰めた結果、それは”安全・安心”であるという結論に至りました。
昇降機は社会インフラであり、安全に、確実に動くことが絶対的な使命。テクノロジーを活用して、いかに昇降機の安全性をさらに高め、お客様に安心を提供できるか。大方針として”安全・安心”を最優先とし、そのためにテクノロジー基盤を整備することに集中しています。軸を明確にすることで、「”安全・安心”に直接つながらない施策は、優先度を下げるかやらない」という判断もしやすいですし、周囲の納得も得やすいですから。
そのうえで主な具体的施策をいくつか紹介すると、「フルクラウド化」「グローバル標準」「従業員支援」「お客様のお客様向けサービスの拡充」です。
まずは以前から進めているクラウド化を加速させ、2028年にはすべてのシステムをクラウド環境に移行させます。
そして、各現地法人が活用するシステムの標準化も重要なテーマ。フジテックの売り上げの60%以上を海外が占めていますが、各現地法人で活用するシステムは現地に任せているものもあり、一貫したシステムを構築できていないことが課題です。それでは全世界で共通のサービスレベルを維持できないので、標準化を進めています。
インフラを整備する一方で、従業員の業務を支えるテクノロジー活用も推進していきます。先ほど話したAIももちろん積極的に取り入れていますが、24時間365日対応するフィールドエンジニアの生産性を上げるためのテクノロジーを取り入れていき、お客様の”安全・安心”、そして快適の確保をさらに高めることができればと思っています。
また、お客様の先にいるお客様、すなわち実際に昇降機を管理される方々ならびにご利用者様へのサービス充実も重要な観点だと思っています。
フジテックの直接的なお客様は、ゼネコン様や設計事務所様です。建物が建ち、サービスが稼働し始めると、マンションの場合は管理会社の方々がお客様になります。現在は主に管理会社の皆様にエレベータの稼働状況などの情報を提供していますが、その先の実際のエレベータ利用者の方々にも必要な情報を届けたいと考えています。
例えば、能登地震の際、管理会社の方々は年始でお休みでしたので、ウェブ上で見られるエレベータの稼働状況へのアクセスが非常に少なかったのです。しかし、そこに住む方々や働く方々は、いつエレベータが復旧するのかという情報を必要としていました。
この情報は我々がすでに持っているものです。このような情報をいかに直接利用者の方々に届けられるか。私たちの商品やITツールを活用してお知らせする方法を考えているところです。

私が考えるCIOの理想像
──友岡さんは、パナソニックとファーストリテイリングを経て、フジテックに移籍しました。以前在籍した会社に比べて、フジテックのCIOの醍醐味や難しさは何でしょうか。
昇降機は社会インフラです。みなさんの生活になくてはならないものを提供しているという使命感があります。加えて、昇降機は消耗品などの他の商品と違って、一旦据付されると簡単に取り替えることができませんから、重責を担います。プレッシャーは相当のものですが、だからこそやりがいを感じます。

技術的には、機械部分は比較的クラシックな面がありますが、それを保守する部分には最新のIoTやAIが活用できます。大量のログデータを分析し、予防保守や予兆検知を行うことで、人の目や感覚を超えた、データに基づくサービスが可能になってきています。
製造業のCIOとしての醍醐味は、その複雑性にあります。ソフトウェア企業などと違い、物の仕入れや製造、在庫管理といった複雑な要素があり、これをITで支える難易度は高いのです。その分、CIOの役割も重要で、醍醐味も感じています。
──友岡さんが考える「理想のCIO」とは、どのようなスキルやマインドセットを持つ人でしょうか。
技術的な知見はもちろん必要ですが、それ以前に、自社の「事業」と「お客様」を深く理解していることが大前提です。
自分たちの事業は何のために存在するのか? お客様の最大のお困り事は何か? 我々が提供すべき本質的な価値は何か? これを常に問い続け、IT戦略を事業戦略と一体のものとして考え、実行できること。これがCIOの最も重要な資質だと思います。お客様やご利用者様に対する理解を怠れば、事業価値を見誤り、市場の変化に取り残されかねません。
──最後に一つリクエストをさせてください。これからCIOを目指す若手エンジニアにアドバイスをください。
私自身、30代前半はEDIのエラー対応に明け暮れる毎日でした。COBOLプログラマーからキャリアをスタートし、決して華やかな仕事ばかりではありませんでした。しかし、その経験が無駄だったとは全く思いません。EDIの仕事を通じてグローバルなビジネスの流れを、COBOLを通じて基幹システムがビジネスをどう支えているかを、肌で学ぶことができたからです。
皆さんが今、どんな仕事を担当しているとしても、それが一見すると地味に見えたとしても、決して腐らないでほしい。その仕事を通じて、そのシステムの裏側にある「ビジネス」を理解しようと努めてください。
システムを通じてビジネスを深く深く理解すること。それが将来、必ず大きな力になります。

「自分の今の仕事をつまらないと思わないこと」。どんな仕事であれ、「他の誰がやるよりも、自分がいちばん高い質でやり遂げる」という気概を持つことです。
周りの華やかな仕事が羨ましく見えることもあるでしょう。でも、そこでふてくされず、今ある環境でベストを尽くす。「皿に盛られた飯を食え」という言葉がありますが、好き嫌いせず、与えられたものを慈しみ、徹底的に磨き上げる。その経験が、間違いなく皆さんを成長させます。
もちろん、会社から与えられた仕事だけが全てではありません。それとは別に、自分自身で学び続け、スキルを磨き続ける努力も不可欠です。幸い、今はオンラインでいくらでも学べる時代です。「会社がクラウドに消極的だ」と嘆く前に、「もし明日GOサインが出たら、自分はすぐにクラウド戦略を推進できるか?」と自問してみてください。
チャンスは、準備ができている人のところにしか訪れません。「自分はレンガを積んでいるだけだ」と思うのではなく、「自分は将来、壮大な教会を建てるために、今、このレンガを積んでいるんだ」という意識を持つこと。また、とにかくまず、小さくてもいいから「動くもの」を作ってみることも大事です。プロトタイプを見せることで、周りの理解や協力を得やすくなりますからね。
受け身ではなく、自ら未来を切り拓く。その気概を持つ若い人たちが、これからの日本のIT、そして日本の企業を力強く変えていってくれることを、心から期待しています。一緒に歩んでいきましょう。
IT最新事情 第3版
世界4,000人のITリーダーから得た調査結果から、AI・自動化・セキュリティなど最新のトレンドを探ります。

企画:植野大輔、池上雄太
執筆:池上雄太、森石豊 / 株式会社スタジオユリグラフ
撮影:遥南 碧
取材・編集:木村剛士












