10分でおさらい、DXの「ナゼ」と「ナニ」
本動画では、DXの本質やDX時代における収益性向上のポイントをおさらいします。DXの定義を再確認し、あらためて理解を深めたい方はぜひご覧ください。
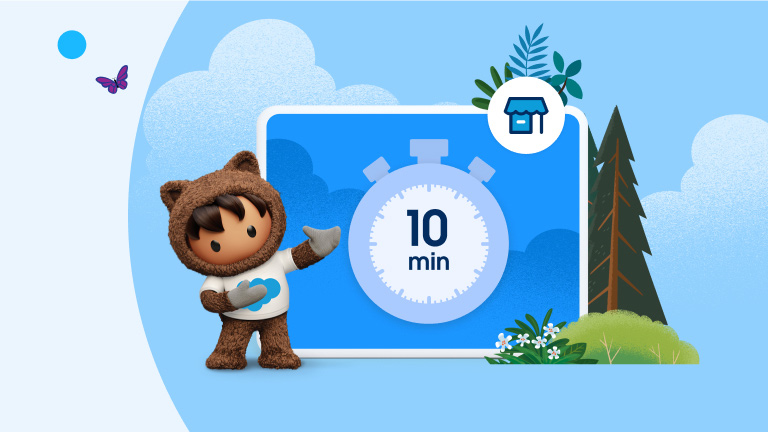
外資系テック企業から一転、日本の人材サービス会社に
──経歴をみると、アルテミス、ベリサイン、シマンテックと外資系テックカンパニーを経験した後、一転して日本の人材サービス会社、インテリジェンスに移籍しました。それから12年になります。外資系IT企業から日本の人材サービス会社への転身。大きくキャリアを変えてきました。
朝比奈:最初のキャリアは、ITプロダクト・サービスを提供する側にいて、開発を担当していました。ただ、エンジニアリングは好きだったのですけれど、才能がないことに気づきまして(苦笑)。
そこからキャリアに迷い、さまざまな役割を経験しました。コーポレートマーケティングやプロダクトマーケティング、経理や人事……。もう迷走状態(苦笑)。結果的に多様な職種を経験することで、ビジネスアナリスト(BA)のポジションなら当時の全ての経験が活かせるという答えに辿り着き、ベリサインで社内情報システム部門のBAに着任し、コーポレートIT分野に進みました 。

パーソルテンプスタッフ株式会社 執行役員 CIO
外資系プロジェクトマネジメントソリューションベンダーにてプロダクト開発、導入を中心に担当。外資系ITセキュリティ会社2社でコーポレートIT部門のリーダーシップを執った後、2014年にインテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社。2021年よりパーソルホールディングス グループデジタル変革推進本部 本部長としてグループ全体のデジタル変革を推進。2025年より現職。2024年度(第42回)「IT賞(マネジメント領域)」受賞、第9回「HRテクノロジー大賞人的資本経営部門」優秀賞、「JAPAN HR DX AWARDS 2024 特別賞」を受賞。
その後、手掛けていた大規模プロジェクトがあと少しで完成という矢先、会社が買収されます。私は買収元企業に移り、PMI(*)のジャパンリードを担当しました。
*PMI:Post Merger Integrationの略称。企業合併後、相乗効果を出すために文化や組織、制度などを統合していく取り組み。
当時、買収元・買収先企業ともに、本社がシリコンバレーの隣り同士だったのですが、カルチャーが全く違って。その前も外資系企業にいたのでM&Aには慣れていたものの、PMIが非常にドラスティックで短期的な結果を求められるようになりました。刺激的な環境の醍醐味を味わっていたものの、中長期の視点をもって、プロダクトやサービスを作り上げる喜びを求める気持ちが強くなっていきました。
その中で、シリコンバレーのITエンジニアたちは楽しそうに仕事をして高給を得ているのに対し、日本のITエンジニアは優秀なのにはたらく環境に恵まれていない。人材サービス業に興味を持ち、これまでの経験を生かしてテクノロジーで日本の人材サービス業を強くしたいと考え、当時のインテリジェンス(現パーソルキャリア)に移ることを決めました。
──インテリジェンスの魅力は何だったのですか。
社員が会社に対して強いロイヤリティを持っていること。そして当時のCIOが描いたIT戦略が魅力的だったことと、テクノロジーで会社を進化させたいという経営層の強い意志があったことですね。
──移籍後、ギャップを感じましたか。
それはもう、とてもとても感じましたよ。入社後、最初の10か月ほどは機能停止状態(笑)。入社直後は、アルバイト求人事業「an」のIT責任者を務めていたのですが、そもそも人材ビジネスが分かっていないから言葉が通じない。何が話されているのか理解できず萎縮して引っ込んでいる時期もありました。日系企業が初めてでしたので、外資系とは全く異なる日本風の文化に適応するのにも時間がかかりましたね。

直面したホールディグスIT部門の「疲弊」
──華麗なキャリアの中に、そんな苦労があったんですね。2021年には、パーソルホールディングスのデジタル変革推進本部本部長に就き、グループ全体のDXの陣頭指揮を取ってきました。経緯を教えてください。
anの事業で大きな商品改定を行ったのち、ホールディングスに移り、パーソルグループで新規事業創出を担う会社の立ち上げをしていました。そんな中、ホールディングス内のIT部門の疲弊を耳にしました。
ホールディングスのIT部門が担うシステムは、複数の事業会社を横串で繋ぐ人事やファイナンスなどのコーポレート系のシステムで、多様で複雑。難易度はそもそも高いんです。
それにも関わらず、その当時のパーソルグループでは、M&Aが頻繁に行われ組織再編もたびたび発生します。エンドレスな状態でPMIが続いているのにIT部門の人数は少人数。メンバーは疲れ果て、チームは崩壊状態でした。また、当時の風潮として、ホールディングスのIT部門は力が弱く、他部門から、「あとはやっておいて」と丸投げされるような状況でした。
グループデジタル変革推進本部の当初の発足目的は、データを活用した新規事業の創出でした。ただ、私はこの現状を目の当たりにし、最優先すべきは組織の立て直しと提言し、この職を受けたんです。
立て直しにあたっては、業務の整理や方針の策定、浸透などさまざまなことに取り組みました。現在、グループ全体として2023年から進めている中期経営計画の最中で、今期が最終年度なのですが、この中計におけるテクノロジー戦略の両軸は、テクノロジーによる「顧客体験向上」と「社員のはたらく体験の向上」。
顧客向けのサービス向上は当然ですが、社員の体験を向上させることもそれと同等に重要。社内でより良いデジタル体験を得て力を発揮できるようになった社員が、さらに新しいものをお客様に向けて生み出していく。このサイクルを回すことに力を尽くしてきました。
振り返ると、成果を上げることができたプロジェクトもあれば、まだ取り組めていないこともあります。ただ、ホールディングスのIT部門の立ち位置とミッションを明確にし、組織と人を強くできたこと。そして社員向けのデジタル環境とはたらく環境を改善する多くのプロジェクトを推進できたことには成果を感じています。

──中計の最終年度にも関わらず、この4月には事業会社のパーソルテンプスタッフに籍を移し、CIOを務めています。ここにはどんな思いがあるのですか。
グループ全体のテクノロジー活用は進んだ感触を得ている一方で、事業そのものをテクノロジーで磨いていく取り組みは、まだ道半ば。拍車をかけたいと思い、中核事業会社のパーソルテンプスタッフの中に入ってDXを加速させていきます。
パーソルテンプスタッフの事業は「企業」と「はたらく個人」のダブルカスタマーモデル。法人向け施策に個人向け施策、マッチング施策、そしてそれを支えるオペレーションとプラットフォーム。これら全てを磨いていきます。キーワードは、「高速化」と「省力化」。そして、それを支えるテクノロジーが「データ」と「AI」です。
業務そのものやプロセスを徹底的にDXしていきます。高速化してお客様の満足度を上げていきますし、社内プロセスは省力化を進めています。わかりやすい例でいえば、マッチングプロセス。人材が欲しい企業とはたらきたい個人の最適なマッチングを迅速に行えれば、両者どちらにも喜ばれますよね。

──この中計期間中にさまざまな第三者機関からデジタル改革に対して表彰されています。直近では、「JAPAN HR DX AWARDS 2024」特別賞」を受賞しています。
受賞理由は、生成AI活用に関する取り組みを評価いただいたことでした。グループ社員が自律的に新しい技術を学び、自ら積極的に業務に取り入れて改善する。そしてそれらを学び合う“共創する文化”を作ることができたことを評価いただいたのです。
こうした社員が自発的にテクノロジーを取り入れるカルチャーを実践できたこともこれまでの成果だと思います。
第三者機関にも評価されたAIを浸透させるための秘訣
──受賞理由にもなったAI活用について教えてください。まず朝比奈さんはAIをどのように捉えていますか。
「ChatGPT 3.5」が出た時、「これは凄い」と。過去のAIはシステムの奥の方にあるものでしたが、生成AIの登場によって完全にフロントに来た。私自身、第二次ブームのときにAIの開発をしていたこともあるのですが、AIに自然言語で触れられるようになったことは、本当に衝撃的で鳥肌が立ちました。
2023年に生成AIが勃興してきた時期、人材業界では個人のプライバシー保護を重視するために警戒心が強く、AI活用に慎重な風潮が広まっていました。しかし、「ChatGPT」の普及を目の当たりにして「使わないことのほうがリスクになる」と強い脅威を感じて、導入を急ぎました。
──新しい技術を社内に浸透させたいけれど、反対勢力があったり、リテラシーが低かったり、活用の可能性を感じられなかったりして、なかなか進まないケースも多いです。社員が自律的に学び合う文化をどのように醸成したのですか。
まず、人材サービス企業として社内で安全にAIを使える環境作り、セットで守らなければならないガバナンスルールを整備し、「この範囲内であれば安全」というガードレールを作りました。
新しい技術に取り組みたいと思っている人はどの組織にも散らばっています。そんな「ファーストペンギン」的な人たちをピックアップしてエンカレッジすることにも取り組んで、「やってみようよ、サポートするから」という形で輪を広げていきました。

生成AIの導入方法には、2つのパターンがあります。最初からたくさんのプロンプトを用意して「このように使うと便利」と示すパターンと、まず自由に使ってもらうパターンです。
私たちは後者を選び、「これはいい」と思ったプロンプトを皆で共有する「プロンプトギャラリー」というものを設けて、そこから自発的な展開が広がっていきました。こうした動きを加速するための社内イベントも頻繁に開催して、導入の敷居を下げることにも力を注ぎました。
また、生成AI活用を進める際には、正しい知識も必要なので、セキュリティに関する社内勉強会や、大規模言語モデルの動作原理についての研修を、ITバックグラウンドを持たない人にも分かるような形で、繰り返し提供しました。
レイヤー別にも、色々な仕掛けをしました。ボトムアップの層への発信を行いながら、グループ会社の経営陣向けには私の名前で書いた生成AIに関するメールマガジンを定期的に配信しました。カジュアルな文体で「こんなすごいことが起きたんですよ」と親しみやすく伝えたり。レイヤーによって訴求方法は変えますが、何より大切なのは、楽しそうにやることですね。実際、AIの活用は楽しいですし、その楽しさが伝わったことで、少なからず普及につながったと思います。
──経営陣のリテラシーや関心度合いは上げながら、全社で進めるための合意はどのように取り付けたのでしょうか。当時はまだ多くの企業が生成AI導入に慎重だったと思います。
まず配下のエンジニアに声をかけ、社内GPTのプロトタイプを作り始めました。同時に法務部門に声をかけ、生成AI利用に向けてのルール整備を一緒に行ってほしいことを依頼しました。
プロトタイプはおよそ2週間ほどで一定使えるものができました。当時は大手コンサルティングファームの方々が、企業トップマネジメントへの生成AIに関する啓発活動を活発化させていたタイミングでしたので、役員が集まるオフサイトミーティングで生成AIの勉強会を開催。勉強会後に私から「既に生成AI環境を作り始めています」とプレゼンしました。
経営陣から「リスクはあるの?」と聞かれたので、「安全面は大丈夫。ルールも準備した。ただコストが読めないので、上限を決めて様子を見ます」と説明しました。誰からもノーと言われないような提案をしながら、既に動き出していることを示す。
そうして経営陣から「それほど大事なものをリスク低くできるなら、やればいい」という反応を得て、プロジェクトはスタートしました。私のコミュニケーションスタイルでもある「もう作ってます。大丈夫だから行きましょう」という前向きな姿勢で経営陣を安心させたんです。

理想のCIO像—経営者としての視点
──最後に、朝比奈さんが考える理想のCIO像を教えてください。どのようなスキルやマインドセットが必要だとお考えですか。
私が教えてほしいくらいですが(笑)、他社の素晴らしいCIOの方々に触れて感じるのは、優秀なCIOは「CIOとは経営陣の一人である」と明確に意識していることです。
テクノロジー部門のトップですから、テクノロジーを当然深く理解していなければなりません。ですが、それと同等に、企業が進むべき方向性、その実現のためにはどんな戦略と実行方法が必要かを描く。そのうえで、それをテクノロジーでどう支援するかを考える。
CIOとは経営者なのです。単なるIT部門、テクノロジー部門のリーダーではありません。それを強く意識している人は、自然と語る言葉も事業部門との向き合い方も変わってくるし、自社のビジネスに対する解像度が高く愛着が強い。理想のCIOとはそのような存在ではないでしょうか。
信頼できる生成AIを実現するために準備すべき6つの戦略
信頼は生成AIによるビジネス変革のための要です。信頼を礎にすることで始めて、生成AIの可能性を自由にビジネスに活用できるようになります。

企画:池上雄太
撮影:遥南 碧
取材・執筆:木村剛士

























