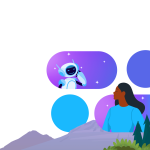あなたは普段、AIをどれくらい活用していますか?
AIは急速に進化し、業務効率を大きく向上させています。ビジネスの現場でもAIを活用できるスキルは、今や武器です。特に入社1年目からAIを使いこなせると、業務の理解も早まり、成果も出やすくなります。
今回は、日頃から仕事に役立つ情報を発信しているインフルエンサー4人に、入社1年目で覚えておきたい、AI活用術を伺いました。業務で迷ったとき、AIの力をどう活かすか?そのヒントをお届けします。
目次
【セールスフォース流Salesforce活用術】セールスフォースが実践する6つのAI活用法
SalesforceがどのようにAI活用で成約率50%以上UPや顧客満足度(CSAT)52%UPを実現しているのか、具体事例をもとに解説します。

1. メモが活用されずに埋もれている
「要点の整理」と「誤解が生じそうなポイントの指摘」を依頼

たべっち
会議や勉強の場でメモを取っても、後で見返さずに埋もれてしまうことはありませんか?書くだけで満足してしまい、整理や活用まで手が回らないことは頻繁にあります。
そんなときは、AIでメモを整理してみましょう。会議後に思いつくまま入力し、「要点を整理して」と指示すれば、簡潔なまとめがすぐに得られます。ただし、重要なポイントが抜けることもあるため、「この内容で誤解が生じそうな点を指摘して」と追加で指示を出すと、曖昧な部分も明確になります。
また、会議中にメモを取る余裕がない場合は、録音データから文字起こししてくれるAIを使うのも有効です。さらに、「この内容を発展させるには?」と質問すると、新たな視点も得られます。
AIを活用することで、メモを効率よく整理し、実際に使える情報へと変えられます。ぜひ試してみてください。
2.「ちょっと調べておいて」に時間がかかりすぎる
リサーチは、「具体的な質問」で「まとめ」と「抜け漏れ確認」も

たべっち
私もリサーチに時間がかかりすぎて、本来の業務が進まないと感じることがありました。膨大な情報を整理するのは大変ですが、AIを活用すれば、必要な情報を効率よく集められます。
まず、リサーチの目的を明確にすることが大切。「2024年の日本におけるBtoBマーケティングのトレンドを3つ教えて」といった具体的な質問をすると、的確な回答が得られます。一方、「マーケティングについて教えて」といった曖昧な質問では、求める情報が得られにくくなります。
さらに、AIの回答をそのまま使わず、「簡潔にまとめて」や「この内容で抜け漏れがないか確認して」と指示すると、より精度の高い情報に仕上がります自分で検索して最新情報を補完すれば、より正確なリサーチが可能です。
このプロセスを取り入れることで、リサーチ時間の短縮と、質の向上が同時に叶います。AIをうまく活用し、リサーチ業務の負担を減らしてみてください。
3. 議事録をきちんとまとめるのが大変
短時間で作成するには「フォーマットの用意」と「文字起こし」が重要

たべっち
私も会議中にメモを取るのが追いつかず、後で整理に時間がかかり、次のアクションが遅れることがありました。こうした負担を減らすためにも、AIの活用は効果的です。
まず、リアルタイムで文字起こしできるAIを使えば、発言の抜け漏れを防ぎ、録音を聞き返す手間も省けます。そのデータを元に「決定事項と次のアクションを要約して」と依頼すると、短時間で要点を整理できます。さらに「重要な論点が抜けていないか確認して」と追加指示を出せば、精度もアップします。
また、事前に「会議の目的」「決定事項」「アクションアイテム」といったフォーマットを用意し、AIに「この形式でまとめて」と指示すると、一貫性のある議事録が完成します。
AIを活用することで、議事録作成の時間を短縮し、会議後のアクションをスムーズに進められます。ぜひ試してみてください。
4. 依頼されたことにうまく対応できない
依頼内容の再確認が必要だが、まずはAIに「何を聞けば良いか」を確認

オクシン
依頼内容を再度確認・ヒアリングを行う必要がありますが、まず「何を聞けば良いか」をAIに確認しましょう。下記のような解答が得られました。
・目的や背景を確認する
・成果物のイメージや完成形を具体的に聞く
・期限・優先度を明確にする
・作業範囲・担当範囲の確認
・コミュニケーション方法、確認タイミングを決める
・要望の優先順位や制約条件を確認する
・内容をまとめて上司や先輩に最終確認してもらう
上記をこのままAIに聞くのではなく、自分なりの解答は持っておいた方が良いでしょう。AIはあくまでもアシスタントなので、自分で考えることが大切です。例えば「目的や背景」について考える際には「営業のアポイント獲得の増加」という具体的な目的を自分で設定しておきます。自分の考えを整理し、明確にしたうえでAIに質問を投げかけることで、より効果的な結果を得ることができます。
5. 業務に追われてバタバタしてしまう
「タスクの洗い出し」と「優先順位の決定」が重要

オクシン
仕事を円滑に進めるためにやることは「タスクの洗い出し」と「優先順位の決定」の2つです。それらを自分に合った方法で管理することが重要。仕事を進めるのが上手な人は、マルチタスクではなく、シングルタスクに振り分け高速で終わらせています。
仕事を「美味しいカレーライスを作ること」に置き換えるとわかりやすいです。
AIに「美味しいカレーライスを作る手順を教えてください」と質問すると「下ごしらえ、炒める工程、時短方法、味付け、仕上げ」など、具体的な手順を教えてくれます。さらに、「美味しいカレーライスを作る工程の優先順位を教えてください」と質問すると、作業工程の順番を教えてくれます。
カレーライスだと、野菜を切っておく、煮込みの工程、お湯を湧かしたり米を炊くタイミングです。米を炊くのに30~40分と考えると優先順位が上がりますよね。また、お湯を湧かすまでに5分程度の時間があるとすると、その間に別のタスクを行なえます。
これを仕事に応用すると、AIに相談しながら、どのタスクをどの順番で終わらせていくか、使えるリソースは自分以外にはあるか、ツールは使えるかを加味した上で意思決定を行うことで、仕事をスムーズに終わらせることが可能になります。
6. 発注先に急ぎの依頼をメールするのが苦手
「メール送信前のAIチェック」で認識のズレを排除

はるゆき
発注先へのメール、「なるべく早く」という言葉を使っていませんか?実はこれ、相手を困惑させ、取引に悪影響を及ぼす可能性が大です。「早く」の基準は人それぞれ。認識のズレが納期遅延やトラブルを招くことも……。
そこで試したいのが、メール送信前のAIチェック。「なるべく早く見積書を送ってください。この文章、伝わりますか?」とAIに問いかけましょう。AIはこう答えます。「〇〇株式会社の〇〇(商品名)の見積もりを、〇月〇日〇時までにメールでご送付ください。見積書には、内訳と納期を記載し、有効期限は〇日間でお願いします。」このように、期限、提出方法、記載項目、有効期限を明示することで、依頼内容が明確になります。
AIは最適な表現を提案してくれる強力なパートナーです。「言った言わない」のトラブルを防ぎ、発注業務をスムーズに。メール送信前のAIチェックで、あなたのビジネスコミュニケーションは劇的に改善されるでしょう。
7. プレゼン資料のストーリーが決まらない
聞き手を惹きつけるために、「複数のプレゼン構成案」を依頼

はるゆき
プレゼン資料の構成、いつも頭を悩ませていませんか?聞き手を惹きつける構成を考えるのは、時間も労力もかかります。
そこで試したいのが、プレゼン台本作成におけるAIとの共同作業。「〇〇業界の経営者向けに、自社サービスの導入メリットを訴求するプレゼン資料の構成を考えて」とAIに問いかけましょう。AIは、聴衆の属性やプレゼンの目的に合わせて、複数の構成案を提案してくれます。
例えば、「課題提起→解決策提示→事例紹介→質疑応答」のような基本的な構成案だけでなく、「ストーリー形式で共感を誘う構成」「データに基づいた説得力のある構成」など、さまざまな選択肢を示してくれるでしょう。
さらに、各構成案のメリット・デメリットを比較検討したり、具体的なスライドの流れを提案してもらったりすることも可能です。
AIを上手に活用することで、プレゼン資料作成の負担を軽減し、聴衆を惹きつける魅力的なプレゼンを作成しましょう。
8. スライドデザインが変わり映えしない
伝わるスライドは、「メッセージ生成」と「画像生成」の合わせ技で

つだしん
スライドを作成する際は、「構成」「デザイン」「コンポーネント」の3つの視点を持つことをおすすめします。
まず構成では、スライド全体の流れを最初に考え、1枚につき1つのメッセージを意識します。AIを活用し、スライドで伝えたい内容の大枠を自動生成してもらうことをお勧めします。
次にデザインを決める要素として、フォントの統一、十分な余白、色の使用比率をスライドごとに統一することが挙げられます。最近は画像生成に強いAIもありますから、レイアウトの最適化や配色の生成に活用してみてください。
最後にコンポーネントですが、AIでの画像生成を活用すると、スライドに合ったイラストやアイコンを作成できます。PNGやJPEGといった画像形式ではなく、後から編集可能なSVG形式で出力してくれるAIを使えば、スライドの統一感を保ちやすいです。シンプルで直感的なグラフや図解であれば、データの可視化に強いAIもあります。
様々なAIの特性を組み合わせることで、効率的に、訴求力の高いスライド作成が実現します!
9. アイデアのイメージをうまく伝えたい
伝えたいイメージに近い画像を集めて「添付」

つだしん
アイデアをビジュアルイメージとして伝えるとき、必ずしもオリジナリティが必要というわけではありません。過去の表現をオマージュするのはいかがでしょうか。
デザインの多くは、言語化できるものばかりではありません。無理に言葉で伝えようとせず、伝えたいイメージに近い写真やイラストを集めてみましょう。画像をそのまま送ることでイメージを伝えるという手法は、デザイナーもよく行います。
たとえば、おしゃれで洗練されたイメージを伝えたいときは、私ならまずいくつか似たような店舗、カフェ、ホテルなどを検索し、それらの中からイメージに近い写真をいくつかピックアップして、AIで画像生成をする際に添付します。最近は、グラフィックや図解系のAIも進化していますから、AIを経由することで言葉を見た目に変換する処理をしてみるのもおすすめです。
会話と同じように、イメージを伝える際にも、相手に合わせることも重要です。相手がグラフィックイメージを伝えて欲しいのか、あるいは言語情報のみで意思疎通ができる相手なのか、見極めることも重要ですね。
Salesforceの自律型AIエージェント “Agentforce”ってなんだ?
SaleforceのAgentforceは、自律型AIエージェントを作成して展開するための新しいプラットフォーム。自律型AIエージェントは、ユーザーに代わって業務を実行し、複雑なタスクを自動で処理できます。その様子を、デモでわかりやすく紹介します。

まとめ & インフルエンサー紹介
いかがでしたか。AIは単なる効率化ツールにとどまらず、考えがまとまらない時や、相手への伝え方に迷う時の壁打ち相手として、業務の幅を広げてくれます。
今回ご紹介した活用法の中で1つでも気になるものがあれば、まずは試してみてください。自分なりのやり方を見つけながらAIに慣れていくうちに、仕事の見え方も変わってくるはずです。
インフルエンサー紹介

たべっち(@tabestation)
図解制作/PR/コンサルタント
図解を通して、日々の学びや書籍の要約を発信。見やすいまとめでインプットがしやすいと話題を呼び、わずか8ヶ月間で2万フォロワーを達成。現在は5万人にフォローされています。短期間でフォロワーを増やしたノウハウは、電子書籍『図解でTwitter攻略 8ケ月で2万人と繋がった具体的な方法』(Kindle)で公開。


はるゆき(@haruyuki031)
大手IT企業 営業部長
スムーズなコミュニケーションに必要な「伝え方」のコツを、SNSでわかりやすく発信。現役の営業部長だからこそ話せるリアルな知見を、NG例やOK例を織り交ぜながら説明するスタイルが人気です。学生時代は話すことが苦手でしたが、小売店に就職後、「伝え方」を追究してトップセールスマンに。書籍『伝え方のすべて』(KADOKAWA)を執筆。

つだしん(@tsudashin)
アートディレクター/CIデザイナー
デザイナー/アートディレクター。デザインをビジネスに活用するノウハウや見解をSNSで発信。デザインの仕事でAIをどう活用できるのかについても積極的に模索し、発信中。AI×デザインビジネスシーンで活躍する人材育成サービス「NUTS」も運営。