個人情報の漏洩は、企業にとって非常に深刻な問題です。
もし個人情報が外部に流出したら、企業の信頼性や顧客の安全が脅かされます。法的な責任や経済的損失も避けられません。
このようなリスクを回避するためには、漏洩の原因を理解し、適切な対策を講じる必要があります。
本記事では、個人情報が漏洩する原因とリスクについて解説し、漏洩を防ぐための具体的なセキュリティ対策を紹介します。現在のセキュリティ対策に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
生成AIのリスクを軽減する10の戦略
生成AI活用のためのセキュリティ対策と実践を徹底解説
多くの企業が生成AIの導入を急いでいますが、同時にセキュリティリスクへの対処も必須となっています。 生成AIをビジネスに導入する際に、担当者が考えるべきポイントを10個に集約し、具体的な対策を紹介します。

目次
個人情報や機密情報が漏洩する3つの原因

個人情報が漏洩する主な原因には、外部からの攻撃、内部での不正行為、または従業員のミスなど、さまざまな要素が挙げられます。
例えば、独立行政法人 情報処理推進機構の「情報セキュリティ10大脅威 2024」で挙げられている社会的に影響が大きかったと考えられる脅威のうち、とくに以下の3つは個人情報や機密情報漏洩の原因となります。
- ランサムウェアによる被害、標的型攻撃による機密情報の窃取
- 不注意による情報漏えい等の被害
- 内部不正による情報漏えい等の被害
出典:独立行政法人 情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2024」
ランサムウェアによる被害、標的型攻撃による機密情報の窃取
ランサムウェアとは、ファイルを暗号化し、復号のために身代金を要求するマルウェアの一種です。またデータを暗号化するだけでなく、事前に盗み出して公開をちらつかせる手法も増えています。
標的型攻撃は、特定の組織や個人を狙って高度な手法を用いるサイバー攻撃です。フィッシングメールやソフトウェアの脆弱性を悪用して侵入し、機密情報や個人情報を長期間にわたって窃取することを目的とします。企業がこのような攻撃の標的となり、情報漏洩を引き起こすケースがもっとも多いです。
近年、攻撃の手口は高度化しており、企業にとって大きなリスクとなっています。企業はさらにセキュリティを強化し、外部からの攻撃に備える必要があります。
不注意による情報漏えい等の被害
社員の不注意が原因となることも多いです。具体的には、以下のようなミスや不注意が考えられます。
| 例 | 概要 |
|---|---|
| 書類やPCの放置 | 個人情報が記載された書類やPCを放置し、第三者に見られる |
| 誤送信 | 誤った宛先にメールやファイルを送信する |
| パスワードの使い回し | 複数のシステムで同じパスワードを使い回す |
| 記憶媒体の紛失 | 個人情報が入ったUSBメモリや外付けハードディスクを紛失する |
社員のミスや不注意による個人情報漏洩を防ぐには、定期的な研修の実施など、社員のセキュリティに対する意識を高める施策が効果的です。
内部不正による情報漏えい等の被害
企業内部で起こる個人情報漏洩リスクとして、一部の社員が悪意を持って個人情報を会社から持ち出すケースがあります。
たとえば、退職・転職する社員が顧客情報や機密データを不正に持ち出し、悪用するケースです。
内部の不正行為を防ぐためには、社員に対する監視体制を強化したり、情報管理のルールを徹底したりすることが求められます。
個人情報や機密情報が漏洩した場合の3つのリスク

個人情報が漏洩した場合、企業は重大なリスクに直面します。
主なリスクは以下の3つです。
- 刑事上の罰則
- 民事上の損害賠償責任
- 企業の信用低下・顧客離れ
これらのリスクは企業の経営に深刻な影響を与え、最悪の場合、経営破綻に至ることもあります。具体的にどのようなリスクがあるのか、一つずつ見ていきましょう。
刑事上の罰則
個人情報漏洩が発生した場合、企業や関係者は刑事責任を問われる可能性があります。
たとえば、個人情報保護法に違反した場合、法人に対し、非常に多額の科料が課されることを踏まえ、今後の対応を考える必要があります。情報漏洩に関与した社員や経営者も刑事罰を受けることがあり、場合によっては懲役刑が科されることもあります。
従って、企業は、法律に違反しないようコンプライアンスを強化し、情報漏洩防止のための措置を徹底しなければなりません。
民事上の損害賠償責任
個人情報が漏洩し、それが原因で顧客や取引先に損害を与えた場合、企業は民事上の損害賠償責任を負うことになります。
たとえば、顧客の信用情報が流出し、顧客が金銭的な損害を被った場合、企業はその損害額を賠償しなければなりません。損害賠償額は、漏洩した情報の重要性や影響の範囲によって高額になることがあり、場合によっては数千万、数億円に達することもあります。
機密性の高い情報が漏洩した場合の損害賠償額は、企業に致命的な打撃を与える可能性があり、企業の存続自体に影響を及ぼすかもしれません。
企業の信用低下・顧客離れ
個人情報が漏洩すると、企業の信用は著しく低下し、顧客が離れるリスクが高まります。特に、メディアで漏洩事件が報じられると、企業のブランドイメージが大きく損なわれ、長期的に顧客離れが進む可能性があります。
信頼回復には時間とコストがかかるため、情報漏洩を未然に防ぐための対策を徹底することが、企業にとってもっとも効果的な予防策です。
個人情報や機密情報の漏洩が発生したときの対応手順

個人情報漏洩が発生した際、企業は迅速かつ適切な対応を取ることが求められます。
ここでは、情報漏洩が発生した場合の具体的な対応について、以下の4つのステップで解説します。
- 事実関係を整理して応急処置を行う
- 原因を調査する
- 情報公開を検討する
- 再発防止策を実施する
1.事実関係を整理して応急処置を行う
個人情報漏洩が発覚した場合、最初に行うべきは事実関係の整理です。どの情報が、どこから漏洩したのかを調査し、迅速に漏洩元を特定しましょう。
漏洩元が特定できたら、必要に応じてシステムを一時的に遮断するなどの応急処置を行います。これにより、さらなる情報漏洩を防ぐことが可能です。
万が一個人情報漏洩が発生しても、企業が迅速に初動対応を行えば、情報漏洩の被害を最小限に抑えられます。
2.原因を調査する
初動対応の後は、再発防止に向けて情報漏洩の原因を徹底的に調査しましょう。
具体的には、システムのログや関係者へのヒアリングを行い、情報漏洩がどのように発生したかを調査します。内部のセキュリティ体制や管理体制に問題がなかったかを洗い出し、外部からの攻撃や不正アクセスがあった場合の経路も確認します。
再発を防止するための効果的な施策を打ち出すためには、情報漏洩の原因を明確にすることが重要です。
3.情報公開を検討する
原因を特定できたら、情報漏洩の事実をいつ、どのように公開するのかを検討します。
企業の透明性を確保するためには、顧客や取引先に情報漏洩の事実を適切なタイミングで通知する必要があります。情報の公開が被害の拡大を招く恐れがある場合は、公開の時期や対象を慎重に検討しましょう。
情報公開の際には、漏洩した事実を隠すことなく誠実かつ適切な説明を行い、顧客や取引先からの信頼回復に努めなければなりません。
4.再発防止策を実施する
情報漏洩の原因が特定された後は、調査結果をもとに再発防止策を速やかに実施しましょう。再発防止策の実施は、同様の事故発生防止や、企業のセキュリティ体制強化につながります。
効果的な対策を維持するためには、定期的なセキュリティチェックを行うことも重要です。
再発防止策の実施と定期的なセキュリティチェックを通じて、同様の事故発生を防止しましょう。
個人情報や機密情報の漏洩を防ぐための6つのセキュリティ対策

個人情報や機密情報の漏洩を防ぐためには、効果的な対策を実施し、セキュリティ体制を強化することが重要です。
ここでは、機密情報漏洩を防ぐために実施すべき基本的なセキュリティ対策と、特に企業において追加で対策すべき内容についてをご紹介します。
基本的なセキュリティ対策
- 多要素認証(MFA)の導入
- アクセス権限の制限
- データの暗号化
- デバイス管理体制の強化
- 社員研修の実施
- 守秘義務契約の締結
追加で考慮すべき対策
- 特定のデータ項目の変更履歴、不審な操作やデータのアクセスパターンのリアルタイム追跡
- インシデント対応計画の策定
- ゼロトラストモデルの採用
- 定期的な侵入テスト
- バックアップと復元プロセスの整備
基本的なセキュリティ対策
下記の対策を一つずつ見ていきましょう。
多要素認証(MFA)の導入
多要素認証(MFA)は、システムへのアクセス時に複数の認証要素を組み合わせて、セキュリティを強化する方法です。
以下に、代表例として、三要素認証の3つの要素を挙げます。
| 種類 | 概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 知識要素 | 自分だけが知っている情報 | ・パスワード ・秘密の質問 |
| 所有要素 | 自分だけが持っているモノ | ・スマートフォン ・ハードウェアトークン ・社員証などのICカード |
| 生体認証要素 | 自分だけが持っている特徴 | ・指紋 ・顔 ・声紋 |
たとえば、パスワード(知識要素)と指紋認証(生体認証要素)を組み合わせることで、セキュリティ強化を図ります。パスワードを入力した後に、スマートフォンで受け取った認証コードを入力するログイン方法も、多要素認証の一種です。
以下の記事では、多要素認証の定義や導入のポイントを詳しく解説しています。セキュリティ対策を実施する際に、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:不正ログインを99.9%防止「多要素認証」の重要性
アクセス権限の制限
個人情報漏洩を防ぐためには、データへのアクセス権限を制限することが効果的です。
社員全員がすべての情報にアクセスできる状態では、ヒューマンエラーや内部の不正による情報漏洩が発生しやすくなります。社員のアクセス権限を、業務に必要な情報や機能に制限することで、誤操作や不正アクセスの機会が減少し、情報漏洩の発生を防ぐことができます。
また、社員の異動や退職に応じて、定期的にアクセス権限を見直すことも重要です。これにより、不要な権限が残ることを防ぎ、第三者による不正アクセスを防止できます。
データの暗号化
データの暗号化は、個人情報漏洩を防ぐための基本的かつ強力な対策です。
企業は顧客情報、社員データ、機密情報など、膨大な個人情報を保有しています。これらのデータを暗号化して保存することで、万が一情報が漏洩した場合でも、その内容が解読されるリスクを抑えることが可能です。
データの暗号化は、保存時だけでなくインターネット経由での送信時にも必要です。通信中のデータを暗号化することで、外部からの盗聴や改ざんを防ぐことができます。
デバイス管理体制の強化
企業内で使用されるデバイスの管理体制を強化することも、個人情報漏洩の防止には欠かせません。
なぜなら、社員が業務で使用するPCやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに保存された個人情報も、盗難や紛失によって情報漏洩するリスクがあるからです。
デバイス管理体制の強化には、以下のような対策が効果的です。
| 対策 | 概要 |
|---|---|
| リモートロック | デバイスが盗難や紛失に遭った場合、デバイスをリモートでロックする |
| リモートワイプ | 紛失したデバイスに保存されたデータをリモートで消去する |
| MDM(モバイルデバイス管理) | 社員のスマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを一元管理する |
これらの対策を実施することで、盗難や紛失が発生した場合でも個人情報を保護することができ、企業全体のセキュリティ強化につながります。
社員研修の実施
社員のセキュリティ意識を高めるためには、社員研修の実施が効果的です。
研修では、セキュリティに関する基本的な知識や、個人情報保護法を遵守する重要性をすべての社員に理解させることが重要です。特に、マルウェアやフィッシング詐欺への対策、パスワード管理の重要性を教えることは、情報漏洩防止に直結します。
また、セキュリティポリシーや情報漏洩時の対応方法について教育を徹底することで、企業全体のセキュリティ意識を高め、情報漏洩のリスクを軽減できます。
社員が不正な操作やミス、不注意を犯さないよう、定期的なセキュリティ研修を実施しましょう。
守秘義務契約の締結
守秘義務契約とは、企業が社員や業務委託先と結ぶ契約で、業務で扱う情報を外部に漏洩しないように義務づける契約です。
この契約により、情報漏洩が発生した場合の法的責任を明確にし、情報の取り扱いに対する責任感を強化できます。
特に、契約社員や外部業者などの第三者と連携する場合は、契約に情報の取り扱いや漏洩時の対応を明記し、機密情報の漏洩を防ぎましょう。契約違反があった場合のペナルティを設定することも効果的です。
追加で考慮すべき対策
上記の対策は基本的なものですが、徹底することで大きな効果を発揮する、情報漏洩を防ぐための基本的かつ重要な手法です。さらに以下のような追加の対策を検討することで、より強固にセキュリティを強化することが期待できます。
- 特定のデータ項目の変更履歴や不審な操作やデータのアクセスパターンのリアルタイム追跡
- インシデント対応計画の策定
- ゼロトラストモデルの採用
- データ損失防止(DLP)ツールの導入
- 定期的なペネトレーションテスト
- バックアップと復元プロセスの整備
特定のデータ項目の変更履歴や不審な操作やデータのアクセスパターンのリアルタイム追跡
SaaS ベンダーなどでは、不審な操作やデータのアクセスパターンをリアルタイムで追跡するツールを提供しています。こうしたツールを設定することで、万が一持ち出しなど問題が発生した際に早期発見と対策に役立ちます(前述の「機密情報漏洩が発生したときの対応手順」参照)。
たとえば、Salesforce の場合、「イベント モニタリング」というセキュリティアドオン製品がありますが、イベント モニタリングは、不正アクセスや異常なデータダウンロードの兆候を検知するのに効果的です。また、「項目監査履歴」を併用すると、特定のデータ項目の変更履歴を追跡し、不審な変更やデータの不正操作を記録することができますので、問題発生時の原因特定や内部不正の抑止につながります。
こうしたツールを活用することで、常よりログデータを集約し、セキュリティイベントを効率的に監視・管理できる環境を整えると、脅威を早期に検知できます。
インシデント対応計画の策定
インシデント対応計画は、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティインシデントが発生した際に迅速かつ効果的に対応するための手順を文書化したものです。万が一情報漏洩が発生した際に迅速に対応できるよう、対応手順や責任者を明確にする計画を事前に準備することが重要です。
■計画のポイント
- インシデントの種類ごとに対応フローを明確化する(例:データ漏洩、不正アクセス)
- 関係者の役割と責任を明確化する(IT 部門、法務部門、広報部など)
- セキュリティ系のツールなども活用し、即時対応を可能にする
ゼロトラストモデルの採用
ゼロトラストは、「信頼せず、常に確認する」という原則に基づき、全てのアクセスを検証するセキュリティモデルです。ネットワーク内外を問わずすべてのアクセスを信頼せず、常に検証する「ゼロトラスト」モデルを採用することで、内部不正や外部攻撃のリスクを大幅に低減します。
- MFA(多要素認証): アカウント保護を強化し、IDとパスワードの盗難リスクを軽減。
- データ暗号化: Salesforce 内のデータを保護し、アクセス権限がないユーザーには解読不能にする
- 項目レベルセキュリティ、プロファイル設定 : 最小権限の原則を適用し、必要最低限のアクセス権のみを付与
■導入のポイント
- デバイスやネットワークの状況、ユーザーの役割に基づくアクセス条件を設定する
- サービス、システム間の連携においても OAuth 2.0や IP 制限を活用。
(参考 : プロファイルでのログインIPアドレスの制限)
定期的に侵入テストをする
ペネトレーションテスト(侵入テスト)は、第三者が模擬的にシステムを攻撃し、脆弱性を特定する手法です。システムの脆弱性を把握するために、第三者による侵入テストを実施し、未然にリスクを特定・対策を行います。
■導入のポイント
- 少なくとも年1回のペネトレーションテストを計画する
- テスト結果に基づき、セキュリティ設定の見直しやシステムのアップデートを実施する
(参考 : セキュリティ脆弱性の診断提出ガイド )
バックアップと復元プロセスの整備
定期的にデータをバックアップし、災害やランサムウェア攻撃時に迅速に復元できるプロセスを整備します。システム障害やランサムウェア攻撃などに備えて、データのバックアップと迅速な復元プロセスを確立することが重要です。
■導入のポイント
- 定期的なバックアップの実施(毎日または毎週)
- 復元テストを実施し、実際に問題発生時にデータが確実に復元できることを確認
Salesforce Backupによるデータの保護
Salesforce Backupは、Salesforce環境に格納されているデータを安全かつ簡単にバックアップします。操作時点のデータとバックアップデータの比較や復元処理についても画面操作にて簡単に実行可能です。
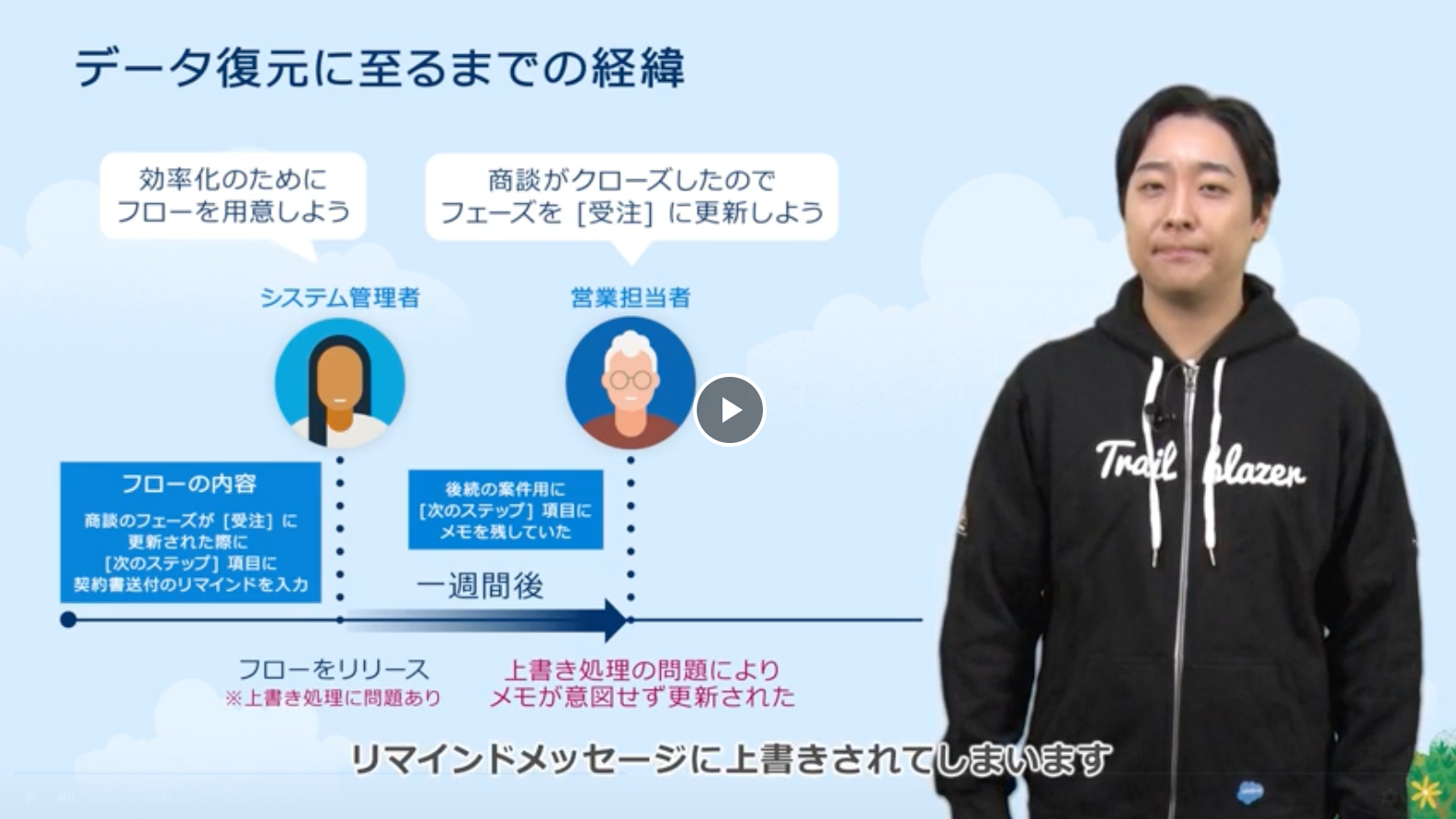
AI技術の進展による個人情報・機密情報漏洩への影響

企業はさまざまな対策を講じてセキュリティ強化に努めていますが、近年のAI技術の進展により、攻撃手法の進化が懸念されています。たとえば、AIを活用したフィッシング詐欺の進化や、機械学習を利用したサイバー攻撃などです。
一方で、AI技術は業務効率化や顧客サービスの向上など、企業に多大な恩恵をもたらしています。
たとえばSalesforceの「Agentforce」は、AIを活用して顧客データを分析し、個別化された営業活動やマーケティングを支援する機能を提供します。この機能により、企業は業務の効率化や、より迅速で効果的な顧客対応を実現できるのです。
このように、AIは企業の業務効率化や顧客対応の向上に寄与する一方で、サイバーセキュリティの新たな課題を生み出しています。そのため、企業はAIによる恩恵を享受しつつも、進化するセキュリティリスクに対応するための対策を強化することが求められています。
生成AIツール利用で無意識に情報漏洩をさせてしまうことも
生成 AI ツールサービスの個人利用版を業務で使用する際には、データ漏洩のリスクが懸念されます。これには以下のようなリスクが含まれます。
- 入力データの不適切な取り扱い
多くの生成 AI ツールは、ユーザーが入力したデータを一時的に保存し、モデルの改善やサービス品質向上に利用する場合があります。企業の機密情報や顧客データを入力すると、その情報が AI システムの学習プロセスに活用される可能性があります。 - データの再生成リスク
入力されたデータがモデルの学習結果に影響を与えた場合、他のユーザーが生成した結果に間接的にそのデータが反映される可能性があります。これにより、意図しない形で機密情報が漏洩するリスクが生じます。 - プライバシー保護が十分でない場合の影響
多くの生成 AI ツールやサービスでは、企業利用向けと個人利用向けでデータ取り扱いポリシーが異なります。個人利用版の場合、企業が求める厳密なプライバシー保護基準を満たしていないケースが多く、データが第三者の管理下に置かれる可能性があります。
生成AIのリスクを軽減する10の戦略
生成AI活用のためのセキュリティ対策と実践を徹底解説
多くの企業が生成AIの導入を急いでいますが、同時にセキュリティリスクへの対処も必須となっています。 生成AIをビジネスに導入する際に、担当者が考えるべきポイントを10個に集約し、具体的な対策を紹介します。

リスク軽減のための推奨事項
上記のようなリスクを軽減するには、以下のような対策を行いましょう。
- 業務利用は企業向けバージョンを使用
業務で生成AIを使用する場合、データ保護が確立された企業向けライセンス(例:Salesforce Agentforce)を利用し、データが学習プロセスに使用されないことを確認しましょう。(参考 : Agentforce を選ぶ理由) - 入力データの取り扱いを厳格に管理
機密情報や個人情報は入力しないポリシーを徹底し、ツールを利用する際にはデータの機密性を考慮します。 - 社員教育の実施
生成 AI の利用に伴うリスクを社員に周知し、適切なツール利用方法を共有します。
生成 AI ツールの活用は業務効率化に大きく貢献しますが、その利用方法を誤ると重大なデータ漏洩リスクを招く可能性があります。適切なツールの選定と運用ルールの策定を行うことで、リスクを最小限に抑えることが重要です。
関連記事:
AIが抱えるセキュリティの問題点とは?AIによる脅威や対策まで紹介
AI導入のメリット・デメリットは?日本の導入率や手順、事例も紹介
信頼できる生成AIを実現するために準備すべき6つの戦略
生成AIをビジネスに導入する際に、担当者が考えるべきポイントを10個に集約し、具体的な対策を紹介します。

「Salesforce Shield」で進化するセキュリティリスクに対応

進化するセキュリティリスクに対応するためには、従来のセキュリティ対策に加えて、高度なセキュリティツールの導入が効果的です。
特に、アクセス制御やデータの監視、暗号化といった高度な対策が、リスクを最小限に抑えるためには不可欠です。
Salesforceのセキュリティ製品群は、これらの対策を効果的にサポートし、個人情報保護のレベルをさらに向上させることができます。
たとえば「Salesforce Shield」は、次のような機能により企業の情報漏洩リスクを低減させます。
- ユーザーアクティビティの監視と異常検知:不正アクセスや不適切な操作のリスクを軽減
- データの暗号化:外部および内部の脅威から重要データを保護
- データ追跡と記録管理の強化:企業の透明性を確保
こうした機能により、企業はデータセキュリティを確保しながら、信頼性の高いビジネスを推進できるのです。
個人情報や機密情報の漏洩を防ぐための対策を実施しよう

個人情報漏洩を防ぐためには、企業がしっかりとしたセキュリティ対策を講じる必要があります。
具体的には、アクセス権限の制限やデータの暗号化、社員研修の実施などが効果的です。
また、AI技術の進展に伴う新たな脅威に備えるための対策も求められています。
高度なセキュリティツールを活用することで、新たな脅威から個人情報を守り、顧客からの信頼性向上に努めましょう。
責任共有モデルを支えるセキュリティオプション
企業でセキュリティに関わるすべての方に向けて、Salesforce が提供する様々なセキュリティオプションについて、その意義とユースケースを、対応する最新のセキュリティ脅威とあわせてご紹介します。










