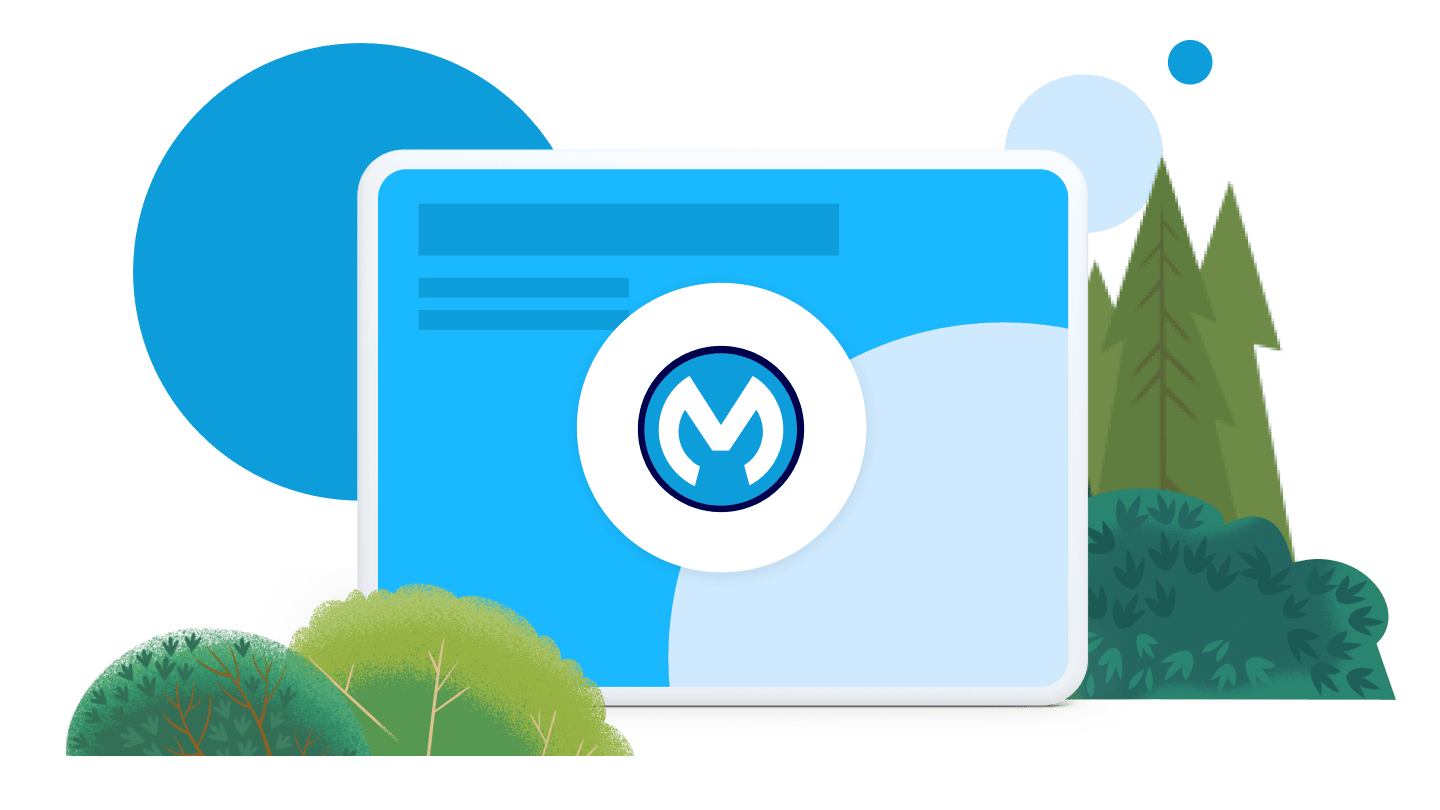資生堂は顧客体験向上からお客さま購買まで販売に関するさまざまな業務の高度化を行っています。また、財務・物流・製造・人事領域を中心にビジネスプロセスの標準化とIT投資の効率化を目指し、グローバル共通の基幹システムとしてSAP S/4導入を進めています。
これまでに世界各地の事業所で構築したシステムには、システム間のデータ連携不足や運用コストの高止まりといった課題がありました。そこで2022年に入って、APIでデータ連携を一元管理する基盤を構築することを目的に「MuleSoft」を導入。その結果、グローバル共通基盤でありながら、各地域の要件にも対応可能な柔軟なインテグレーション基盤を実現しました。さらにAPIの集約・標準化により、プロジェクトのデリバリースピード向上にもつながりました。
こうしたプロジェクトをリードした資生堂のビジネストランスフォーメーション部グローバル戦略ポートフォリオ&ガバナンス室、神永麻以子氏に聞きました。
接続性ベンチマークレポート
自律型AI、インテグレーション、API戦略の洞察
ITリーダー必読、世界1,050人のITリーダーへの調査。自律型AIと企業への影響を分析した価値あるインサイトを提供します。
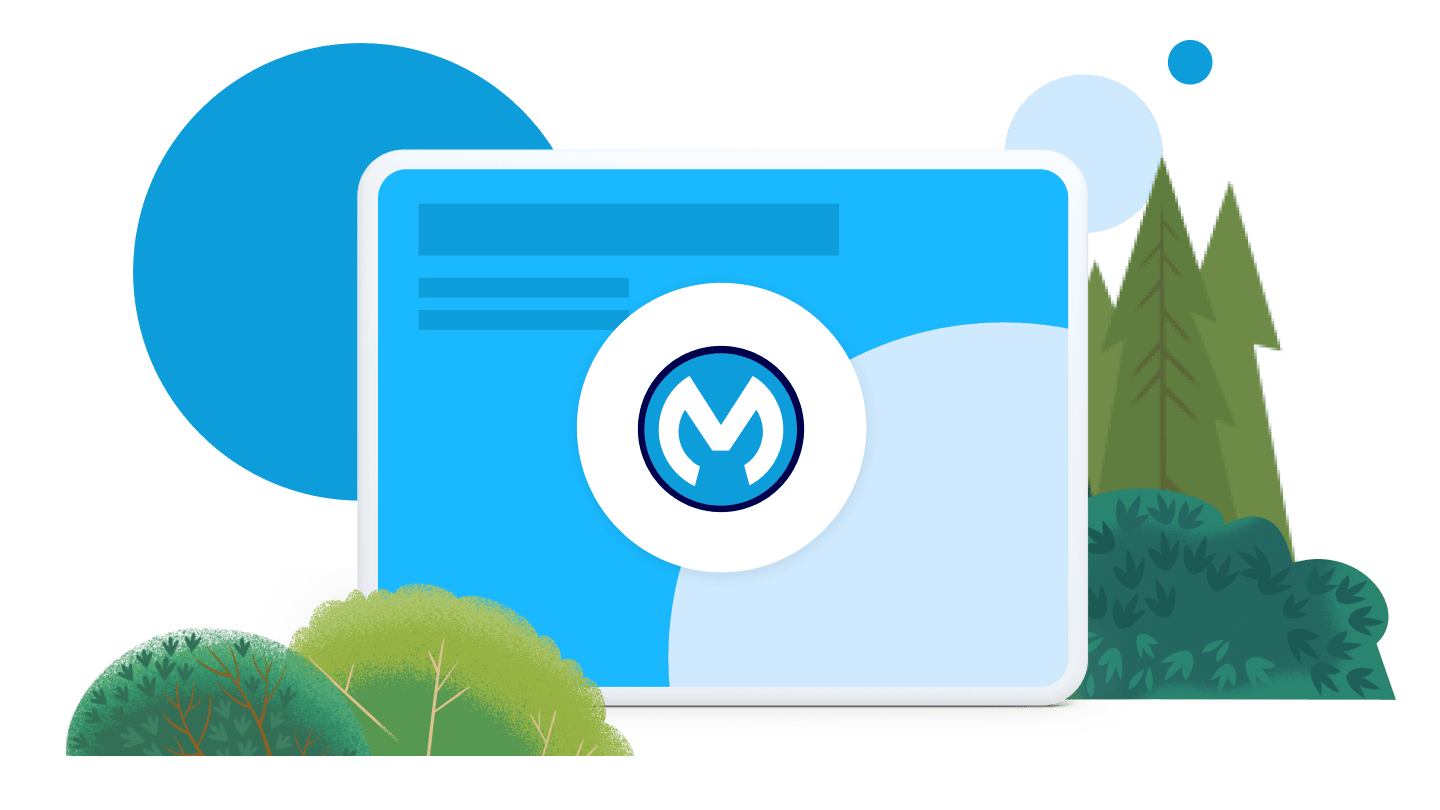
目次
リアルタイムのデータ連携を目指し「MuleSoft」を選択
──まずは、「MuleSoft」を必要とした課題をお聞かせください。
まず1つ目は、世界の各地域で個別にシステムを構築・運用してきましたので、データ連携の仕組みが綺麗にデザインされていなかったことです。マニュアル作業も多く存在しました。
2つ目は、各システムがバッチ処理を前提に設計されていたので、リアルタイムでの連携が困難でした。ビジネスモデルがグローバル化する中で、さまざまなビジネスニーズに対応するうえでのボトルネックになっていました。
3つ目の課題は、各地域が運用してきたレガシーシステムの運用コストが高止まりしていたことです。
これらの課題を解決するために、「MuleSoft」を活用して全世界共通のデータ統合連携基盤を作りたいと考えました。

資生堂 ビジネストランスフォーメーション部
グローバル戦略 ポートフォリオ&ガバナンス室
(肩書きは現在のもの。MuleSoft導入時はグローバルIT戦略室 室長としてプロジェクトをリード)
──なぜ「MuleSoft」でなければならなかったのですか。
まずは、グローバルに展開しているソリューションであることを重視しました。当社ではビジネスとITシステムの両サイドの観点から、グローバルでの標準化を進めています。そのため、たとえば日本と欧州では使えるが、米国では使えないといった制約がない、世界標準のソリューションを求めていました。
ただ、そうは言っても、地域ごとのビジネス環境に適応することも非常に重要です。このため、地域ごとにある程度はシステム運用を柔軟に変更できることも必要と考えていました。
グローバル全体でシステムの標準化を進めつつ、各地域がフレキシビリティを持って運用していける。加えて、セキュリティとガバナンス管理も担保されているという点で、当社にとっては「MuleSoft」が最適なソリューションでした。
アジア・パシフィック地域の導入が終わればグローバル展開が完了
──「MuleSoft」の導入・活用状況とその成果を教えてください。
まず、全世界における「MuleSoft」の導入プロジェクトを管理・統括するC4E(Central for Enablement)チームを立ち上げました。C4Eは「MuleSoft」が提唱する概念でもあり、「MuleSoft」の活用推進を担い、API仕様やドキュメントの標準化をはじめナレッジの集約や提供を行っています。
このチームが2022年4月から5月に日本でプラットフォームを立ち上げ、同年の6月以降は中国、米国、欧州、香港にも順次、展開しました。
導入地域の拡大に伴って、C4Eチームの役割はAPI資産受入と本番運用の管理に移行し、当社のグローバルガバナンスに則って、各地域がプロジェクト導入やAPI開発を担当しています。現在はアジア・パシフィック地域での導入を進めており、これが完了すればグローバルでの導入が一段落します(インタビュー当時。2025年現在では導入完了ずみ)。
「MuleSoft」導入の最大の成果は、グローバルデータ連携基盤を通じて、APIをグローバルに一元管理する体制を整え社内での標準化を実現したことです。
標準化されたアーキテクチャの再利用で、プロジェクト導入のスピードアップにもつながっています。もともと100以上あったAPIを約10分の1に集約できたケースもありました。APIを集約すると、システムの管理・障害ポイントを削減できるメリットがあります。
導入後の3年間は、各地域で順次使い始めていましたが、その後は各地域で「MuleSoft」を徹底活用してスケールアップしていくことを期待しています。当社では、「MuleSoft」のナレッジサイトを用意していて、チームメンバーがAPIやネットワーク設計の説明などを公開しています。社内の異なる地域間でこうした情報のシェアが活発になれば、再利用率が向上して、「MuleSoft」のさらなる活用にもつながっていくと思います。

新プロジェクトごとに「MuleSoft」を適用するスキームを構築
──「MuleSoft」のプロジェクトを成功に導いた要因は何でしょうか。
まずは基礎となるチームが、外部パートナーを含めて5人という少人数で進められたことがあると思います。
ナレッジやプロセスが集約できているのでチームメンバーの対応として「この担当者しか分からない」「このことしか対応できません」というような偏りがありませんでした。
先ほどお話ししたナレッジサイトにはシステム設計やネットワーク接続、データセットの内容などの情報が共有されているので、そこを見れば誰でも速やかにキャッチアップできるようになっています。こうしたナレッジシェアリングのおかげでプロジェクトの推進が円滑になりましたね。異動や退職によるナレッジ消失の危険性も低減できました。
もう1つの成功要因は、ビジネス感覚を持ったメンバーを揃えたことだと思います。社内には基幹システム、CRMやECサイト、人事管理などから収集したさまざまなデータが存在していますが、データセットをどうデザインするかを判断するのが結構難しいのです。
今回のチームではITとビジネスの両方の感覚に長けたメンバーが揃っていたので、データ連携の設計をスムーズに進められたと思います。
あとは、各地域に「MuleSoft」を導入する際の特徴的な対応として、既存システムを「MuleSoft」に置き換えるプロジェクトは行わず、新しいプロジェクトが立ち上がった際に、必ず「MuleSoft」を活用することにしています。このスキームでは、C4Eチームがプロジェクトチームと一緒に、開発した標準API仕様やインテグレーションのメソッドを実装していきます。
既存を置き換えるとなると大事になりますが、新規プロジェクトなら最初から「MuleSoft」ありきで進めることが可能です。さらに地域ごとに協力を仰ぐ外部パートナーは異なりますが、C4Eチームが協力することで構築済みのグローバル標準の仕組みが適用されるため設計・開発工数も削減できる、ということでグローバルと地域の間でWin-Winのスキームを構築し、運用しています。

コアファンが多いのも「Mulesoft」の強み
──最後に今後の展望をお聞かせください。
「MuleSoft」はコミュニティが活発であることも大きな魅力で、日本以外では都市ごとに万単位のエンジニアが集って、再利用性の高いAPIなど「MuleSoft」に関するさまざまな情報交換をしています。
当社のメンバーもそうですが、みんな「MuleSoft」のファンですよ。そういったファンの人たちはこの技術に対するプライドがあり、プロジェクトを進める解決手法を持っているという点でも心強いですね。
そうした人々をもっと巻き込めるようにチームの増員も視野に入れて、各地域の信頼できるパートナーさんとも一緒に協力しつつ、システム内製化を強化していきたいと考えています。
これまでの3年はみんなで「MuleSoft」を使い始める3年でした。ここからは今後の資生堂ビジネスの成長に欠かせない基盤として更に活用の幅を広げていきたいですね。
MuleSoft for Agentforce
Agentforceの力を最大限に引き出すMuleSoft。データ統合の課題を解決し、安全なAIエージェント連携で業務を自動化。自律型AIで生産性を高める方法をガイドで解説します。