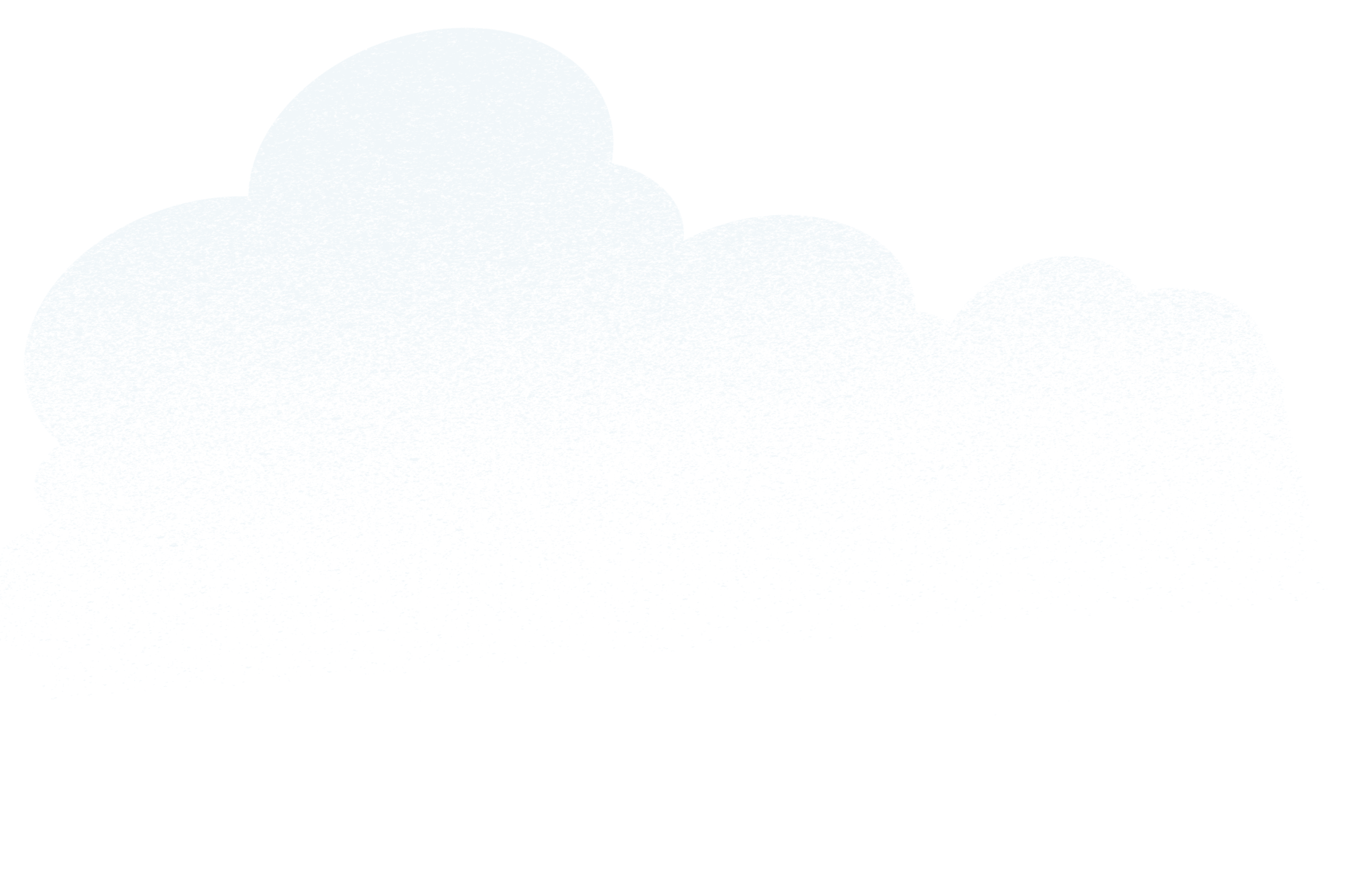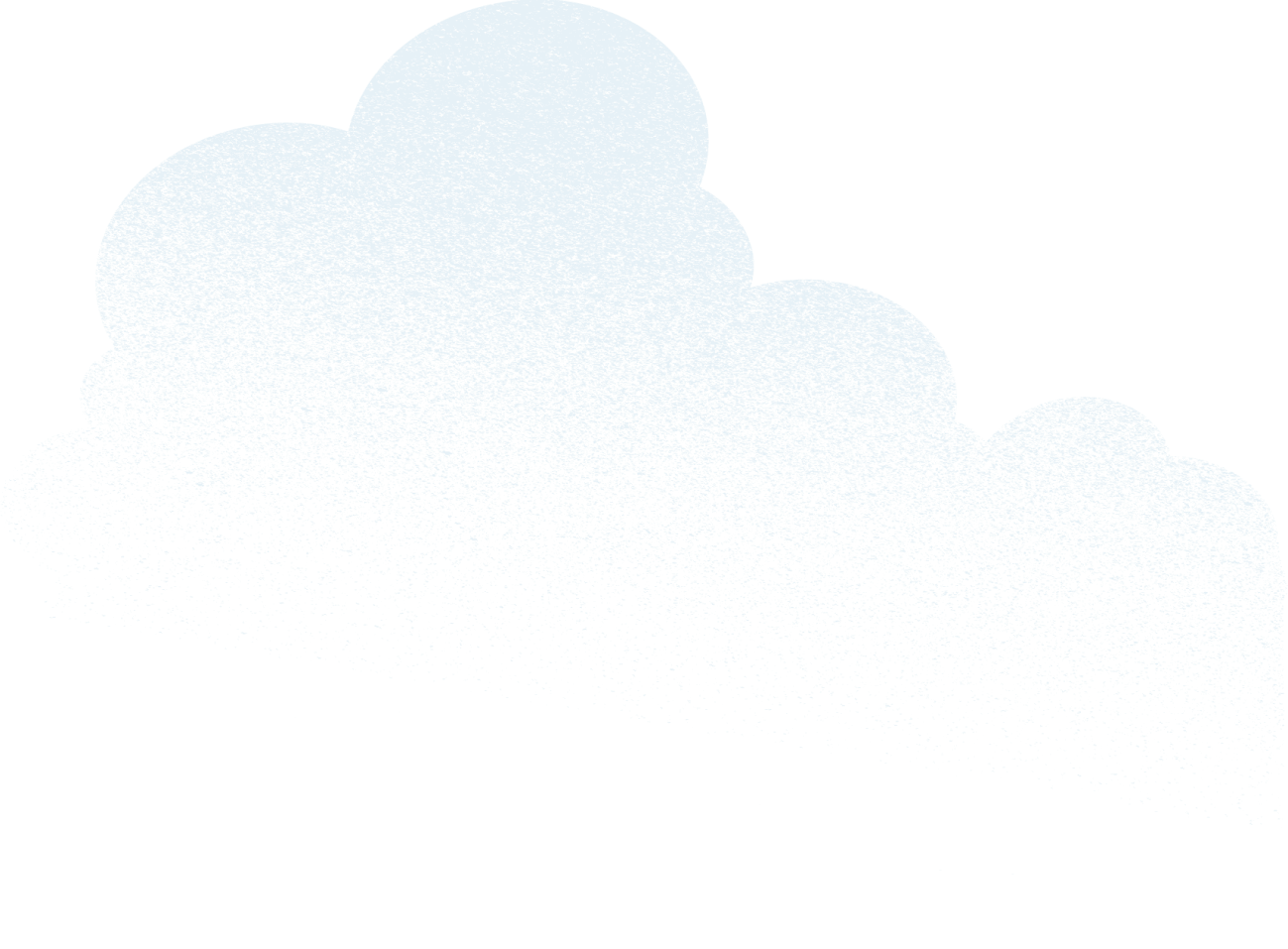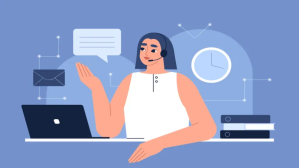元Apple米本社副社長が語る「AIの民主化」に必要なこと

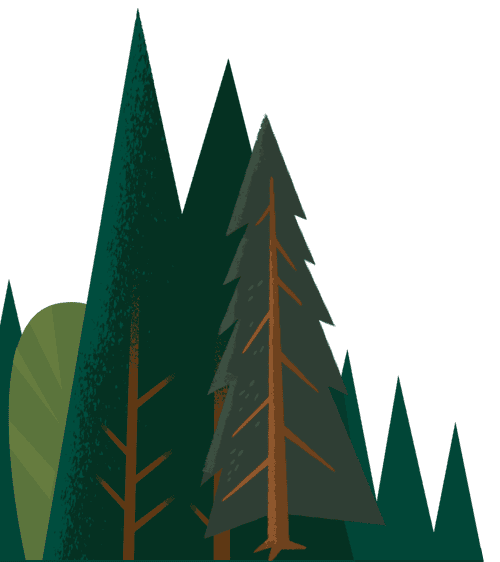
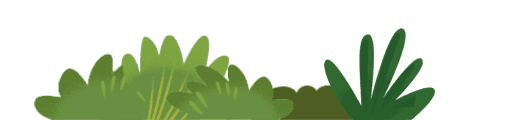
生成AIが盛り上がりを見せる中、この分野にビジネスチャンスを感じAIスタートアップが続々と登場している。AIスタートアップを紹介する連載シリーズ、今回はAI InsideのCMOで元Apple米国本社副社長兼日本法人社長の前刀禎明氏に登場いただきました。

Tsuyoshi Kimura
スティーブ・ジョブズ氏からAppleの日本再生を託されたことで知られる元Apple米国本社副社長兼日本法人社長、前刀禎明氏は2022年から日本を代表するAI SaaSのリーディングカンパニー AI insideのCMOとして活躍しています。
常にテクノロジーの最先端で、新たな体験とマーケットを数多く創造してきた前刀氏は、生成AIが「民主化」するために何が必要だと考えているのでしょうか。
AI専門メディア「AI NOW」の小澤健祐編集長をインタビュアーに迎えて、AIとともに歩むビジネスの未来に切り込みました。
目次
AI用語虎の巻: ビジネスのための生成AI用語集
増え続けるAI用語のキャッチアップにご活用ください。




普及のカギは「技術を人々が感じないで使えること」
小澤健祐氏(以下、小澤):前刀さんは、IT業界で大変長い期間ご活躍されていて、2021年にAI Insideにジョインされました。生成AIが広まった昨年2023年は、どんな変化があったとお感じですか。
前刀禎明氏(以下、前刀):数年前に予測系AIが出てきた時はあまり使い物にならなくて、AIブームも下火になり「AIってまだ使えないじゃない?」と思っていたところに、突然「ChatGPT」が出てきた。
テクノロジー全般に言えることですが、ベネフィットがユーザーにとってよくわらかないと一気に広まることはありません。でも、Chat GPTは何か訊いたら、間違いもするけど答えてくれるし、絵も描いてくれる。とてもわかりやすいAIの使い方が世に示されましたよね。
実はリテラシーの低い人ほどAIに対する期待値は高くて、そんな人々がこれからAIがどんどん進化すると期待を寄せた年。それが2023年だったと思います。

ソニー、ベイン・アンド・カンパニー、ウォルト・ディズニー、AOLを経て、ライブドアを創業。スティーブ・ジョブズ氏から日本市場を託され、アップル米国本社副社長 兼 日本法人代表取締役に就任。危機的であったアップルを復活させた。現在、株式会社リアルディア代表取締役CEO。セルフ・イノベーション事業、コンサルティングなどを手がけている。CQを高めるラーニング・プラットフォームを開発するディアワンダー株式会社も設立。2021年6月AI inside取締役、2022年2月AI inside CMO就任。
小澤:前刀さんはAppleやディズニーで、「マーケットを創る」という視点でさまざまなプロジェクトを推進してきました。
前刀:僕がAppleに入ったのは2004年で、スティーブ(Apple創業者のスティーブ・ジョブズ氏)から言われたのが、「日本のマーケットは壊滅的にダメだ。なんとかしてくれ」と。
2003年に日本初の「Apple Store」が銀座にできて、オープン当初は人が入っていたけれど、しばらく経つと全然入らない。当時のAppleにとって日本市場は危機的な状況で、これは大変だということで僕に声が掛かりました。
当時の日本の音楽業界はMDが全盛の時代で、音楽プレーヤー市場でMDが寡占状態という、世界のなかでも非常に特殊な市場でした。
そうした環境で、僕が携わる前のiPodは、「メモリが何GBで、ハードディスク内蔵で、パソコンと繋いで」など、ガジェット好きな人向けの技術が前面に出ていて、マーケットに価値がまったく伝わっていなかった。
そこで僕が取り組んだのが、技術ではなく「楽しさや価値」を徹底的に押していくこと。あとは、ライフスタイルに浸透しやすいカラフルな5色展開。
そんなiPod miniを全色持って発売前に色々な人に見せてまわってみると、「可愛い!」という反応があって。その後に「音楽が聴けて、(MDよりはるかに大量な)1000曲も入る。パソコンに繋ぐだけで曲名も自動的に入るし、とても簡単だよ」と価値や利便性の話をしました。
そうして驚きの連続を生み出しながら、カラーリングに応じたファッションコーディネートを提案するようなアプローチも打ち出した。
Appleは、常に「技術を人々が感じないで使えること」を大切にしている。その前にいたソニーやウォルト・ディズニーでも、僕はいつも技術そのものよりも、それが「どんな価値を生むのか」にとても興味があって、そうしたことをAppleでも取り組んでいました。
プロンプトを書いているようでは普及しない
小澤:AIに視点を移すと、私も自分の本のなかで「作るAIから、使うAIへ」と書いているのですが、生成AI以前のAIは、個別の課題や目的に合わせてモデルを作る必要があったし、どうしても技術先行だった。UXというか抽象的なところで滑らかさがない、そんな性質があったと思います。

「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。ディップが運営するAI専門メディア AINOW編集長を務める。書籍「生成AI導入の教科書」。1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。その他、AI領域で幅広く活動。ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進、生成AI教育事業を展開するCynthialyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、社長のAI化を進めるサービス「AI社長」を運営するTHA顧問、生成AIとエンターテイメントの融合を進めるAI Booster顧問、東大発AIスタートアップ Lightblue顧問。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇、講演、メディア出演も多数。
前刀:私が感じているのは「世の中にデータサイエンティストが必要という考えがあるようではAIは普及しない。データサイエンティストが不要になった時にAIが本格的に普及する」ということ。
もう少し噛み砕いて言うと、「プロンプトを書かなくてはいけないようでは生成AIは普及しない」ということ。実際、今年ヨーロッパで発表された「T Phone」の生成AIのように、「何とかして欲しい」とお願いすると勝手に実行してくれる、あのレベルまでいかないとAIが民主化したとは言えないと思いますね。
小澤:今も色々なところで「AIの民主化」と言われていますが、本当の民主化が実際どれだけされているのかですよね。
前刀:そう。なぜ民主化ができないかというと、やっぱり、考え方が技術中心だから。僕自身は、今の生成AIはまだ民主化レベルのUI、UXとは言えない、めちゃめちゃ機械的なものだと思っています。
小澤:ChatGPTはそのなかでも、サクサクと会話がリアルにできるところが、iPod miniのような新しい価値や体験の登場だったということになりますか。
前刀:シンプルに「自分にどう役立つのか?」ということを、人がいかに認識したのか、という点においては、その通りかもしれませんね。

2024年に日本で起きてくる劇的な変化
小澤:2023年の日本では、トライアル的に生成AIに取り組む企業が多く、AIマーケットに参入する企業も増えてきました。2024年は、色々なサービスのなかに生成AIが組み込まれて、新しいユーザー体験を生み出していく年になるのかと思っていますが、前刀さんはどうお考えでしょうか。
前刀:二極化していくのかな、と。
まず、AIにめちゃめちゃ頼る人がいる。逆に、AIなどわからないと遠ざける人がいる。前者のAIに頼る人は、AIがないと仕事ができなくなり、思考能力が低下し衰えていき、下手をすると、後者のAIを使わない人よりももっと劣化してしまう危険性がある。
そこで大事になってくるのが「AIで何をやるのか」を突き詰めること。AIがなかった従来とは全く違う仕事のやり方や価値が創造できるようになるので、そこを考えられる人が増えてくることで、2024年は劇的な変化が起きて、「人」そのものも大きく変わってくる。
小澤:人材の話ですと、優秀なマネージャーは、仕組み化したものをどんどん下に任せて新しいことを始めますよね。そうした「下ろしては上がる」という2方向のアプローチができる人は、おそらく生成AIのプロンプトを書くのも上手だし、生成AIをフル活用できる。
一方で、そうではない人は、今ある業務フローを全部AIに任せているだけで、上にも行けなければ下ろすこともできない状態になる。そうした二分化なのかなとも思います。
前刀:その通りだけれど、そもそも、「仕組み」だったり「スキル」として定義できるものは、すべてAIで置き換えることができてしまうよね。そうすると結局、次第に価値が落ちてくるサービスや企業がたくさん出てきてしまう。
やはり、今までの仕事のやり方を、ゼロから組み直すくらいのつもりでないと、おそらく時代の流れにはついていけないと思います。

小澤:スクラップアンドビルド的に、自社のそもそもの優位性はどこなのか考えていくということですね。
前刀:たとえば、アメリカのAmazon GOと日本の無人レジを比較してみると、Amazonのほうはレジがない。でも日本の場合はレジがあることが前提になっている。買い物をスムースにするという目的にフォーカスしたら、そもそもレジは要らないのでは?
そうやって、物事をゼロから考えること、本質的な目的に向き合うことが日本企業はすごく苦手だから、そこは変えたほうがいいですね。
「欲求」「好奇心」にフォーカスせよ
小澤:生成AIの活用においては、どうしたらその問題を乗り越えることができますか。
前刀:技術的にはどんどん進化していきます。ただ「技術的にできる」ということと「価値を生んでいる」ことは、全く異なることに気付くことが大切。
たとえばiPhoneやiPodが日本でヒットした時、日本の人たちは「あの中身はすべて日本製の部品」と言いながらも、自分で作ることはできなかった。
生成AIでも、いまGeminiやClaudeなど技術側ではさまざまな競争があるけれども、それもiPhoneの部品と同じです。それらを手段としてどう組み合わせ、自分たちがどんな価値を生み出したいのか、何を作りたいのか、 そうした「創造的な欲求」をきちんと考えていくことがとても重要です。
小澤:現状、日本企業の生成AI活用が10ー15%という市場調査のデータもありますね。

前刀:日本の企業はフォロワーのスタンスでいることが多いので、誰かが生成AIを賢く使ったという事例が出てきたら、その数字も上がっていくでしょう。
小澤:日本での生成AIの普及を阻んでいる要因として、セキュリティやハルシネーションなどリスクを気にして、企業が身構えてしまうところも大きいと思います。
前刀:AIに限らず、テクノロジーにはリスクがあるのは当たり前で、たとえば自動運転にリスクがあると言っても、人間のほうがよっぽど事故を起こしているし、自転車だってひどい事故を起こしている。
ハルシネーションにしても、人間はAIに正解を求めすぎていて。むしろ人間が想像もつかないことをAIが答えてくれたら、誰も思いつかないユニークなアイデアや予期せぬ提案として「そうきたか!」と受け止めて、自分の発想を広げていくような使い方をすべきでしょう。
そうした、個人の頭の柔らかさによって、差が大きく出てくる時代が来ています。昨年のAI inside Conference 2023で僕が話したのが、IQ, EQに続く”CQ”というスキルで、”C”はキュリオシティとクリエイティビティ。好奇心と創造性を高めていく感覚で、仕事や会社をもう一度考え直して再定義したほうがいいです。
小澤:私も「人間はAIに答えを求めすぎ」とよく話しています。ハルシネーションが問題視されること自体も不思議ですよね。企画書の作成など、そもそも答えがない問いに対して、良い企画とは何かを模索する際の「伴奏者」としてAIを活用すべきなのに、多くの人がAIを検索ツールとして捉え、すぐに答えを求めてしまう傾向はあると思います。
2024年に迎えるターニングポイント
小澤:これまでAI insideはAI SaaSのパイオニアとして、ビジネスとしてわかりやすくコスト削減ができるサービスを提供してきましたが、現在の生成AIトレンドを受けて、どのような方向に向かっていくのでしょうか。
前刀:我々としては、一番わかりやすいところとしてデータ入力やデータ活用、BPOや業務効率化のAI-OCR領域で、ある意味で覇者になった。そうした利益が出るところはビジネスとしてしっかりやっていく。
その先をどうやっていくのか、AI inside自身が今後どんな価値を提供していくのか、AI Platformerに進化するための大きなターニングポイントに来ています。
取材・執筆:池上雄太、前野あい、撮影:柳澤恒太、編集:木村剛士