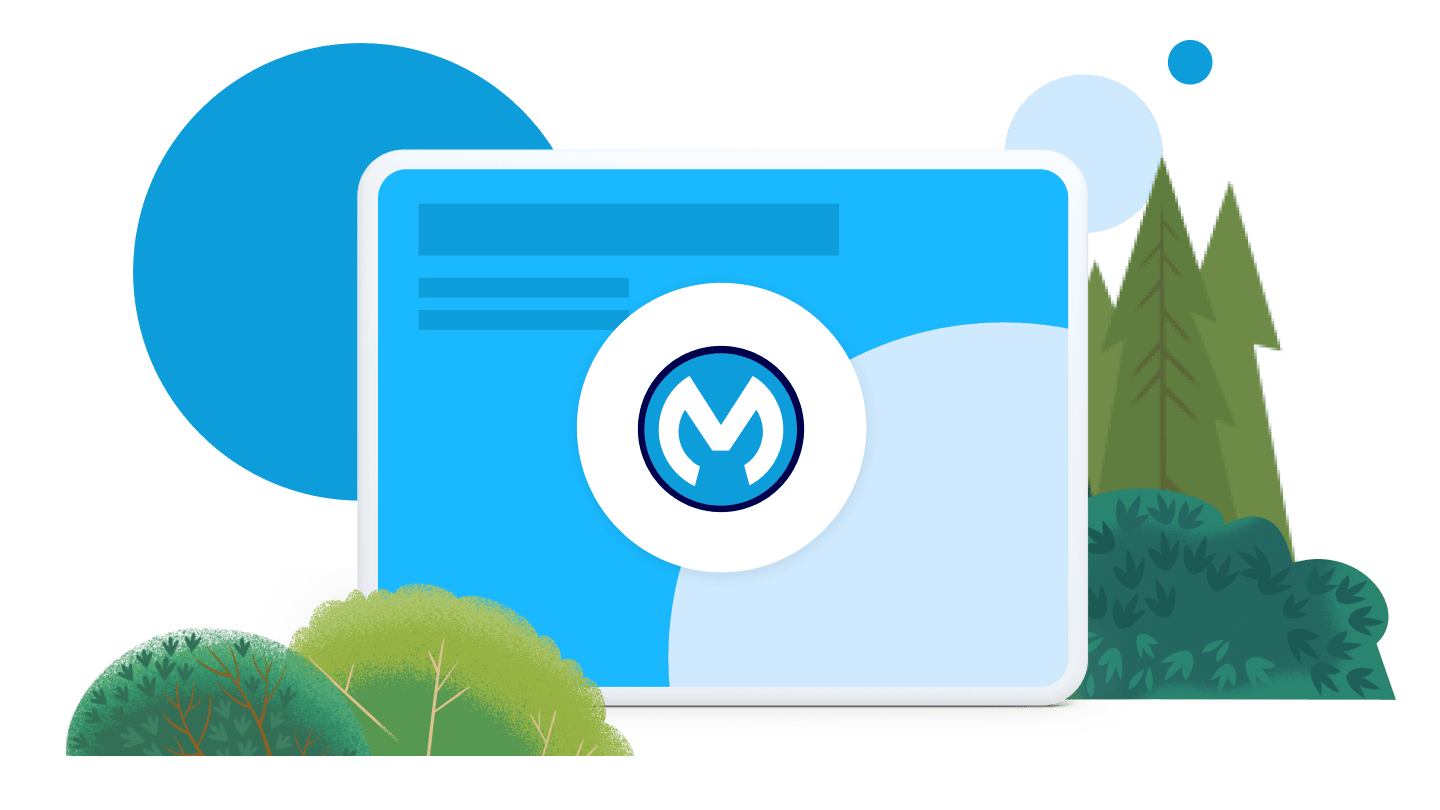Key Takeaways
目次
製造メーカー向けサービス体験DXガイド
本ガイドは、顧客とビジネスパートナーが製造メーカーと付き合う中で得る「体験」を変革する方法について、製造業界のリーダー向けにご紹介いたします。


経営計画のカギは「データ連携」と「デジタル活用」
──まず、DX技術戦略部の役割を教えてください。
青山:日立建機はグローバル展開する建設機械メーカーで、建設機械の製造・販売・レンタル・アフターサービスなどを手がけています。
「モノづくり」の会社ですが、近年は「CIF(Customer Interest First=顧客課題解決志向)」というスローガンを掲げ、お客さま視点で「コトづくり」にも取り組んでいます。
CIFを強く意識した中期経営計画「BUILDING THE FUTURE 2025 未来を創れ」では、「革新的ソリューションの提供で、真のソリューションプロバイダーとしての成長をめざす」と宣言。その実現手段として「データ連携」と「デジタル活用」の促進を明言しています。

そのために組織も改革。2020年に「IT推進本部」から「DX推進本部」へと改組しました。IT推進本部は、どちらかと言うといわゆる既存システムの刷新や効率化によるコスト削減や生産性向上といった「守りのIT」の戦略が中心。新たな価値を創出し非連続な成長を後押しする「攻めのIT」は限定的でした。それが組織名に「DX」を冠するようになり、より「攻めのIT」に力を入れています。
その中で私が所属する「DX技術戦略部」は、DXの推進に必要となる全社共通のテクノロジーやIT基盤の企画・設計、改発、運用を行い、CIFの実現をサポートすることがミッションです。

日立建機株式会社 DX推進本部DX技術統括DX技術戦略部部長
データの民主化を見据えた利活用基盤を本格運用
──今年度とくに力を入れているプロジェクトを教えてください。
CIF実現のためには、データの利活用とアプリケーション開発のアジリティ向上が必要不可欠です。これらに関して、この数年は大きく2つの成果がありました。
1つはデータ利活用の基盤、いわゆるデータレイクの本格運用です。これは社内の情報を収集・蓄積・公開する機能を持っており、基幹システムを含む業務システムのデータを統合しています。
また、お客様の現場で稼働している機器の稼働データや過去の保守履歴などを確認できる「Global e-Service」(*)というシステムがあるのですが、ここに蓄積した約20年分のデータも統合。つまり、業務システムと機器からのデータが同じ場所にある環境を構築したのです。
*「Global e-Service」は、日立建機の登録商標です
この基盤に蓄積したデータとAIなどの最新テクノロジーを活用して、お客様に寄り添った新たなサービスや製品の開発が加速するものと期待しています。
一方で、現在のデータ利活用の基盤には3つの課題が残っています。
1つ目はデータ量の増加に伴うコスト・処理時間の増加。2つ目は、システムから収集した生のデータを公開しているため、データの活用には収集元システムの知識が必要であること。3つ目がデータを取得・加工するためのSQLやETLなどの知識(例えばSQL、ETLなど)が必要であることです。
これらを解説するために、ユーザが使いやすいように加工したデータを用意し、AIなどを活用してシステムやITの知識がなくてもデータを活用できるような基盤を構想しています。
事例で読み解く製造業のDX
ミスミグループの営業組織改革を支えた3つの柱とは
製造業の企業文化とデジタルを掛け合わせて画期的な新事業「meviy」を立ち上げたミスミグループ本社。このeBookでは同社のDX成功の条件を再現性の高いデジタル活用を軸に探ります。


理想のアーキテクチャを「One Product」で実現するMuleSoft
──もう1つの成果についても教えてください。
データ利活用基盤と同じように、集約・共通利用の考え方をシステムの機能にも適用したいということで、データの利活用基盤と同様に、APIを開発、活用するための基盤の整備を進めたことです。
その背景には、主に2つの課題がありました。まず、システム構成です。縦割り構造のサイロ型システムが構築されており、システム間は密結合の状態。これでは開発に時間がかかってしまい、ビジネスのスピードを鈍らせてしまいます。
もう1つの課題が、APIを社外に公開する潮流がある中でのガバナンスです。各部門が勝手にAPIを作成・公開してしまうとセキュリティリスクが生じます。また、逆に社外のAPIを自由に使用することも危険です。
この課題を克服するために、API基盤の整備による「密結合」から「疎結合」への移行を決断。と、APIに関するガバナンスの両方を実現したい。そこで導入したのが、「MuleSoft」でした。
──なぜ、MuleSoftを選定いただいたのでしょうか。
MuleSoftのアーキテクチャ「API-led Connectivity(API主導の接続性)」が、私たちの「密結合から疎結合を目指し、業務ロジック層とプレゼンテーション層を分離したい」という考えと非常に近かったことが大きな理由です。
※API-led Connectivity:組織のエコシステム内で再利用可能かつ目的に応じたAPIを通じて、データをアプリケーションに接続する、SOA(Service Oriented Architecture=サービス指向アーキテクチャ)の進化系アプローチ。高速な開発でビジネスアジリティ向上に貢献する

もちろん他社製品も検討しましたが、どれも複数製品の組み合わせが必要。私たちは1つの製品で全体をカバーでき、マネージドサービスとして利用できることを重視していたので、MuleSoftが最適でした。
データ利活用基盤の推進を一緒に進めてきた日立製作所が、MuleSoftの実装実績を有しており、強力なサポートが得られることも重要な選定理由でした。

50種類のAPIでも1人で運用可能
──MuleSoftの導入にあたってどのように推進してきたか、プロジェクトを振り返っていただけますか。
最初にMuleSoftを適用したのは、機器の稼働状況を管理するGlobal e-Serviceのモダナイズでした。20年ほど運用していることもあり、内部が非常に複雑で密結合した状態でユーザーインターフェースも古い。そこでMuleSoftを使って作り直すことにしたのです。
しかし、綺麗に作ろうとすると環境を分けることになり、CPUコア数が増えます。MuleSoftの現在のライセンス体系では、コア数も加味されるためコストがかかってしまう。このトレードオフをしっかり考慮して設計する必要があることを実感しました。理想を追求するだけでなく、現実的なバランスを取ることの重要性を学びましたね。
──どのような効果を感じておられますか。
パブリッククラウドへの移行とMuleSoftを活用したマイクロサービス化によるGlobal e-Serviceの再構築で、運用コストを25%抑制する狙いがありましたが、現時点で定量的に計測できていません。
ただ、運用コストの削減効果は確実にあります。携帯・衛星通信の認可を取得し、通信が可能な世界149の国と地域(2025年2月時点)で稼働する48万台の建設機械からデータを「Global e-Service」で収集。
連携するバックエンドシステムは36システム。フロントエンドサービスは90アプリケーションを提供し、月間30万ユーザーが利用しています。
その中で現状、次期Global e-Serviceで使用しているのは6APIで、それらを含め本番環境で11APIが稼働していますが、このAPI基盤の運用を1人で担っており、50APIぐらいは1人で十分に運用可能だという感触を得ています。
もしMuleSoftを使わずにマイクロサービス化していたなら、とてもこの体制では運用できなかったでしょう。
開発面については、共通機能の部品化によってリードタイムを30%短縮できると見込んでいました。こちらもまだ十分な評価ができていませんが、今後ボリュームが増えてくれば効果が出てくると期待しています。
2025年 接続性ベンチマークレポート
世界のITリーダー1,050人の調査:AI時代に必要なデータ統合戦略
MuleSoftがVanson BourneおよびDeloitte Digitalと共同で実施した「接続性ベンチマークレポート」は、世界の1,050人のITリーダーへのインタビューに基づき、貴重なインサイトを提供します。
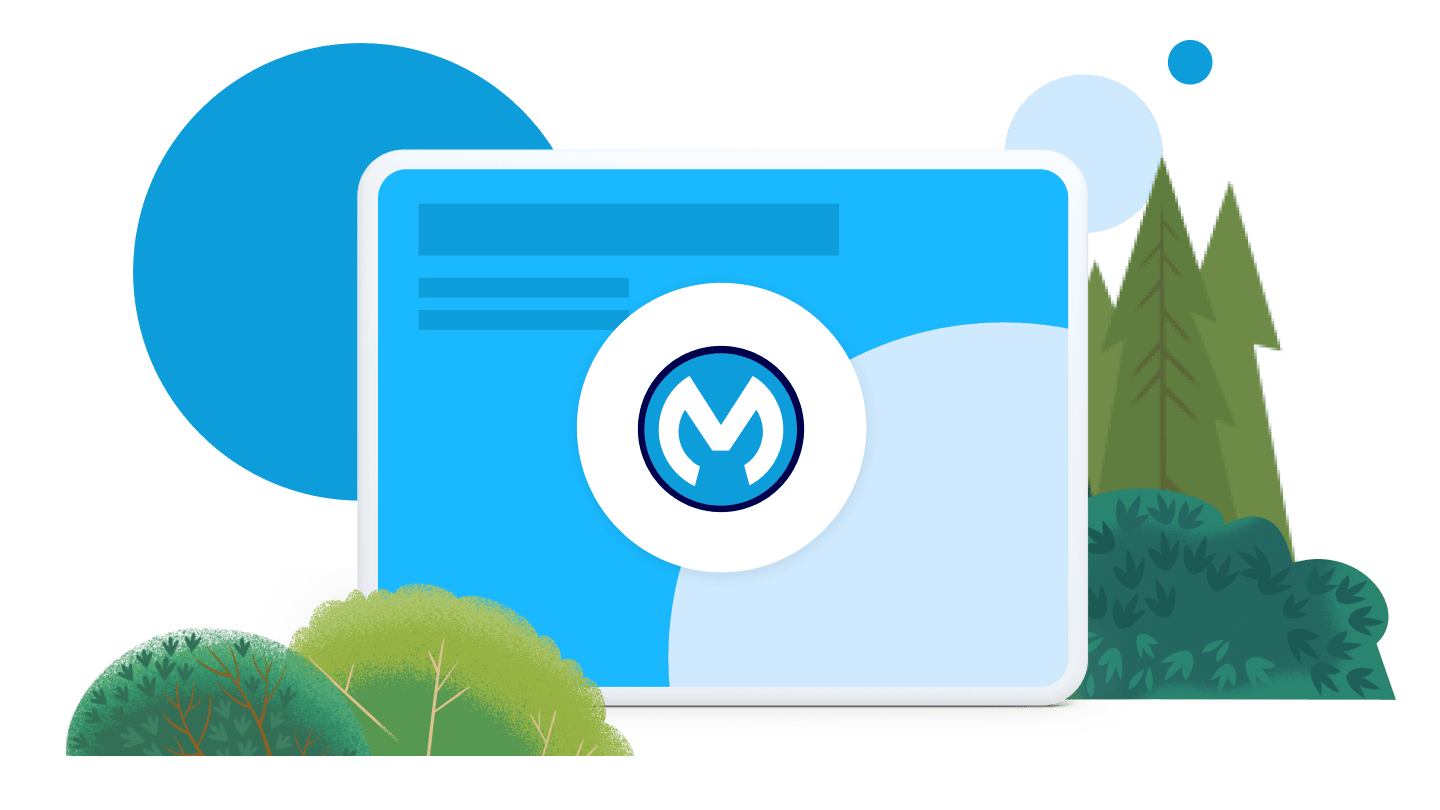
──ガバナンスに関してはどう評価していますか。
MuleSoftは、ガバナンスを効かせるために十分な仕組みを持っていることが確認できました。ただ、全社で使用する場合、適切に機能するように作り込むのに手間はかかりますので今も地道に取り組んでいる最中です。

AIとの協働を見据えたAPI整備を重要視
──今後の展望についてお聞かせください。
大きく2つのことを考えており、次期中期計画への反映を検討しています。
1つは、APIの社外提供に関するガバナンス確保。当社内でのルール整備を行い、MuleSoftやアプリケーションをサイバー攻撃から保護するWAF(Web Application Firewall)などの技術基盤とセットで展開していきます。
そして最も重要なのが、AI活用を前提としたAPI整備です。極端なイメージですが、いずれ個別のアプリケーションのユーザーインターフェースは不要になると考えています。すべてAIが処理してくれるので、AIとのインターフェースだけ持っていれば良い時代がきっと来るでしょう。
例えば、AIに「今、このマシンの状態はどう?」と聞けばすぐに確認でき、「過去にどういう修理履歴がある?」と問い合わせれば教えてくれる。そうなれば、現在のGlobal e-Serviceのような画面は不要になります。
さまざまなAIエージェントを、APIを介して適材適所でシステムに組み込み、自然な会話でデータを活用する。まさにMuleSoftが提唱している世界観を目指していきたいと考えています。

執筆:加藤学宏
撮影:北山宏一
取材・編集:木村剛士
MuleSoft for Agentforce
スマートなAIエージェントを迅速に構築
企業が直面する統合の壁を乗り越えるための実践的なインサイトを提供し、AIの取り組みを支える強固で柔軟なインテグレーション戦略の必要性と、生産性向上への道筋を明確にします。