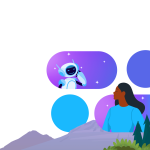2018年に創業し2023年に東証グロース市場へと上場したAVILEN(アヴィレン)。AI関連開発とAI/DX人材育成の両輪のビジネスモデルを軸に躍進。雨後の筍のように生まれるAIスタートアップの中で、その存在が際立っています。
躍進の秘訣は「完全自動化できる」と言い切るAIエージェントと、優秀なAI技術者が集まる400人弱の開発コミュニティ。創業者で代表取締役の高橋光太郎氏に話を聞きしました。
企業向けAIエージェントの最新事情
AIエージェントの最新トレンドを解説。企業がAIを効果的に導入し、顧客との信頼関係を築くための具体的な方法を紹介します。
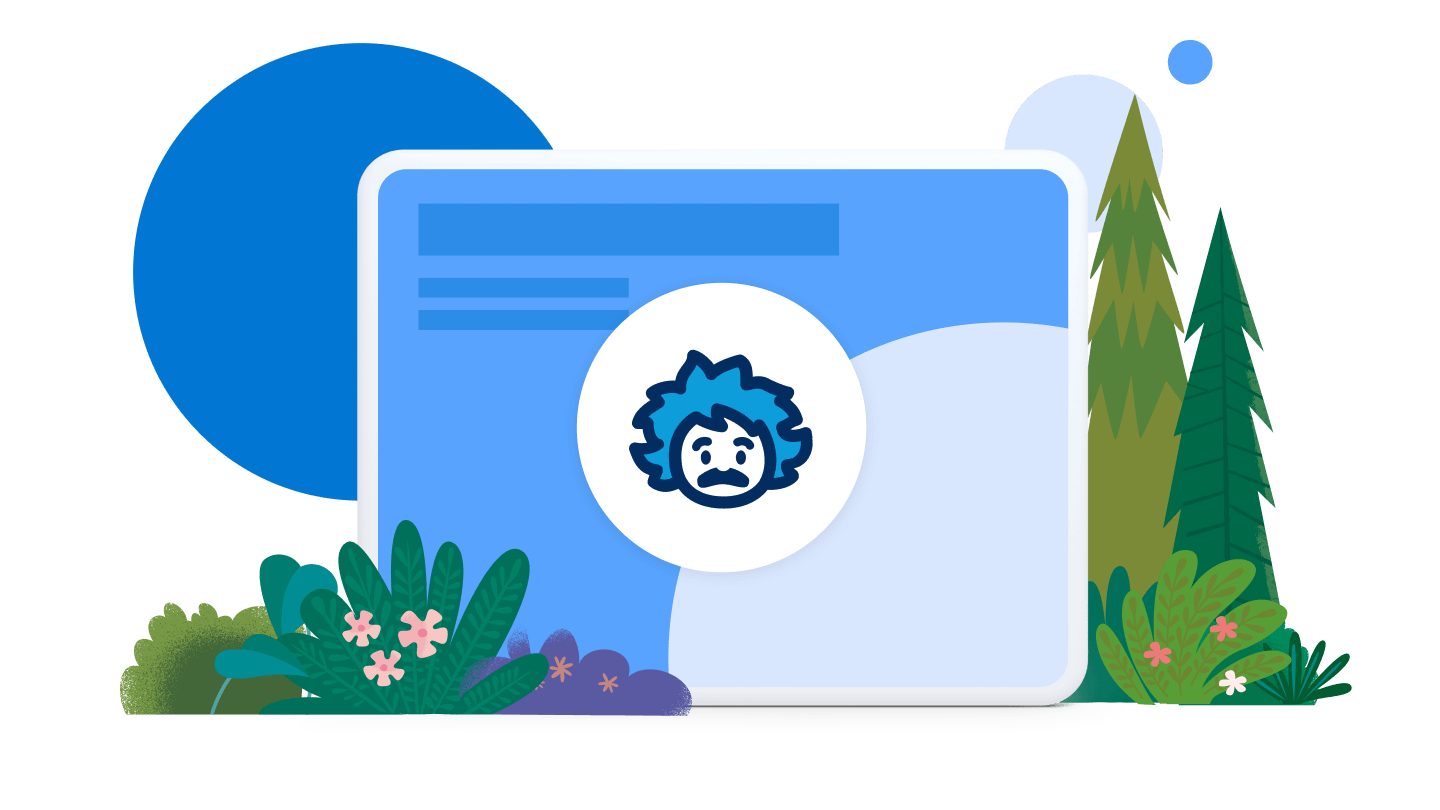
学生起業家を支えたのは「タイミングとパートナー」
──東京大学大学院に在籍していた時に起業しています。きっかけを教えてください。
私が高校生の時、父が独立・起業しまして、とても楽しそうに仕事をしている様子を見ていたからか、私もいつかは起業したいと漠然とした思いを持つようになりました。とはいえ、具体的な計画はないまま、大学院に進学しました。
背中を押したのは、やはりAI。大学院の在籍中にAIに出会い、深く研究していけばいくほどその可能性の虜になって。世の中を劇的に変えると感じ、「今しかない」と半ば衝動的に4人の仲間と起業しました。

株式会社 AVILEN 代表取締役/データサイエンティスト
創業メンバーとしてAVILENに参画し2021年から代表取締役を務める。 2023年にAVILENを東証グロースに上場。 東京大学大学院を修了し、機械学習による即時的な津波高予測の研究に従事。 金融データ活用推進協会標準化委員。
──会社設立後、5年でIPO(新規株式公開)。AIというトレンドを掴んで早期に軌道に乗せた印象を受けます。
そんなに甘くはなくて(苦笑)。学生が創業した会社と取り引きしていただける企業はそう多くはありません。なので、スケールしやすいBtoBビジネスを最初からやりたかったですが、まずはBtoCに絞ってAI関連の資格取得に向けた事業を始めました。
その当時は、AIに対する関心が高まり始めた時期。学生も社会人もAIを学びたいと思っている人は増えていたにもかかわらず、良質な人材育成事業を手がける企業は存在していませんでした。
創業メンバー5人のうち4人はAIの研究者で、手前味噌ですが、全員が最高のメンバーで、特に教え方や教材のクオリティが評判となり、多くのお客様に支持されてきました。その実績が法人の方々にも注目され、徐々にエンタープライズ領域でのお客様が増えていきました。今では、日本ディープラーニング協会(一般社団法人)が実施する資格制度「E資格」の取得者数は、9期連続日本一。個人だけでなく法人向けにも展開し、累計800社ほどのお客様にご利用いただいています。この人材育成事業が早期に立ち上がったのは、幸運でした。
それと、パートナーの存在も大きな要素でした。それはジャフコグループです。2020年12月に、ジャフコグループに既存株式の過半数以上を譲渡し、戦略的なパートナーシップを結んだんです。
──過半以上とは、お互いに大胆な決断ですよね。
ですよね(笑)。PL(損益計算書)が何かもわからなかった学生が、技術だけでスピード感をもってAI変革を進めていけるほど甘くないと思っていました。
AIの発展は早く、インターネットの登場と同じくらい、いやそれ以上の劇的な変化をもたらす。スピードが勝負だと思っていました。最先端の技術を追いながら、経営やIPOなどについてを学んでいては遅れをとってしまう。ですので、「時間を買う」意味でジャフコグループとの二人三脚での経営を決めたんです。
ジャフコグループの目的は、当然IPO。「最短最速での上場」を合言葉に握手し、「2年8か月で上場しよう」という目標を立てました。ジャフコグループは、技術以外の会社として未熟な部分を鍛えて上げてくれました。結果、1日も遅れることなくIPOを実現できました。きっと、私たち単独で経営するよりも2年ほどの時間を買えた(短縮できた)と思います。

完全自動化が可能なAIエージェントが差異化に
──事業区分をみると、「ビルドアップ」と「AIソフトウェア」というカテゴリで分けています。ビルドアップは祖業の人材育成事業ですが、最新の決算(2024年12月期)をみるとAIソフトウェアが前期比67.1%増と驚異的に伸びており、ビルドアップの売上高を超えています。
AIソフトウェア事業は、文字通り法人向けのAIを活用したビジネスアプリケーションソフトの開発・販売です。ニーズの強い汎用的なソリューションはSaaSパッケージにして提供するほか、お客様の要望に応じたカスタマイズ開発も行っています。
──AIソフトウェア事業を手がけるスタートアップは急増し、大手も当然力を入れています。すでに「レッドオーシャン化」していますが、AVILENが選ばれる理由は何でしょうか。
AIソフトウェア事業は創業時からやってはいたんです。ただ、技術だけが強いメンバーが集まっていたから先進技術に飛びついてPoCばかり繰り返していて、顧客も満足して売り上げも立つが、未来に常に使われ続けるAIシステムは作ることができていませんでした(苦笑)。
これではまずいと思い、とにかくお客様の声を聞き、その課題解決に集中することに努めました。さらに松倉(怜・取締役CEO)や太田(拓・執行役員CRO)といった外資系戦略コンサルファームで上流を経験してきている優れた人材を経営陣に迎え、お客様の課題を解決するためのプロダクト作りにシフトし、本質的なニーズの解決ができるようになり、使われ続けるAIシステムの提供ができるようになりました。
その大前提を構築したうえで、当社の差別化は主に3つです。1つはお客様のある特定の業務プロセスを完全自動化できるAIエージェントの技術。2つ目はそれを支える開発力。3つ目は内製化まで支援することができる一気通貫力です。
まず技術、AIエージェントから説明します。多くのAIは、単一タスクの自動化は図れるものの、複数のタスクが連鎖して構成する業務プロセス全体を完全に自動化するものはほぼありません。どこかの工程で人が介在しなければならないケースが多い。
採用業務を例にすると、「採用AI」を謳う多くのAIは、魅力的なリクルートメッセージの作成はAIが担うかもしれませんが、そのメッセージをチェックし、適切な送り先を選定し、送信し、結果を分析するのは人ですよね。AIで自動化を図れているのはごく一部です。
AVILENは違います。当社のAIエージェントを使えば、AIが会社の戦略に適した欲しい人材を自動で選び、メッセージを書いて送信。その結果を週次レポートとして出してくれます。
人が行うのは、月に1回程度「返信率が悪いから文面を変えよう」といった指示を出すくらい。ダイレクトリクルーティングに人が一切関わりません。私たちはこのような全自動化により、採用担当者2人を減らしてマネージャー1人だけの配置を実現できています。
──それができる理由は何ですか。
技術的優位性はもちろんありますが、大事なのは設計思想と上流からの支援。AVILENのAIエージェントは、特定の業務プロセスに特化しています。それもかなり範囲が狭い。具体的には、メーカー向けの帳票処理自動化や食品工場における異物混入防止の自動化など。一見すると、範囲が狭いので、効果が薄いように感じる人もいるかもしれませんが、担うプロセスは完全に自動化でき、そこに人を配置する必要はないので絶大な効果を出せます。
ある特定の業務に特化しなければ、完全自動化は実現できません。「どんな業界のどんな業務でも自動化できるAIエージェント」などありえない。その業界特有の商慣習を熟知し、細分化した業務に特化するからこそ自動化はできる。AVILENは「業界×特定業務」の組み合わせでAIエージェントを開発しているので、真の自動化を図ることができているんです。
また、顧客の解像度を徹底的に上げ真の顧客価値を共に考え、AIが前提となる世の中にない新たなプロセスを生み出すという上流からの支援を技術的優位性と設計思想と組み合わせ課題を解決する。お客様はこの戦略と完全自動化の技術力を評価してくれています。

AIエージェントとは。
この記事では、AIエージェントとは何か、なぜ注目を集めることになったのかについてわかりやすく解説しています。

東大、京大などの学生AI技術者を400人規模で組織
そして、それを支える「開発力」が2つ目の強みです。
AVILENの社員は現在60人ほどですが、それ以外に「AVILEN DS-Hub」という機械学習の研究者コミュニティを組織しています。DS-Hubには東京大学や京都大学などに在籍しAIを研究する学生が400人弱在籍。AVILENの開発プロジェクトに関わっていて、AVILENの高い技術力の一端を担っています。
メンバーはテストをパスした人だけで合格率は5-6%。優秀な開発者が集まっていることがAVILENのもう一つの強みです。
──なぜ、そんな優秀な人材を集めることができるのでしょうか。
最も重要だったのはタイミングと継続だと思います。祖業の教育事業は始めた2018年では、まだ対面講義が主流だったことから多くの講師が必要でした。創業メンバーで賄える規模ではなくなってきた時に、講師を探すにあたって学生に着目したんです。その当時、私の出身大学である東京大学や、京都大学、東京工業大学などに在籍するエッジの効いた学生は、高度なレベルでAIを学んでいたので、こうした学生を仲間にして。好きなAIで、お金を稼ぐことができるのは学生にとっても魅力で、口コミで優秀な人材が集まるようになったんです。
こうした学生が貴重な戦力になるだけでなく、一部の学生は正社員としてAVILENに入社してくれていますので、新卒の人材採用には苦労しないという利点も生んでいます。
今、同じようなことをしてもきっとここまで大規模なコミュニティにはならなかったはずなので、タイミングがとても良かったですね。

堅実な成長を見通すもM&Aで「時間を買う」
──今後の見通しを教えてください。どの程度の規模を追いますか。
2025年は、AIソフトウェア事業、特にAIエージェント部門は年率30%程度で成長させていきたいと考えています。
──昨年度の成長率を考えれば、少し控えめな印象を持ちます。
急激な成長だけにとらわれると、どこかでひずみが生まれ、クオリティが落ちてしまいます。当社のAIソフトウェアのリピート率は85%を誇っており、とても貴重な指標です。お客様の満足度は下げたくない。また、人材採用も重視しており、中途採用の条件が厳しすぎるなど言われることもあるのですが、拙速に人を採用したら将来必ず苦労すると思います。投資家の方たちの信頼を得るためにも、手堅い30%の成長の見通しを今年度は進めていければと思います。
──将来的には、クラウドのパッケージの売り上げ比率が高まっていくのでしょうか。
5年くらいのスパンで見れば、その可能性は高いですね。当然、コンサルティングでしか解決できない案件もたくさんありますが。
ただ、上流部分も伸ばしていく必要があり、上流の戦略コンサルティングは絶対に手放さないですね。やはり、業務プロセスをいかに深く知っているかが重要で、縦売りだけしていると時代に追いつけなくなります。上流部分を外してしまうと、パッケージ化した製品が絶対に使えると思っても、実際にはお客さんが求めていないものになってしまう恐れがあります。
上流で仕事をしながらヒントを得ることが重要です。また、プロセスの自動化はツールの話が3〜4割で、残りの6〜7割はカルチャーやプロセスの変革をどう起こすかという話だったりします。そういう意味でも、コンサルティング部分の売上は大きく残ると思います。

──昨年度はM&Aにも着手しました。
2024年に初めて、LangCoreの株式を100%取得し、AVILENにグループイン頂きました。LangCoreは、傑出した⽣成AIアビリティを 武器に伴⾛型開発と⽣成AI コンサルティングを提供しており、その強みを活かしながら、当社の業績に貢献しています。
今、AIベンチャーがたくさん生まれています。自前で開発するよりも、良いものがあれば取り入れる方針です。M&Aも「時間を買う」戦略の一つ。特定の領域に特化したAIエージェントは、ゼロから作るのが大変です。そうしたものをM&Aで吸収し、私たちのコンサルティングやカスタム開発のケイパビリティと融合させる。
今後も、当社独自の強みを活かしながら、さまざまな手段と可能性を模索しながら、堅実に事業を伸ばし、AVILENのパーパスである「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」ことを実現していきます。
企業向けAIエージェントの最新事情
AIエージェントの最新トレンドを解説。企業がAIを効果的に導入し、顧客との信頼関係を築くための具体的な方法を紹介します。
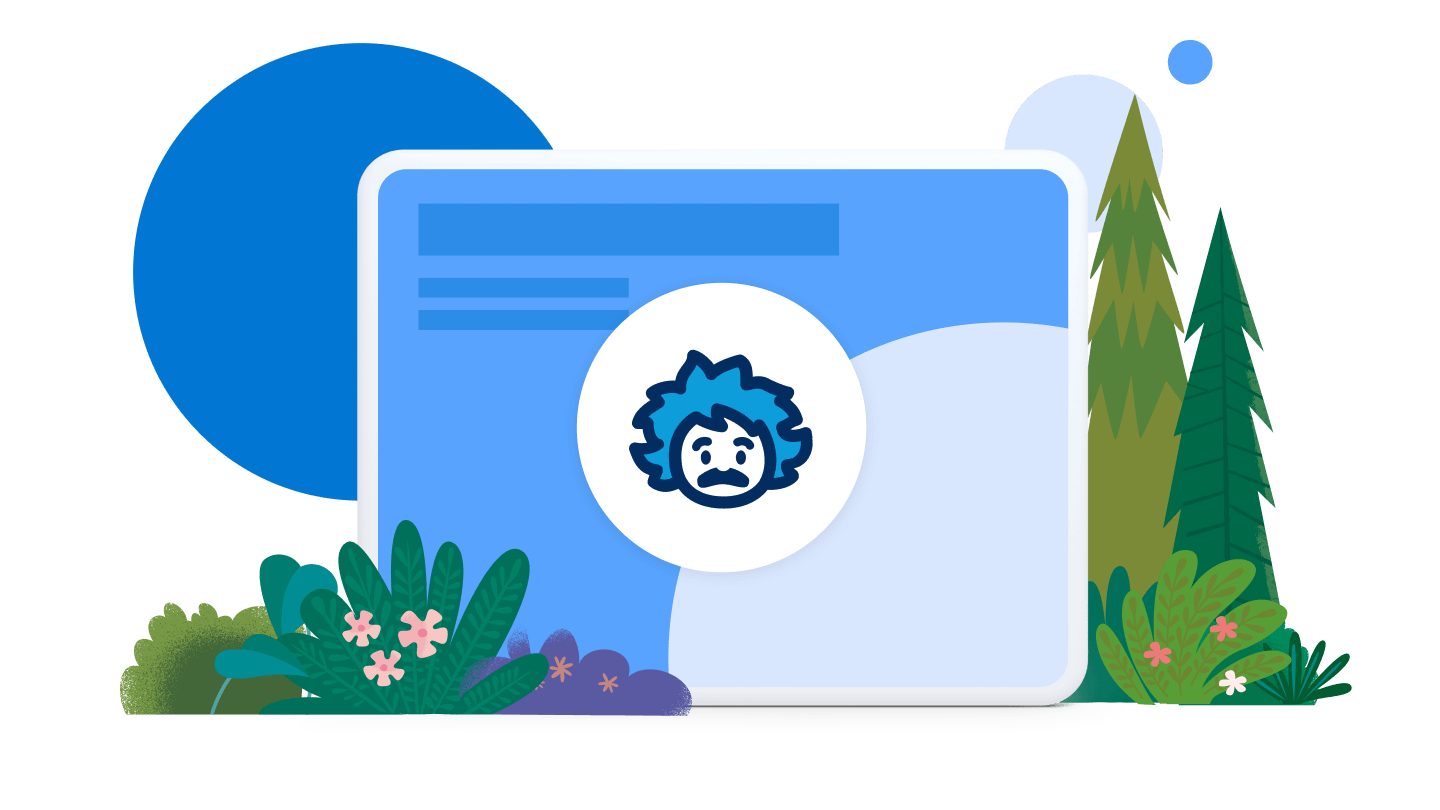
企画:池上雄太
撮影: 遥南 碧
取材・執筆:木村剛士