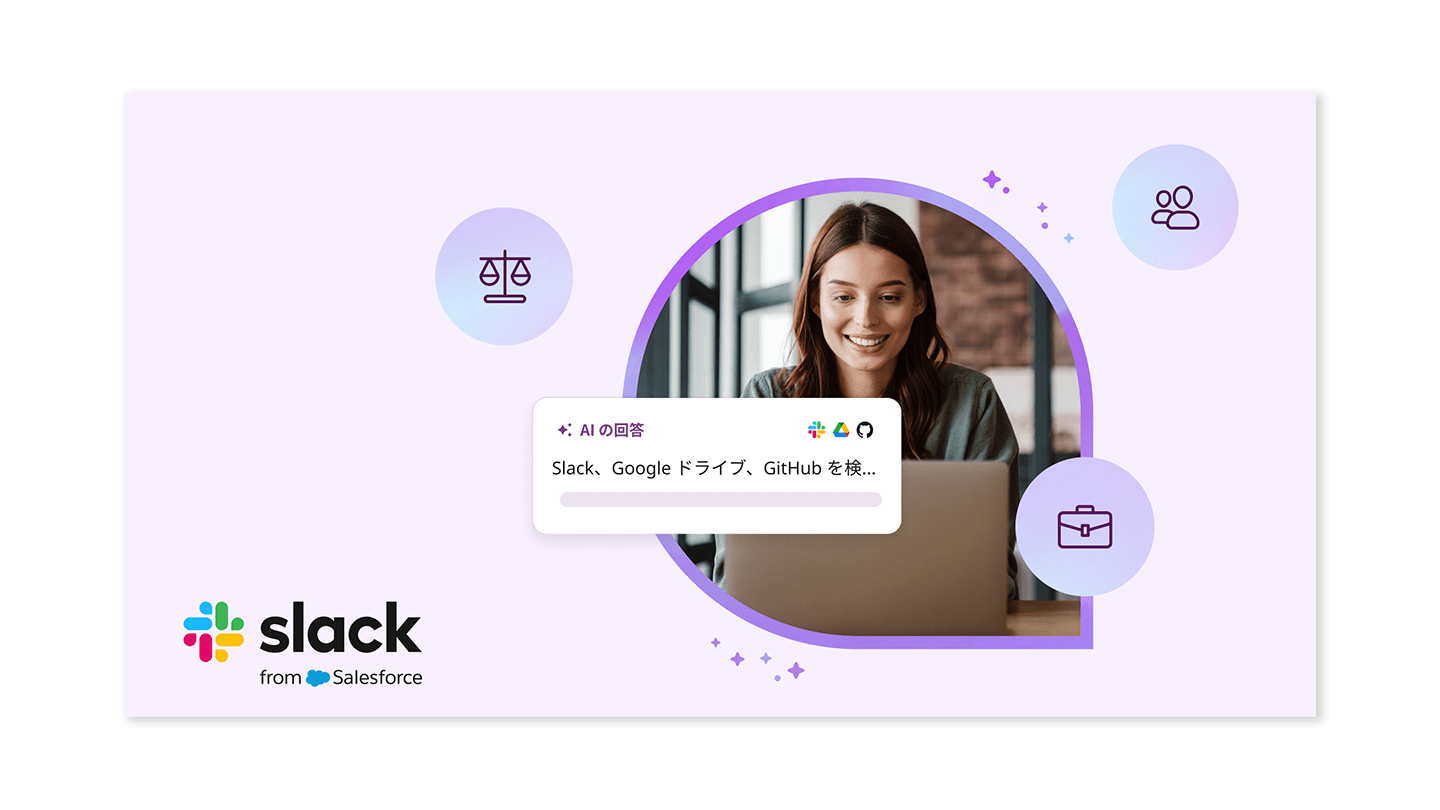Key Takeaways
目次
Slackとは? Slack完全入門ガイド
Slack は世界中で企業の日々の仕事をよりシンプルに、快適に、有意義にしています。この電子ブックでは、営業、マーケティング、IT、サービス、経理といった、企業の組織における成長や効率的な連携に Slack がどのように役立っているかについて、詳しく紹介しています。


世界150か国以上で利用され、導入数が増え続けている「Slack(スラック)」。2017年に日本語版をリリースして以降、日本国内でもスタートアップから大企業まで数多くの企業に支持いただいています。
2024年2月からはAIを搭載。着実に進化を遂げている中、2025年10月開催のイベント「Dreamforce」では、5つのイノベーションを発表。「すべての業務の入り口はSlackになる」という「Slack is Agentic OS」という構想がさらに現実になりました。
本記事では、SlackのPMM/マーケティングをリードする鈴木晶太にインタビュー。最新のSlack事情、AI機能、そしてSlack is Agentic OSとは何か。最前線をあますことなく語ります。
Q.1 Slackってどんなツール?
Slackの源流は、ゲーム開発会社の Tiny Speckにあります。異なる場所と時間帯で働くメンバー同士で1つのゲーム開発を進める中、時差や言語の壁、会話内容が残らないといった課題を抱えていました。
電話やメールでは、やり取りしている相手としかやり取りができず、メンバー全体に均質な情報がいきわたらない。コミュニケーションのミスが開発の遅れを招き、品質向上の障壁になっていたんです。そこで社内のコミュニケーションツールとして生まれたのが、Slackです。
おかげさまで順調にユーザー数を増やし、世界で親しまれてきたSlackは「コミュニケーションツール」として広く認知されてきました。しかし、Slackはコミュニケーションを円滑にするためだけのツールではありません。
「Slackとは何か」を伝える際、私たちは「Slack is Agentic OS(エージェンティックOS)」と説明しています。これは、Slackを創業した時から描いていた理想を具現化させた姿です。

株式会社セールスフォース・ジャパン
製品統括本部 プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマーケティングマネージャー
では、Agentic OSとは何か。
スマートフォンには、多くのアプリケーションが搭載できます。そのベースにあるのがiOSやAndroidといったOSですよね。OSがあって初めて、SNSやゲーム、ビジネスツールなどの多様なアプリケーションを動かすことができます。
同じように、Slackはビジネスパーソンが使うあらゆるアプリケーションを下支えするOS(ビジネスの基本システム)と位置付けています。すべての業務の入り口としてSlackを位置付け、Slackからすべての仕事を始める、すべてのアプリをSlackから呼び出して利用する。そんな世界を描いています。
ですので、広く認知されているコミュニケーション機能は、SlackというOSの上で機能するアプリの1つに過ぎません。
SlackというOSの上で、コミュニケーション機能としてのSlackが動き、それ以外の標準機能であるドキュメント作成やオンラインミーティング、ワークフローなどの機能も動く。加えてAPI連携によって他社ツールも動く。Slackで動作するアプリは2600種類を超え、今もなお増え続けている。
完全体とは言えませんが、すでに仕事の入り口、Agentic OSとしての立ち位置を確立しつつあるんです。

Q.2 他社ツールと比較した優位性は?
今、説明したコンセプトと拡張性が大きな優位性ですが、Slackはご活用いただく企業・団体の規模に関係なくオープンに会話ができ、カジュアルに使える点も強みです。
他のツールは、組織全体での横断的な活用には向いていないものもあります。Slackは、所属しているグループだけでなく、知らないチャンネルで起きている会話や情報の検索も簡単にでき、オープンな会話や組織間連携が進めやすくなっています。企業規模が大きい企業で最近導入実績が多いのは、その証左です。
また、絵文字文化をはじめとしたカジュアルさも、Slackの特徴です。背景にあるのは、創業当初から重視する「遊び心」。ビジネスライクになりがちな組織のコミュニケーションに、フラットでカジュアルにやり取りできる雰囲気をつくり出しています。

Q.3 導入した企業の事例は?
Slackは世界で20万以上の企業・団体に有料プランを利用いただいており、1つを選ぶのは困難ですが、Slackの導入事例として頻繁に紹介するのが、ガレージ・倉庫事業などを展開するKAKUICHI(カクイチ)です。伝統があり、業務プロセスも使うツールも長年固定化されていた中で、Slackが企業変革を支えた代表的な事例です。
KAKUICHIは、創業130年以上の老舗企業で、鉄骨ガレージやホースなどの農業用資材をつくってきました。同社は、もともとテクノロジーに明るくない社員が多かったといいます。しかし、より機動的な組織への変革を目指し、従来の電話・FAX中心の情報伝達・共有手段から脱却して、Slackを導入・浸透させました。
導入当初、ITに不慣れな社員からは「なぜ絵文字を使わなければならないのか」「仕事にカジュアルな会話は必要ないんじゃないか」といった抵抗の声がありました。しかし、田中社長の強いリーダーシップのもと、社長自らが積極的にチャンネルで投稿し、各部署からのリアクションを促す仕組みを構築しました。
その結果、「1対1」の閉じたコミュニケーションが「1対多」のオープンな情報共有に変化し、意思決定スピードが4倍に向上したといいます。100拠点に分散していた営業メンバーは、顧客の問題解決に必要な知恵を瞬時に共有できるようにもなりました。
Slackの週間アクティブユーザー率は94%に達し、全員が等しく情報を持つようになったことで中間管理職の必要性が減るほど、組織構造も変革しました。現在は、この成功体験を社外に生かすことにチャレンジしており、農業改善事業で農家同士の情報交換コミュニティづくりをSlackで手がけています。
創業 130 年超・老舗企業カクイチの意思決定スピードが Slack 導入で 4 倍に
「一番現場に近い人が情報を持つことが組織のスピードを速くする。カクイチでは Slack を導入し、意思決定の速さが 4 倍になりました」
Kakuichi
代表取締役社長兼 CEO 田中離有氏



Q.4 SlackのAIって何ができるの?
2024年2月にSlackのAI機能の総称といえる「AI in Slack」をリリースしました。最初に実装した機能が、「検索」「要約」「議事録」です。
- 検索
まず「検索」です。「〇〇についての説明資料を出して」など、自然言語で指示するだけで、過去の会話履歴や保存したファイルなどを参照し、必要な情報を容易に探すことができます。
AI検索のインパクトを理解するために、Slackのワークスペースは「会社」、各チャンネルはその「会議室」だと考えてみると、わかりやすいかもしれません。
常に複数の会議が同時並行で開かれており、多くの会話が飛び交っています。1つや2つの会議だけなら、会話や資料の内容把握はそう難しくないでしょう。しかし、組織がスケールして、会議の数が10、20と増えれば内容は把握しきれません。
検索機能は、いわばすべての会議から、欲しい内容だけをピンポイントに抽出できる。自然言語で指示するだけで、それまでまったく知らなかったチャンネルも参照し、目的に合った情報を瞬時に回答してくれます。
多くのビジネスパーソンが抱える「情報が見つからない」を解決できるようになり、ある導入企業では、会話の内容を理解するのに要していた時間が50%ほど減少したという例もあります。
- 要約
Slackを使っていると、大量の会話に追いつけなくなることがあります。AI要約機能を使うと、指定したチャンネルの会話を瞬時に要約してくれます。
たとえば、毎朝必ずチェックするチャンネルがあれば、登録しておくことで、そのチャンネルで起きていた会話の「まとめ」をつくってくれます。ニュースで言えば、「今日の記事のおさらい」に目を通すようなものです。要約だけで情報がキャッチアップできるため、すべての会話を読む必要がなくなり、大幅な時間短縮ができます。
- 議事録
Slackのビデオチャット「ハドルミーティング」の議事録を自動作成する機能です。従来は、ハドルミーティングの内容を残すことができませんでしたが、AIの実装でワンクリック、ワンタップで日時、参加者、内容、ネクストアクションまで瞬時にまとめてくれます。
ここまで、最初にリリースした3つの機能を紹介してきました。これだけでも十分利便性は高まりますが、さらに便利な機能を続々と追加しています。いくつか紹介しましょう。
- 翻訳
チャンネル内に扱う言語が異なる人が複数人いても、翻訳ボタンを押すだけで指定した言語に翻訳してくれます。ほとんどの主要言語を網羅しており、Salesforce社内でも頻繁に利用されています。
相手の言語が話せない者同士にもかかわらず、異なる言語を翻訳し合いながら、スムーズに会話が成り立っている。Slack上では、言語の壁がほぼなくなると言っても過言ではありません。
- ワークフロービルダー
AIに自然言語で指示するだけで、指定したワークフローを自動で作成します。つくったワークフローをチャンネルで設定しておけば、ボタンを押すだけでそのワークフローが立ち上がり、必要な人にメンションやアクションを依頼してくれます。
たとえば、ミーティングを設定する際、DMやメールで日時や議題を決めてカレンダーに入れて招待を送り、会議室を予約して……と、いつも決まった行動をします。そうした定型的な業務をワークフローのテンプレ―トに入れてチャンネルに組み込んでおけば、必要なときにボタンを押すだけで、一連の情報を整理して入手できます。
- AI文章作成
ドキュメントツール「canvas」もAIで進化しています。canvasは、Slack上でテキストや画像などのコンテンツを作成・共有できる機能です。AI実装で、自然言語で指示するだけで、内容に見合ったcanvasを自動的に作成可能になりました。Slack内の会話を参考にし、情報を見やすくレイアウトすることも可能です。
たとえば、私が上司との1on1に向けた準備をするとします。従来なら、「今月は何をしたっけ……」と思い返さなければいけませんでした。
AIを使えば、「過去1週間の自分の業務と成果をまとめて」と指示するだけで、過去の投稿を遡り、会話やドキュメント、動画や画像の文字も参照して、一気に指示した情報を整理してくれます。でき上がったら、canvasを上司に見せれば一連の作業が瞬時に済みます。
AI 時代に Slack は「エージェンティック OS」として働き方を変革
Slack は、人、データ、アプリ、エージェント、AI、ワークフローが集結する場所。AI 時代のスピードと生産性のために必要なコンテキストが得られる唯一のプラットフォームです。


Q.5 SlackでAIエージェントは使える?
Salesforceの「Agentforce(エージェントフォース)」で作成したAIエージェントを組み込むことができます。
使い方は、人間に仕事を依頼するのと同じ。Agentforceで作成したAIエージェントにメンションを飛ばして、「〇〇エージェント、この作業をして」とメッセージを送るだけで、指示に従って自律的にアクションを起こしてくれます。
これだけではありません。いま世の中にさまざまなAIエージェントが登場していますが、それらをSlackと連携しておけば、Slack上で動作させることができるようになります。
たとえば、文章作成エージェントや、コーディングエージェント。通常は、それぞれ単体のツールとして、専用のUI(ユーザー・インターフェース)を立ち上げる必要があります。しかし、それらをSlackにインストールすれば、SlackでAIエージェントと会話しながら、文章作成やコーディングを実行できるようになります。
他社ツールを含めたさまざまなアプリケーションは、Slackに連携させることで、Slack上での会話を起点として動作させることができます。個々のインターフェースの切り替えは必要ありません。私たちがSlackを「Agentic OS」と定義している所以ですね。SlackはAIエージェントの活用の入り口にもなるんです。

Q.6 他のSalesforce製品と連携できる?
SalesforceプロダクトとSlackの連携強化を進めています。それにより多くの機能が実装されてきました。
たとえば、AさんはSlackユーザーだが他のSalesforce製品は使っておらず、Bさんは反対に他のSalesforce製品のユーザーだがSlackは使っていないとします。Salesforceチャンネルを使えば、2人ともそれぞれのインターフェースで、Slackを立ち上げて会話ができるというものです。
まずSalesforceのインターフェースにSlackが組み込まれた「Salesforceチャンネル」です。Salesforceの画面上にある「Slackをアクティブにする」というボタンを押すと、Salesforceの画面上でSlackが使えます。
活用シーンとしては、社内の一部のチームではSlackを導入しており、他の部署では導入していないがSalesforceは使用している場合。あるいは、自社でSlackを導入しており、取引先は未導入だがSalesforceは使っているといった場合です。Salesforceチャンネルを使えば、Slackでスムーズに情報とデータの共有が可能になります。
さらに具体的に言えば、営業メンバーが使うケースです。Salesforceチャンネルによって、Salesforceにある商談レコードの検索や編集を、Slackから操作することができます。
従来なら、出先で商談を終えた営業担当者が、「Agentforce Sales(旧Sales Cloud)」を立ち上げてステータスを更新する必要がありましたが、いまでは、電車でモバイルからSlackを開き、商談の金額やステージの変更が簡単にできます。
営業マネージャーであれば、たとえばSlackからダッシュボードへアクセスして、チームの商談状況やパフォーマンスを確認できます。商談ステージに変更があれば、Slack上にアラートが飛ぶため、変化をすぐにキャッチできるようになります。

Q.7 Slackを導入するには?
Slackの導入パターンは大きく2つの傾向があります。トップダウンで組織全体に導入する場合と、一部門から使い始めて徐々に全社へと拡大させる場合です。
Q.2で紹介したカクイチは、トップダウンで導入した事例です。従業員に戸惑いが生じることもありますが、日常業務でSlackに触れてもらうことで、素早く全社へ浸透させることができました。
部門レベルから始める場合、上司に使ってもらうのが最も効果的です。チームで活用しつつ、上司に利便性を感じてもらえれば、徐々に他の部門へと横展開することができるようになります。
セールスフォース・ジャパンは、Slackの導入事例を紹介するイベントを定期的に開催しています。
成功事例に学ぶ生産性向上のヒント
さまざまなチーム、会社、業種で働き方の未来をどのように実現してきたかを示すサクセスストーリーには、効率を高めるためのヒントがいっぱいです。そのすべてに、Slack が貢献しています。



Slackを導入した企業が、どのような苦労を経て、なぜ導入に至ったのか、具多的な活用方法とともにお話しいただく機会です。これも上司と一緒に参加すれば、Slackの価値をより深く理解していただけると思います。
使ってみると、その使い勝手の良さから手放せなくなる企業が多く、Slackの解約率は非常に低い水準となっています。まずは気軽に試していただき、組織に合った導入方法を見つけていただきたいと思います。
導入したくても予算が厳しいという場合は、まずフリープランから始めるのも良い選択肢です。無料で使える範囲でも、Slackの価値を十分に感じていただけるはずです。
ワークスペースの管理
設定方法や管理方法について詳しく知りたい時は、ココをチェック!



Q.8 Slackのライセンス体系は?
Slackの料金プランには、無料で使えるフリープランと、有料プランがあります。フリープランは、過去90日間のメッセージ履歴まで閲覧・検索可能です。アプリ連携は最大10件に制限されますが、1対1のハドルミーティングやファイル共有(1GBまで)が可能です。
.png?w=1024)
有料プランは「プロ」「ビジネスプラス」「Enterprise+」の3つのグレードがあります。プランに応じて使える機能が異なる仕組みになっています。AI機能(AI in Slack)は、有償プランであればすべて利用可能です。
最もお手頃な「プロ」では、AI要約機能と、ハドルミーティングのAI議事録機能の2つが利用可能です。「Enterprise+」では、すべてのAI機能をフルに活用できます。「Enterprise+」以外のプランについては、AIでできることが限られていますが、段階的に機能が拡充されています。

詳細はこちらをご参考ください。
Salesforceのビジネスは大企業向けが多くを占めていますが、Slackはフリーランスや小さなコミュニティ、自治体でも利用されており、企業規模を問わず活用できます。中小企業で予算が厳しい場合は、まず無料プランから始めるのも良いでしょう。
Slackで実現する、中堅・中小企業の生産性向上
成長する企業は、人、情報、ツールをつなぐことでビジネスを次のレベルへと引き上げます。




Q.9 Slackはどう進化する?
冒頭にお話したように、SlackはAgentic OSを目指しており、Slackをすべての業務の入り口にする、中でもSalesforceのフロントエンドにするという構想があります。
これまでSalesforceの各プロダクトは、連携はしているものの、それぞれのインターフェース上で利用されてきました。しかし今後は、すべてのSalesforceの製品をSlackから利用可能にしていきます。
具体的には、Agentforce Sales(旧Sales Cloud)や「Agentforce Service(旧Service Cloud)」、「Agentforce Marketing(旧Marketing Cloud)」などのプロダクトを、Slackと「連携させる」のではなく、「Slackの中に組み込む」という構想です。これにより、Slackを入口として、さまざまなSalesforceプロダクトが利用可能になります。
この構想の背景には、Salesforce創業者のマーク・ベニオフが語った「人は会話をしながら仕事をしている」という思想があります。会話があってこそ仕事が進むからこそ、会話をすべての起点にしなければならない。ただ、それは、「Salesforce単体ではできなかった」といいます。2021年にSlackがSalesforceのグループに加わり、ようやくその構想を実現できる体制が整ってきました。
ほかにも、先日開催したDreamforceでは、5つのイノベーションを発表しています。主なポイントは下記です。

中でも進化した「Slackbot」は多くの方に関心を集めている機能で、アクセス可能なチャンネルやファイル、アプリにアクセスし、ユーザーの質問に答え、指示に対してアクションも自動で実行してくれます。まだ日本では提供されていないものもありますが、近日中に対応します。
そう遠くない未来、Slackを起点として、Salesforceのあらゆるプロダクトを操作できるだけでなく、他社のツールにもストレスなくアクセスできるように進化させていきます。それがAgentic OSを謳うSlackの基本方針ですから。これからのSalesforce、そしてSlackの進化に期待していてください。

取材:長沼良和、金藤良秀
執筆:長沼良和
撮影:大橋友樹
編集:木村剛士
SlackのAIで仕事を変革する10の方法
わずらわしいアプリの頻繁な切り替えにサヨナラしましょう。Slack は「Work OS」として、人、データ、ドキュメント、アプリ、AI エージェントを 1 つのハブに一元化します。