昨今はインターネットの普及が進み、膨大な量のデータを管理する必要性が高まっています。データを管理するための「データベース(DB)」の知識は、技術職はもちろん、営業やマーケティング職につく方にも欠かせません。しかし、データベースは実際どのようなものなのか理解できていない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、データベースとは何か、利用シーンや種類などの基本的な知識を解説します。エクセルとの違いや、メリット・デメリットもまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。
AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット
AIを活用して業務の生産性を向上させるためのおすすめの資料3つをセットにしました。3点まとめてダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。

目次
データベースとは扱いやすく管理・整理されたデータの集合体

データベース(DB)とは、管理および整理されたデータの集合体のことです。基本的に、決められたルールや形式に沿って整理されています。
たとえば氏名、電話番号、品番、コードなど属性ごとに分けることもあります。膨大な量のデータを扱いやすいようにするのが特徴です。
具体的には、商品在庫や顧客リストを管理する際に利用されます。非常に利便性が高く、多くのビジネスシーンで活用されています。
広義の意味では、紙の電話帳や辞書などもデータベースの一種といえるでしょう。
一般的なデータとデータベースの違い
一般的な「データ」と「データベース」の違いは、整理されているかどうかにあります。
一般的なデータは、収集した生の数字や事実などの結果情報が基本です。そのため、体裁が整えられていなかったり、内容によって情報の過不足があったりすることがあります。
一方でデータベースは、決まったデータ構造に沿って情報が整理されているのが特徴です。必要なときに適切なデータをすぐに取り出せます。たとえば契約者リストの中から東京都在住の人のみを抽出したり、担当者名を絞り込んだり、年齢が20歳以上の人をピックアップしたりできます。
データベースとエクセルの違い
データベースとエクセル(Excel)の違いは、用途にあります。
データベースは、データの管理や検索が主な用途です。エクセルに比べるとデータの保存容量が多いため、膨大なデータを扱う際に便利です。また専用のフォームからデータを編集するため、誤って元データを破損させるリスクが低いでしょう。ただし、データベースで情報を扱う際には、SQL言語のような専門的な知識が必要になる場合があります。
一方エクセルは、表計算が主な用途です。管理できるデータ数には制限があり、1シート最大1,048,576行までとされています。そのため膨大なデータを処理するのには不向きです。また、情報をセルに直接入力するため、修正や追加時に元データを破損するリスクが高いことも難点でしょう。
しかし誰でも気軽に使えるUIであるため、専門的な知識がなくても扱いやすいことが特徴です。
関連記事:エクセル(Excel)を活用した顧客管理方法|データベースの作り方も解説
データベースの種類と最適な利用シーン

ひと口にデータベースといっても、さまざまな種類があるのをご存知でしょうか?ここからは、データベースの種類と最適な利用シーンについて詳しく見ていきましょう。
今回紹介するのは、下記の5種類です。
- リレーショナル型データベース(RDB)
- ネットワーク型データベース
- 階層型データベース
- NoSQLデータベース
- オブジェクト指向データベース
それぞれの特性を知ることで、必要な場面で効果的にデータベースを使えるようになります。
1. リレーショナル型データベース(RDB)
リレーショナル型データベース(RDB)とは、複数のデータベースを関連付けて運用できるデータベースです。主に1980年代~現在まで、主流のデータベースとなっています。
エクセルのような表形式でデータを管理し、エクセルでいうシートを「テーブル」、列を「カラム」、行を「レコード」といいます。
リレーショナル型データベースはデータ同士の関係を整理しながら管理できるため、複雑な処理に適していることが特徴です。大量のデータを扱うと処理に時間がかかることがありますが、在庫管理や生産管理、人事データの管理など、正確なデータ管理が求められる業務で広く利用されています。
2. ネットワーク型データベース
ネットワーク型データベースとは、関連性のあるデータを互いに結び付け、網状の構造に整理して保存するデータベースのことです。
たとえば、大学生は複数のクラスに登録でき、クラスには複数の大学生が在籍します。ネットワーク型データベースでは大学生の情報をクラスごとに重複して保存するのではなく、ひとつの大学生情報を各クラスと直接結び付けます。これにより「多対多」の関係をシンプルに表現でき、データの重複を避けつつ効率的に管理できるのがメリットです。
3. 階層型データベース
階層型データベースとは、ツリーのようにデータを関連付けて保存するデータベースのことです。イメージとしては、親族関係図や会社の組織図のようなものになります。
階層型データベースは、上層から特定のデータに至るまでのルートがワンパターンです。そのため、データの検索・処理速度が速いというメリットがあります。
違うルートをたどる場合、同じデータを複数の場所に入力する必要があります。場合によっては、データ重複が起こりやすく、管理に手間がかかる点がデメリットです。
4. NoSQLデータベース
NoSQLデータベースとは、非構造化データと半構造化データを操作できるデータベースのことです。「非リレーショナル・データベース」とも呼ばれています。NoSQLには、キーバリュー型、ドキュメント型、グラフ型などがあります。キーバリュー型は、データがキーと値のペアで保存され、ドキュメント型は、JSONやBSON形式としてドキュメント単位で保存されるのが特徴です。またグラフ型は、ノード(頂点)とエッジ(関係)でデータをまとめます。
とくにビッグデータやリアルタイム処理に適しており、ネットワーク型や階層型などの従来型データベースと異なり、より実践的な利用が可能です。リレーショナル型データベース(RDB)のデメリットである、処理速度を解決できることから昨今注目されています。
RDBでは、事前にスキーマの定義が必要です。一方、NoSQLは事前にデータ構造を定義する必要がないスキーマレス仕様のため、たとえば、画像・音声データなどの非構造データを多く保持する際にも便利です。具体的には、ソーシャルゲームやIoTログ、チャット履歴などに利用されています。拡張性が高く、さまざまな用途で使えるのが特徴です。
SQL言語を使わないデータベースかつ、データのスキーマが柔軟なため特定の形式に縛られず、データ構造を後から変更できるメリットがあります。
5. オブジェクト指向データベース
オブジェクト指向データベースとは、オブジェクト指向の概念を取り入れ、データをオブジェクトとして扱うデータベースのことです。
オブジェクトとは、データとそれに関連する処理を一つの単位として扱うものです。階層的なデータ構造や相互に関連する情報を直感的に管理できるため、CADデータやマルチメディアデータのような複雑なデータ構造に対応できます。
データベースのメリット

データを管理するのに便利なデータベースですが、一般的な情報のまとめ方とは何が違うのでしょうか?ここでは、データベースのメリットを詳しく解説します。
データベースのメリットは下記の3点です。
- 業務を効率化できる
- データを簡単に更新できる
- 自動でバックアップできる
データベースを使うべきか悩んでいる方は、参考にするとよいでしょう。
メリット1.業務を効率化できる
データベースのメリットのひとつ目は、業務を効率化できる点です。信頼性の高いデータの管理には、整合性を維持しつつ並行処理を行うことが欠かせません。そのため、ACID特性(原子性、一貫性、独立性、耐久性)が求められます。
データベースは検索機能が優れているため、必要な情報を素早く取り出せます。また、トランザクション管理により複数人が同時にデータを扱えるのも特徴です。トランザクション管理とは、複数の処理を一つのまとまりとして扱い、すべての処理が正常に完了した場合のみ反映させる仕組みのことです。、これにより、ひとりが作業している間にほかの人が作業できないといったことが防げます。業務を同時並行で進められるため、結果として時間短縮につながるでしょう。
さらに、ほかのシステムと連携させてデータの傾向を分析できることも特徴です。単に情報をまとめておくだけでなく、購買傾向やイベント参加者の属性を分析できるため、戦略的かつスムーズな意思決定が可能になります。
メリット2.データを簡単に更新できる
データベースのメリットの2つ目は、データを簡単に更新できる点です。
データを手作業で管理する場合、一箇所の情報を修正すると、同じ内容が記載された複数の箇所をすべて手直しする必要があります。しかしデータベースではデータを一元管理できるため、一箇所を更新すれば関連する情報にも自動的に反映されます。すでにあるデータの編集・追加といった更新作業の手間を減らすことが可能です。
形式や内容の条件設定ができるため、誤入力を防ぐ効果も高いでしょう。適宜更新する必要のあるデータを管理する際には、データベースが便利です。
データの整合性や可用性に関する考え方として、ACIDとBASEがあります。ACID は、「常に正確なデータ処理が求められる場面」で重視される考え方で、トランザクションの整合性や信頼性を最優先します。一方、BASE は「多少の不整合があっても、システムを止めずに動かし続ける」ことを重視し、特に大規模な分散システムで採用されることが多い設計思想です。
メリット3.自動でバックアップできる
データベースのメリットの3つ目は、自動でバックアップできる点です。
データベースは自動のバックアップ機能がついているケースが多く、万が一誤ってデータを削除してしまった場合や、データ破損が起こった際にも復元しやすくなっています。たとえば、差分バックアップやリアルタイムレプリケーションといった機能は、クラウド型だけでなくオンプレミス型のデータベースでも採用されています。
製品によっては編集ログが残せるため、前のバージョンに戻したいときにも便利です。
データベースのデメリット

データベースにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。ここではデータベースのデメリットを詳しく解説します。
データベースのデメリットは、下記の2点です。
- 導入コストがかかる
- 明確な導入目的がないと使いにくい
あらかじめデメリットを把握しておくことで、データベースを適切に扱えるようになるでしょう。
デメリット1.導入コストがかかる
データベースのデメリットのひとつ目は、導入コストがかかることです。はじめてデータベースを導入する際には、サーバーの設置費用が発生します。そのため、事前にまとまった資金を用意する必要があります。
初期費用をなるべく抑えたい方は、サーバーを設置する必要がないクラウド型のデータベースを活用するのもひとつの手です。
デメリット2.明確な導入目的がないと使いにくい
データベースのデメリットの2つ目は、導入目的が明確でないと使いこなすのが難しいことです。
目的が不明確なまま導入すると、業務の効率化につながったのか判断しづらく、期待した成果が得られないことがあります。そのため、データベースを導入する前に、実務でどのように活用するのか、用途を明確にするのがおすすめです。
また、データの整理や検索に時間がかかると、かえって業務が煩雑になるリスクもあります。自社の状況を踏まえ、導入の必要性を慎重に検討しましょう。
プログラミング言語とデータベース言語は違うもの

プログラミング言語とデータベース言語の違いがよくわからないという方は多いのではないでしょうか。
システムを構築するための「プログラミング言語」とデータベースを操作するために使用する「データベース言語」は別物です。
プログラミング言語は、コンピュータのOS(オペレーションシステム)やアプリケーションに指示を出す言語です。
一方データベース言語は、データベースを管理するソフトウェア(DBMS)に対して、データの定義や操作などの命令を行うために使用します。プログラミング言語のように「手順」を記述するのではなく、「データに対して何をしてほしいか」を宣言的に記述することが特徴です。SQLはデータをどのように操作するかではなく、どのようなデータが欲しいかを記述する点で、手続き型言語と大きく異なります。また、DBMSに対して命令を送り、その結果を受け取るという対話的な操作も可能です。
データベース言語はあくまでもデータベースを扱うためのものなので、それ以外の制御は行いません。
AI搭載のデータプラットフォームならビジネスチャンスが広がる

Salesforceの「Data Cloud」は、構造化データと非構造化データをそのままの形式で一元管理できるデータプラットフォームです。
Data CloudはCRMデータや顧客の購買行動をデータとしてリアルタイムで収集・管理できます。収集したデータは、AnalyticsやTableauなどの分析ツールを用いることで、傾向や属性を知ることが可能です。データをもとに、見込み客の予測にもつなげられます。見込み客の特定から営業担当者への割り当てまでのプロセスを自動化できることもメリットです。
複雑なデータを統合・管理し、営業活動を効率化したいと考えている企業にとって、Data Cloudは有力な選択肢となるでしょう。Salesforceは自社でData Cloudを活用し、業務効率を上げています。活用事例について、下記で紹介していますので、あわせてご確認ください。
Salesforceが自社でData Cloudを活用する「Customer Zero」事例
その有効性は、Salesforce自身が「Customer Zero」としてData Cloudを積極的に活用し、大きな成果を上げていることからも明らかです。社内では「C360 Truth Profile」と呼ばれるData Cloudインスタンスを運用し、営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど、顧客に関わる全部門が参照するリアルタイムの統一顧客プロファイル(Customer 360ビュー)を構築しています。これは、Sales CloudやMarketing Cloudデータに加え、Google AnalyticsやTrailheadなど、290以上のデータストリームから15億件以上のレコードを統合し、約1億2000万件の統合プロファイルを生成することで実現されています。
この統合データ基盤の活用により、たとえばマーケティングでは、ターゲット広告の精度が劇的に向上。とくにLinkedIn広告では、ターゲットとのマッチ率が従来の20%から65%へ高まり、ROIが5倍になりました。営業プロセスでは、リード管理を自動化し、リードの処理時間を20分からわずか22秒に短縮。営業担当者がより迅速に有望なリードへアプローチできるようになり、効率が大幅に向上しました。カスタマーサクセスにおいても、顧客の学習状況(Trailheadデータ)やエンゲージメントを統合的に把握し、よりパーソナライズされた迅速なサポート提供に繋げています。
Salesforce自身がData Cloudを基盤としたデータ活用を徹底することで、データにもとづく迅速かつ精度の高い意思決定が可能となり、顧客体験の向上とビジネス成長を同時に推進しています。この「Customer Zero」としての実践事例は、Data Cloudがもつ変革の可能性を如実に示しています。
【業界別】Data Cloud ビジネス変革事例10選
ばらばらに点在する隠れデータ資産を活かして、営業・マーケティング・カスタマーサービス部門でビジネス変革を実現する具体的な方法を紹介します。
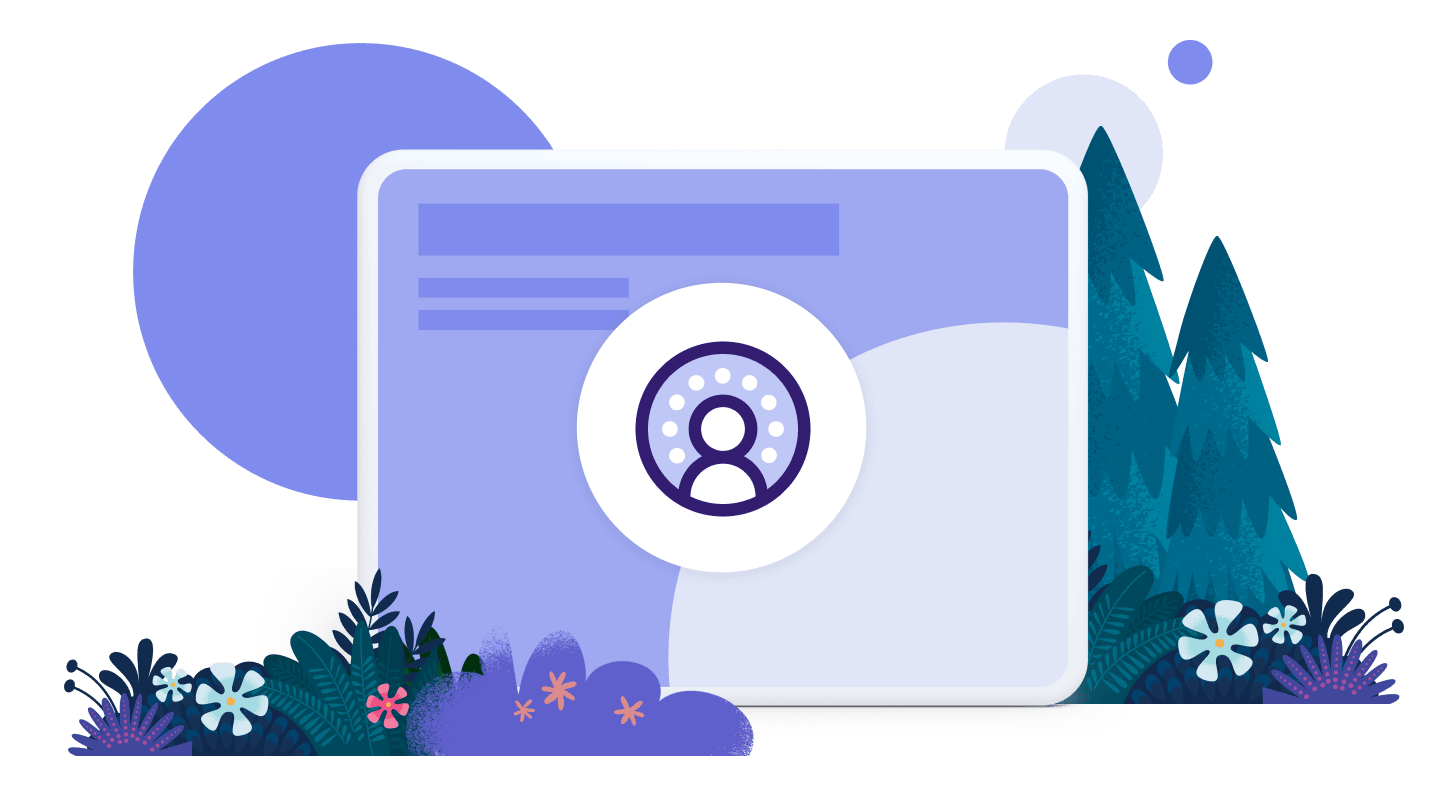
データベースを活用すれば業務を効率化できる

データベースとは、情報を扱いやすいように管理および整理したデータの集合体のことです。従来のエクセルなどのソフトに比べると、膨大なデータを扱う場合に適しています。情報の追加編集がしやすかったり、誤入力を防げたりすることも特徴です。
顧客データや販売履歴など、今後データ量はより膨大になっていくでしょう。大量の情報を正確に記録し、分析できるかどうかが企業の信頼性にもつながってくると考えられます。ぜひ自社でデータベースを導入してみてはいかがでしょうか。
関連記事:AIに対する就業者の信頼を左右するのはデータ:Salesforceによる最新の調査結果
AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット
AIを活用して業務の生産性を向上させるためのおすすめの資料3つをセットにしました。3点まとめてダウンロード頂けますので、ぜひご活用ください。






















