ビッグデータとは、人間では全体を把握することが困難なほど膨大なデータ群を指します。ビジネスに活用すると、業務の効率化や顧客理解を深めたマーケティング施策の立案などに効果的です。
しかし、どのように収集や分析を行って活用するべきか悩んでいる人も少なくありません。
本記事では、ビッグデータをビジネスに活用するメリット・デメリットについて解説します。実際に活用した事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット
AIを活用して業務の生産性を向上させたい方に向けて、すぐに活用できるヒントをまとめた資料をご用意いたしました。ビジネスにおけるAIの活用方法を幅広く知りたい方は、ぜひご覧ください。

関連記事:データ分析とは?行うメリットと9の分析手法ついて解説
目次
ビッグデータとは?

ビッグデータ(Big Data)とは、人間の力や一般的なソフトウェアでは処理しきれないほど膨大で複雑なデータの集合です。
データ量に明確な定義はありませんが、一般的に数テラバイト(TB)から数ペタバイト(PB)規模といわれています。
これは、スマートフォンで撮影した写真を1メガバイト(MB)と仮定した場合、以下の量になります。
- 1TB:100万枚(毎日100枚撮っても約27年間保存できる)
- 1PB:10億枚(1万人が毎日100枚撮っても約27年間保存できる)
この例を踏まえると、ビッグデータは人間が把握しきれないほどの量だとわかるでしょう。
ビッグデータの特徴は「データ量(Volume)」だけではなく、以下の「3V」と呼ばれるモデルで語られます。
- Volume:データ量
- Variety:データの種類や範囲の広さ
- Velocity:データの速度や頻度
ただし、近年では3Vに「Veracity(正確性)」と「Value(価値)」が加わり、「5V」と呼ばれるモデルで説明されるのが一般的です。
3Vまたは5Vを兼ね備えたビッグデータには、以下の例があります。

こうしたビッグデータを活用すると、データが持つ本来の意味や役割を超えて、新たな価値の発見や二次的効果の享受が期待できるのです。
総務省によるビッグデータの解釈
総務省は「平成29年版 情報通信白書」において、ビッグデータの構成要素を以下の3つに分類しています。
| データの種類 | 内容 |
|---|---|
| オープンデータ | 国や地方公共団体が提供するデータ |
| 産業データ | 企業が保有するパーソナルデータ以外のデータ |
| パーソナルデータ | 個人の属性に係るデータ |
また、これらのデータを個人・企業・政府などの間で円滑に循環させてイノベーションを促し、データ活用を経済成長に結びつけることを重要視しています。
ビッグデータの身近な事例
ビッグデータを活用した身近な事例は、以下のとおりです。
| 事例 | 内容 |
|---|---|
| 動画・音楽配信サービスのレコメンデーション | ユーザーの視聴・再生履歴を分析し、個人の好みに合わせたコンテンツを推薦 |
| 天気予報アプリ | 気象データや過去の天候パターンを分析し、より精度の高い天気予報を提供 |
| クレジットカードの不正利用検知 | 過去の取引データを分析し、通常と異なる利用パターンを検出することで不正利用を防止 |
ビッグデータは、予測やニーズの把握といった場面で多く使用されています。ビジネスにおいては、データドリブンな意思決定や正確な顧客ニーズの把握などに応用可能です。
ビッグデータの種類

ビッグデータにはいくつかの分類方法がありますが、狭義では次の3つに分類されます。
- 構造化データ
- 半構造化データ
- 非構造化データ
種類によって管理・処理の仕方が変わる点を押さえておくと、ビッグデータを活用する際に活かせます。
構造化データ
構造化データとは、列と行で構成されたテーブル形式のデータのことです。
たとえば、以下が該当します。
- 顧客情報
- 販売POSデータ
- 販売・生産実績
構造化データは整理と検索がしやすい特徴があり、データベース管理システム(DBMS)や関連するツールを使用することで、データの操作や管理を効率的に行えます。ただし、今後の増加はそれほど見込まれていません。
半構造化データ
半構造化データとは、完全な構造定義を持たないデータで、構造化データと非構造化データのハイブリッド型です。
たとえば、以下が該当します。
- Web操作のログデータ
- SNSに書き込まれたデータ
- センサーデータ
部分的に構造化データまたは非構造化データとなっているため、構造化データほど容易には管理できないものの、非構造化データよりは扱いやすいという特徴があります。専用のツールを使うことで、管理や処理の効率化が可能です。
非構造化データ
非構造化データとは、構造定義をまったく持たないデータを指します。
たとえば、以下が該当します。
- 防犯カメラ映像
- コールセンターの音声記録
- 文書記録
非構造化データは、構造化データのようにテーブル形式では管理できないため、データベースやデータウェアハウスによる管理が必要です。近年、非構造化データの量が爆発的に増加しており、ビッグデータの多くを占めるといわれています。
ビッグデータを活用するメリット

ビッグデータを活用するメリットは、次の3つです。
- 精度の高い予測分析ができる
- リアルタイムにデータを分析・可視化できる
- 顧客に合わせた顧客体験サービスを実現できる
ビッグデータの活用を進める際にメリットを意識して計画を立てると、高い効果を期待できるはずです。
精度の高い予測分析ができる
ビッグデータは、従来よりも膨大かつ幅広いデータであり、蓄積されたデータとリアルタイム情報を掛け合わせた分析ができるため、従来よりも精度の高い予測が可能になります。
たとえば、過去の気象データと収量データの統計解析により、農作物の収穫量を予測し、適切な栽培管理を行っているケースがあります。
ビッグデータの高精度な予測をもとに取り組んだ結果、従来より高い効果を得られれば、データに基づく意思決定のよさを実感できるでしょう。ビッグデータの活用は、勘や経験に頼る意思決定からデータに基づく意思決定へ移行するきっかけになり得ます。
リアルタイムにデータを分析・可視化できる
ビッグデータの活用は、ITツールを使って行われるため、データの蓄積から可視化までをリアルタイムの実行が可能です。
たとえば、カーナビや運転手のスマートフォンから位置情報を収集・分析して、リアルタイムの交通状況を通知できるシステムがあります。
最近はAIを搭載したデータ分析プラットフォームが増えてきており、より分析速度や精度が高まってきています。AI搭載型のプラットフォームを通じてビッグデータを活用すれば、企業におけるデータ活用や意思決定スピードも迅速化されるでしょう。
顧客に合わせた顧客体験サービスを実現できる
ビッグデータをもとにした多角的な分析によって、潜在的な顧客ニーズを捉えたサービスを展開できます。たとえば、ECサイトにおいては、登録した顧客情報や購買履歴に合わせた広告の配信によって、アップセルやクロスセルの促進が可能です。
アップセルやクロスセルとは、顧客単価を高める営業手法を指します。
また、過去のデータと現在の傾向を分析することによって、将来のニーズや行動の予測が可能です。先回りしたサービスの提供によって、顧客満足度の向上によるLTVの最大化を期待できます。
アップセルやクロスセルの活用方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
▶アップセル・クロスセルとは?違いや活用方法、成功事例を紹介
ビッグデータのビジネスに必要な技術

ビッグデータを活用するためには、データを蓄積・分析するプラットフォームが必要です。データ分析プラットフォームには、一般的に次の技術が活用されています。
- クラウドコンピューティング
- IoT
- AI
これらの技術の役割を理解したうえで活用できると、ビッグデータの活用効果を高められるでしょう。
クラウドコンピューティング
ビッグデータのような膨大なデータは、従来のハードディスク(HDD)やソリッドステートドライブ(SSD)では保存が困難なため、クラウドコンピューティング(クラウド)が必要です。
クラウドとは、インターネット上にデータを保存する考え方のことです。Google DriveやOneDriveのように、サービスとして提供されているケースもあります。
オンプレミスの自社サーバーにビッグデータを蓄積することも可能ですが、クラウドよりも初期投資が大きく、維持費もかかる点に注意が必要です。
ただし、セキュリティが高いため、金融機関や政府機関ではオンプレミスサーバーを使ってビッグデータを活用するケースが多くなっています。
ビッグデータを扱う際は、クラウドや大規模なオンプレミスサーバーを用意して、膨大なデータを蓄積できる環境の整備が求められます。
IoT
IoT(Internet of Things:モノのインターネット)とは、さまざまなモノとインターネットをつなぐ技術のことです。
たとえば、ビニールハウス内に設置したセンサーから温度や炭酸ガス量のデータをリアルタイムに収集できるシステムがあります。IoTを活用してセンサーとシステムをつなぐことで、ビニールハウスの監視と環境の維持ができるわけです。
このように、IoT技術を活用する際はIoTセンサーが必要です。IoTセンサーは、画像や音、光などさまざまなデータを収集し、クラウドに保存できます。
AI
AI(Artificial Intelligence:人工知能)とは、コンピュータに人間のような思考や知覚をさせる技術のことです。
たとえば、近年話題となっているChatGPTは、生成AIというAIの一種で、人間のように言葉を学び、人間の指示や質問を理解したうえで回答できます。この技術をデータ分析に活用すれば、専門知識がない人でも容易にデータを読み解けるのです。
膨大なビッグデータを分析するためにはAIが必要であり、AIによる高度な分析が新たな価値を創出します。
ビッグデータの活用をサポートする2つのツール

ビッグデータを活用するためには、AIが搭載されたデータ分析プラットフォームが重要です。ここでは、2つのツールをご紹介します。
- データの蓄積・分析を支える『Data Cloud』
- データをリアルタイムに可視化する『Tableau』
ビッグデータを活用するためにデータ基盤の整備に着手される場合は、ぜひ導入を検討してみてください。
データの蓄積・分析を支える『Data Cloud』

『Data Cloud』は、企業が持っているさまざまなデータをSalesforceのプラットフォーム上に集約して管理できるツールです。Salesforceが提供するCRMはもちろん、外部の多様なデータソースと連携し、分散されたデータを統合できます。
AIによるリアルタイムのデータ分析や高度なインサイトの抽出が可能となり、ビッグデータの活用をサポートします。
ビッグデータの活用基盤として役立つ『Data Cloud』の機能は、2分間の動画にまとめているので、ぜひご覧ください。
▶デモ動画を見る
データをリアルタイムに可視化する『Tableau』

『Tableau』は、ビッグデータの分析結果をリアルタイムに可視化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールです。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、データの分析・可視化ができます。
AIが分析をサポートしてくれるため、専門的なデータ分析の知識がなくてもビッグデータを活用できます。ビッグデータの活用基盤となって、企業における迅速な意思決定を促進させるでしょう。
無料トライアルを提供していますので、ぜひお試しください。
Tableau の無料トライアルを試してみよう
無制限のデータ探索と発見が今、始まります。
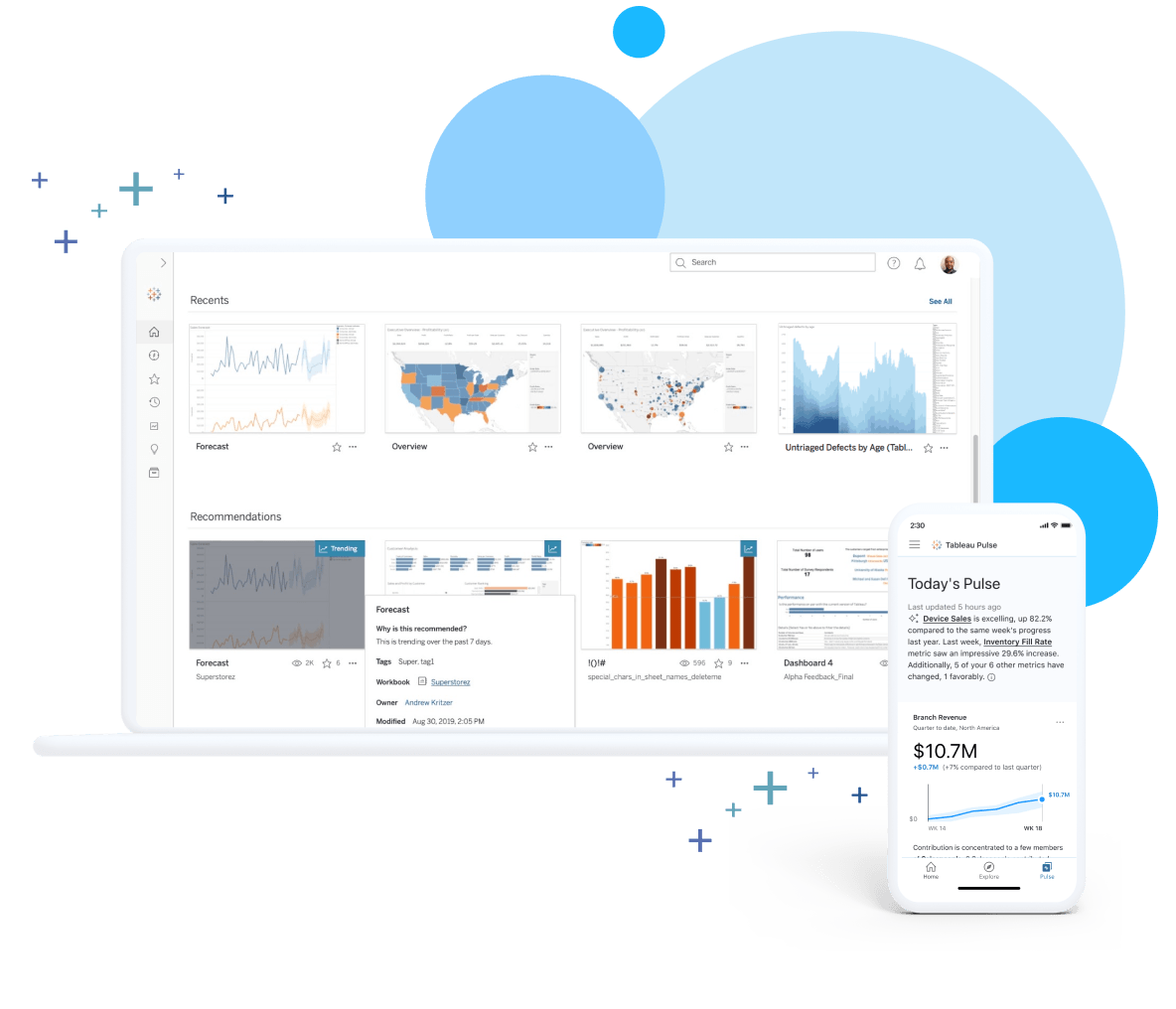
ビッグデータの活用事例

ここでは、ビッグデータの活用事例を3つ紹介します。
- 事例1.ビッグデータの可視化で意思決定を加速
- 事例2.ビッグデータを分析してパートナーに具体的なROIを提示
- 事例3.ビッグデータ×AIによるレコメンデーションでサービスを最適化
自社での活用イメージを深めるための参考にしてみてください。
事例1.ビッグデータの可視化で意思決定を加速

Marico Limited社は、アジアとアフリカの新興市場25か国で事業を展開する企業です。
同社は、ビッグデータの可視化を通じて意思決定を加速させるために『Tableau』を導入しました。従来は複数のデータソースに分散していた情報が統合された結果、データの可視化と分析の自動化を実現。
その結果、データ処理にかかる時間が大幅に短縮され、従業員がデータ分析やビジュアライゼーションについて日常的に議論する文化が醸成されました。
参考:Marico Limited 社: ビッグデータの課題に Tableau で対処
事例2.ビッグデータを分析してパートナーに具体的なROIを提示

the ENTERTAINER社は、世界15か国で10,000社以上の業者と提携し、消費者に多彩な特典を提供するロイヤルティおよびリワードのプロバイダーです。
同社は『Tableau』を活用してアプリから得られるビッグデータを分析し、パートナー業者に具体的な投資対効果(ROI)を提示しています。これにより、顧客プロファイルの作成や行動パターンの可視化が可能となり、パートナーが提供する特典を顧客ニーズに合わせて最適化できるようになりました。
データドリブンなアプローチにより、パートナーシップの強化と新たな収益源の創出が実現しています。
参考:Tableau のインサイトで世界のパートナー業者 10,000 社の具体的な ROI を高める the ENTERTAINER 社
事例3.ビッグデータ×AIによるレコメンデーションでサービスを最適化

エア・インディア社は『Data Cloud』と「Einstein 1 Service」を導入し、ビッグデータとAIを活用したレコメンデーションでサービスを最適化しています。
分散していた顧客データの一元化だけではなく、顧客対応の担当者はAIによる予測型レコメンデーションを活用して、迅速かつパーソナライズされたサービスを提供できるようになりました。
たとえば、フライト遅延時には、AIが自動的に座席のアップグレードを提案するなど、顧客体験の向上を実現しています。
参考:エア・インディア社はEinsteinを利用して、世界トップクラスの快適なカスタマーサービスを実現
ビッグデータを活用する際の課題問題点

ビッグデータをビジネスに活用するデメリットと問題点は、以下のとおりです。
- スキルを持った人材の確保が必要になる
- セキュリティ対策の強化が必要になる
- 管理や分析にコストがかかる
収集したデータを適切に活用できるように、それぞれ見ていきましょう。
スキルを持った人材の確保が必要になる
自社のビジネスでビッグデータを活用していくためには、専門的な知識や経験を持った人材の確保が必要です。IPA 独立行政法人 情報処理推進機構が発行する「DX白書2023」によると、調査対象となった企業のおよそ9割が「DXを推進する人材が不足している」と回答しています。
また、分析したデータを自社の戦略に落とし込むためには、技術的な知見にあわせてビジネスに対する洞察力を有している人材が有効です。そのため、採用戦略と合わせて自社での人材育成も検討していく必要があります。
セキュリティ対策の強化が必要になる
ビッグデータには、個人に係るパーソナルデータも含まれるため、セキュリティ対策の強化が必要です。
たとえば、商品の購入履歴やサービスの利用状況などの情報が流出してしまうと、プライバシーの侵害につながる恐れがあります。このようなリスクを避けるためにも、データの匿名化処理やアクセス権の厳格化などを実施して、セキュリティリスクを最小限に抑えることが求められるでしょう。
また、データ収集の範囲と方法を明確にすることで、顧客が予期せぬデータ利用を知って不信感を抱くことを防止できます。セキュリティの対策にともなって、組織全体の意識向上とシステムへの投資が重要です。
管理や分析にコストがかかる
ビッグデータの分析は、膨大な量のデータを扱うことから、データの整理・加工など管理や分析にかかるコストが増加します。具体的に発生するコストの例は、以下のとおりです。
| 発生するコストの例 | 内容 |
|---|---|
| インフラコスト | 大量のデータを保存・処理するために、高性能なサーバーやストレージが必要になる |
| 人材コスト | 専門知識を持つ人材の採用・育成にコストがかかる |
| データクレンジングコスト | 収集したデータの品質を保つために、データのクリーニングや正規化に時間と労力がかかる |
そのため、運用方針を明確にして、収集・分析するデータの選定や運用にかける予算の策定を事前に済ませる必要があります。
ビッグデータの活用を成功させるポイント

ビッグデータをビジネスに活用するポイントは、以下の3つです。
- 利用目的を明確にする
- 目的に沿ってデータの収集や加工を実行する
- 適切な方法でデータを活用する
限られたリソースの中で最大限の効果が得られるように、ポイントを押さえて活用を進めましょう。
利用目的を明確にする
ビッグデータの分析で扱うデータは多種多様であるため、分析結果からどのようなアクションを起こすのかといった目的を明確にする必要があります。
注意したいポイントは、手元にあるデータを起点として考えるプロセスに陥らないことです。
自社の課題や戦略に沿って決めた目的に応じて、既存のデータの捉え直しや足りないデータの収集を検討しましょう。
目的に沿ってデータの収集や加工を実行する
ビッグデータの分析で扱うデータには、誤記や未入力、重複などの不備が含まれている可能性があります。分析の精度を高めるために、データクレンジングが必要です。
データのクレンジングとは、データの不備を訂正して正確性を高める作業を指します。具体的に行う作業の例は、以下のとおりです。
- データ品質のチェックと不備の訂正
- 分析しやすいようにデータを整理
- 不要なデータの削除や形式の統一
また、システムを横断してデータを使いやすくするために、データ形式やフォーマットの統一を徹底し、日頃からデータ品質対策を講じるのも効果的です。
適切な分析手法を選択する
クレンジングを行ったデータは、分析することではじめて活用できる状態になります。
主なビッグデータの分析方法は、以下のとおりです。
- 決定木分析
- ロジスティック回帰分析
- アソシエーション分析
- クラスター分析
担当者に技術的な専門知識がなくてもツールの導入によって、さまざまなデータ活用が可能になります。
自社に蓄積したデータを活用する際には、課題解決や目的達成に適したツールを検討しましょう。
決定木分析
決定木分析は、過去のデータから特定のデータ項目を予測するための手法で、分類と予測を行うモデルです。データを条件に従って分岐させ樹木状の構造を形成することから、決定木と呼ばれます。
たとえば、顧客情報やアンケート結果などのデータを用いて、特定の属性に基づいて顧客を分類し、購買意欲の高い層を特定することが可能です。ターゲット層の明確化やマーケティング戦略の策定に役立ちます。
ロジスティック回帰分析
ロジスティック回帰分析は、特定の事象が発生する確率を予測する多変量解析手法です。主に「購入する・しない」などの二値データを扱い、データマイニングにおける予測モデリングやパターン発見に利用されます。
たとえば、顧客の購買行動を予測し、ターゲットマーケティングの最適化や異常値検知に活用できます。
アソシエーション分析
アソシエーション分析は、データ内の項目間の共起性に着目し、未知のルールを抽出する手法です。大量のデータから、特定の項目が同時に発生する規則性を発見します。
マーケットバスケット分析としても知られ、購買データの分析に活用されます。
クラスター分析
クラスター分析は、データ間の距離に基づく類似性によって母集団をクラスターに分類する手法です。たとえば、購買履歴や行動データをもとに顧客を分類し、各顧客グループの特徴を分析します。
このようにクラスター分析は、ターゲットマーケティングへの活用が可能です。
活用状況を検証・最適化する
ビッグデータの活用を進める際には、PoC(Proof of Concept:概念実証)を通じて、データ収集や分析手法の有効性を検証し、最適化を図ることが重要です。
PoCとは、新しいアイデアや技術の実現可能性を検証するプロセスを指します。検証と改善のサイクル(PDCA)を継続的に回すことで、ビッグデータ活用の効果最大化が期待できます。
ビッグデータの展望

国内では、国主導でビッグデータの活用が推進されており、今後も続くことが予想されます。
総務省は、ビッグデータの活用を促進するために「ビッグデータ・ポータル」を公開しました。このポータルは、ビッグデータの利活用事例や課題、その解決策などの情報が紹介されています。
利用者数は伸び悩んでいるものの、掲載されている利活用事例は増加傾向にあります。
今後、ビッグデータ・ポータルや関連法の整備が進むことで、国内におけるビッグデータの活用基盤が整っていくでしょう。
まとめ:ビッグデータを活用して自社の成長を加速させよう
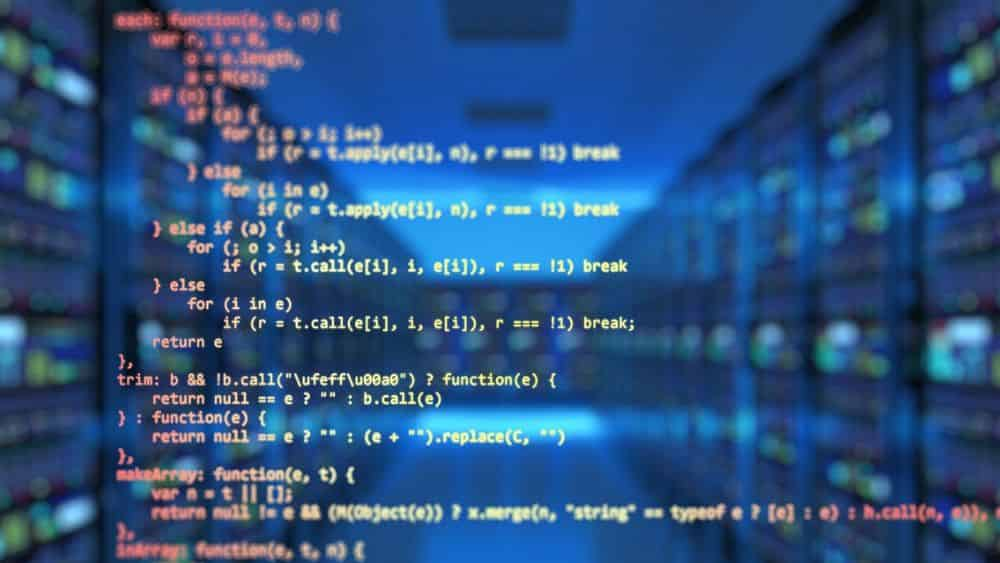
ビッグデータをビジネスに活用すると、業務効率の向上や顧客理解を深めたマーケティング施策の立案などに役立ちます。
ただし、ビッグデータを運用するためには、専門知識を持った人材の採用・育成や、ツールの導入が必要です。人材の採用や育成には時間がかかるため、AIを搭載したツールを導入して、専門知識がなくても運用できる体制を整える必要があります。
Salesforceが提供する『Data Cloud』と『Tableau』は、ビッグデータの活用基盤となるデータプラットフォームです。これまで蓄積したデータを移管したうえで、リアルタイムの分析・可視化を可能にします。
Salesforceでは、ほかにもさまざまなデータ活用ツールを提供していますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、以下の資料では、今すぐ役立つAI活用のヒントを紹介しています。ぜひご一読ください。
AIを活用して業務の生産性を向上させる資料3点セット
AIを活用して業務の生産性を向上させたい方に向けて、すぐに活用できるヒントをまとめた資料をご用意いたしました。ビジネスにおけるAIの活用方法を幅広く知りたい方は、ぜひご覧ください。






















