「DataFam Tokyo」は、データ利活用の方法を学べるセールスフォース・ジャパン主催のイベント。データ可視化&分析ツール「Tableau(タブロー)」と、AIエージェント「Agentforce(エージェントフォース)」、データ活用基盤「Data Cloud(データクラウド)」を組み合わせることで実現する新たなデータ利活用の世界を披露しました。
実施したセッションは40以上ですが、このほど人気を博したセッションに限定して、見逃し配信を開始しました。本記事ではその注目内容を紹介します。記事をご覧になっていただいた後に、ぜひ気になるセッションのアーカイブ映像もチェックしていただければ幸いです。
DataFam Tokyo
イベントアーカイブ
基調講演を含む6つのお客様セッションやクロージングセッションなど、当日の主要プログラムをオンデマンドでご覧いただけます。

目次
【Part1 Keynote】AIエージェントが切り拓くデータ分析の新時代
日本のデータ活用文化を支えるコミュニティの力
基調講演では、「Tableau」が描く次世代アナリティクスの姿として、AIエージェントがデータ分析をどのように変革していくのかを示しました。
最初に登壇したセールスフォース・ジャパンでTableau事業統括本部統括本部長を務める福島隆文常務執行役員は、日本の「Tableau」コミュニティの活動を称賛しました。
「年間107回以上のイベント開催、学生時代から『Tableau』を使い始める若手の増加など、日本においてデータ活用文化が着実に根付いています。データリテラシーとスキルを持った人材が社会に出ていくことで、日本は素晴らしい世界になるものと興奮し、期待しています」

株式会社セールスフォース・ジャパン 常務執行役員Tableau事業統括本部統括本部長
エージェント型分析プラットフォーム「Tableau Next」とは
米国本社から来日したエド・ボーランRVP, Sales Excellenceは、21年以上の歴史を持つ「Tableau」が今、AIによって大きな転換点にあることを説明したうえで、「エージェント型分析の時代には、分析にとどまることなく、その結果をアクションまでつなげていくことが私たちの使命です」と強調しました。

そして発表されたのが、2025年6月に日本語版がリリース予定の「Tableau Next」です。世界初のエージェント型分析プラットフォームであり、4つのレイヤーで構成しています。
- オープンなデータレイヤー
Salesforce Data Cloud上に構築され、セールス、サービス、マーケティングのデータや、Slackにある非構造化データ、Snowflakeのような外部データをゼロコピーで活用できます。 - AIセマンティックレイヤー
共通定義を設定し、組織内外で共有できます。みんなが同じ文脈で情報を見ることができるため、活動をスピードアップできます。 - 最新のビジュアライゼーション
リッチなビジュアライゼーション体験を提供します。 - 統合アクションレイヤー
データを理解するだけでなく、データを用いてアクションします。インサイトをもとに効果的なキャンペーンを実行することも可能です。
「Tableau Next」は既存製品群に加わる新たなポートフォリオであり、相互運用性を担保しています。例えば、「Tableau Desktop」のユーザーがセマンティックレイヤーを使うことによって、よりリッチなビジュアライゼーションを楽しむこともできます。

自然言語でデータと「対話」する時代へ
セールスフォース・ジャパン 製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部の杉村麟太郎プロダクトマーケティングマネージャーは、架空の小売業を想定したシナリオで「Tableau Next」のデモンストレーションを実施しました。
前半はアナリストがデータ接続からビジュアライゼーションの作成までを行うワークフロー、後半はビジネスの意思決定者がどのように活用するかを実演しました。
「『Tableau Next』の特徴の1つは、『Slack』との連携。従来のBIツールでは、ダッシュボードのURLを共有するのが一般的でした。しかし『Tableau Next』では、『Slack』で直接KPIを確認し、チーム内で継続的にコミュニケーションできます」。
また、ビジネスユーザーはダッシュボードの使い方を知らなくても、自然な日本語で質問を投げかけるだけで必要な分析結果を得られる様子も実演しました。

株式会社セールスフォース・ジャパン
製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマーケティングマネージャー
KDDIの「データ×AI戦略」を支える「Tableau」
ゲストスピーカーとして登壇したKDDIでパーソナル事業本部パーソナルシステム本部本部長を務める鍛原誠剛氏は、KDDIのデータ×AI戦略を説明。そのうえで、au IDやau PAY、Ponta Passなど非通信領域のシステム開発を統括する鍛原氏は、通信事業に加えてローソンへの経営参画など事業領域を拡大する中で、多様なデータを統合・活用できる基盤が重要であることを強調しました。
KDDIでは、「Tableau」利用者のスキルレベルに応じて最適な分析環境を提供しています。「これまではマーケターやアナリストが『Tableau』を使っていましたが、今は営業現場やコールセンターなど、分析スキルがそれほど高くない人たちに対してもデータを提供しなければなりません。新たなプレッシャーが生まれています」と鍛原氏は現在の課題を率直に語りました。
そこで現在取り組んでいるのが、営業担当者が使用することを想定した「Tableau Pulse」のPoCです。デモンストレーションでは、新規契約のデータをドリルダウンすると、さまざまな切り口でAIが自動的にインサイトを提示する様子が示されました。
「リテラシーレベルの異なる全ての従業員が、ワンストップで利用できる分析環境の実現できる基盤として『Tableau Next』には期待しています」と締めくくりました。
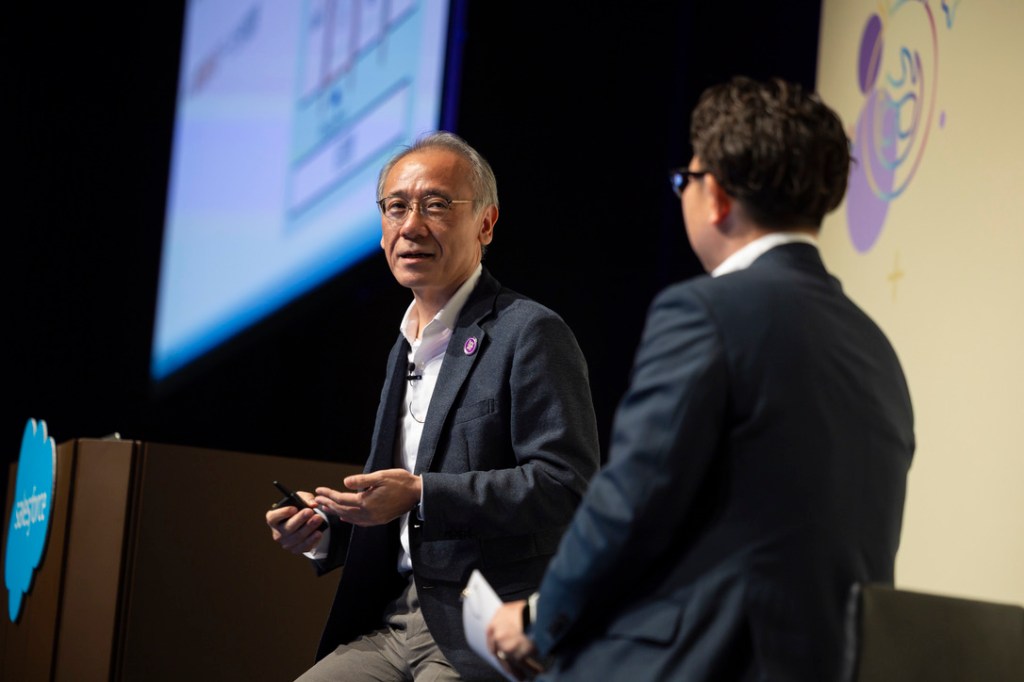
KDDI株式会社
パーソナル事業本部パーソナルシステム本部本部長
「Data Fam」とともにエージェント型分析のベストプラクティスを
再び登壇したエドは、Tableau NextだけでなくDesktop、Server、Cloud、Prepなど既存製品への投資も継続されることをデモンストレーションを交えて強調しました。
最後に福島は、「エージェント型分析のBlueprint」の日本語版リリースを発表。「これはバージョン1です。みなさんと一緒に、新しい時代のベストプラクティスを作っていきましょう」と呼びかけました。
【Part1 Keynote】
データに命を吹き込むAIエージェント~Tableauが切り拓く次世代アナリティクス



【Part2 Case Study】未経験者3名から135名へ。クレディセゾンのCreator育成とTableau定着
カウンター営業10年の経験から湧き出した変革への想い
クレディセゾンのDXは、内製開発チーム「テクノロジーセンター」の立ち上げからスタート。CXに加えてエンプロイー・エクスペリエンス(EX)との2軸で、CSDX(クレディセゾン・デジタルトランスフォーメーション)ビジョンを策定し、DXを全社で推進しています。
「Tableau」の利用は2021年10月に開始。社内公募でキャリアチェンジしたデジタル人材3人が、完全な初心者ながら独学で「Tableau」でのダッシュボード構築を開始しました。
その1人が、セッションに登壇したクレディセゾン株式会社でテクノロジーセンターデータ推進課係長を務める原田祐里氏。商業施設内の対面カウンターで10年間の営業を経験した後、データ抽出や集計業務を担当したことがきっかけとなり、「データで営業を支援したい」という想いから社内公募に挑戦し、データ可視化チームのリーダーへと転身した異色のキャリアを持ちます。
最初にリリースしたのは、経営層が閲覧する「主要営業係数ダッシュボード」と、利用社員の多い「現場向けの提携カード利用動向ダッシュボード」でした。これらを選定したのは、トップダウンとボトムアップ双方の「Tableau」の認知度向上を図るためでしたが、実際にリリースしてみると有用性やフォローによって認知度は向上しました。

株式会社クレディセゾン
テクノロジーセンター データ推進課係長
デジタル人材1000人創出を実現
2023年、内製開発のリソースが限界に達し、そこで「デジタル人材1000人創出」という目標を設定。全社員3700人の約4分の1という規模です。
「この人材が事業部の課題を解決するような開発を行う場合、エンジニアが行うようなコードを書いて複雑な開発を行うことは困難です。そのため開発の中心は、ノーコード・ローコードのようなツールや、『Tableau』のような BIツールとなります。そのため、このデジタル人材の創出において『Tableau』はとても重要な位置付けとなりました」(原田氏)
この実現のため希望者を対象に、半年間の「Tableau人材育成制度」を開始。自社データを使った学習ツールを内製開発し、最終的に部門長への報告で認定を受ける仕組みを構築しました。さらに「CS(シチズンデータサイエンティスト)Viz」イベントでは、認定者が経営層にダッシュボードをプレゼンし、直接フィードバックを受ける機会も設けました。
基礎知識習得後の「伴走構築」の仕組みも用意。このようにCreatorの育成を進めた結果、2022年の3名から、現在は29部門135名まで拡大しています。

【Part2 Case Study】
経営を動かすデータの力~クレディセゾンが挑む全社DXと経営企画の役割~



【Part3 Case Study】近鉄グループがデータで再発見した現場の強み
共通IDの分析でアナログ施策へ回帰
近鉄グループでは、過去2回データ活用の機運が高まった時期があり、作業時間が約10分の1になるなどの成果を上げたものの、定着には至りませんでした。
その原因を包み隠さず語るのは、近鉄グループホールディングス株式会社で総合政策部デジタル推進室データ・AI活用チームの課長を務める盛江佳史氏。「データ未整備」「費用対効果への疑問」、そして最も痛手だったのは「データ活用人材の転職」でした。
「データだけでなくスキルを持った人も集約した上で、人に依存しないチームを目指しました」(盛江氏)
2021年に設立されたデータ・AI活用チームは、差別化を図るため「リアルの現場を持っている強み」に着目し、現場に深く入り込むアプローチを採用しました。
マーケティングでのデータ活用で転機となったのは、グループ共通IDの導入でした。「Tableau」で定点観測ダッシュボードを作成し、流入経路をモニタリングしたところ、それまで百貨店やスーパーに偏っていたポイントカード利用が、ある日突然2倍に跳ね上がりました。要因は近鉄特急予約サイトへのバナー追加。特典も告知もない「サイレント追加」にもかかわらず、顧客が自発的に登録したのです。
「鉄道は我々の重要な顧客接点だった」と気づき、マーケティング戦略を転換。デジタル広告から駅ナカ看板やブース出展といったアナログ施策へと回帰しました。その結果、共通ID登録数は流通系のみの時と比べて2倍、デイリー登録数は1.5〜2倍に増加しました。

近鉄グループホールディングス株式会社
総合政策部デジタル推進室データ・AI活用チーム課長
データ分析で見えた「水曜日の真実」
伊勢志摩の観光サイト「ぶらりすと」の分析でも、意外な発見がありました。販売データから関東の20〜30代女性が主要顧客と判明し、広告戦略を見直した結果、アクセス数が約3倍に増加。さらに周遊チケットの利用分析では、「水曜日11時の利用が多い」ということが判明しました。
「一見不可解なデータですが、実は伊勢神宮周辺の店舗は水曜定休が多く、観光客が困っているという実態が数字で裏付けられたのです」と盛江氏。営業担当者は「やっぱり!」と膝を打ち、自主的にエリア拡大に動き始めたといいます。
この他に、インバウンド向けの施策でも課題解決にデータが役立っています。盛江氏は「データだけでは何も変わりません。でも、人と現場が動けば、世界は変わります。現場力にデータという武器を持ってもらうために、今後は『Tableau Pulse』の活用を検討しています。そして現場の方の先にいる、一番大事なお客さまにより良い価値を提供していきたいと思っています」と語り、セッションを締めくくりました。

【Part3 Case Study】
データで引き出す、人と地域の可能性~近鉄グループのマーケティング変革への挑戦~



【Part4 Case Study】組織規模10倍成長の裏側。Salesforce営業部門が実践するデータドリブン
小さな成功体験から始まる変革
「Tableau」を世界に提供するセールスフォースの営業部門は自社製品をどう活用し、いかにして組織を成長させてきたのでしょうか。
セールスフォース・ジャパンのTableau事業統括本部エンタープライズ第二営業本部第三営業部部長で務める鈴木祐基と、セールスディベロップメント本部エンタープライズ第三営業部Tableau事業部部長の熊谷憲一が、データ活用による組織変革の軌跡を語りました。
「私が入社した9年前には10数名だった日本の営業組織が、今では10倍の規模になりました。しかし、この成長は決して順風満帆ではありませんでした。かつてはオフィスで先輩社員がデータ分析する姿を間近で見て、自然とデータ活用が根付いていたのですが、組織拡大とリモートワークの普及により薄れ始めたのです」と鈴木は振り返ります。
「データを使う動機がない」「どう分析すればいいかわからない」「現状維持の引力が強い」という3つの壁を破るために採った策は、知識として分析の「型」を示して気づきを与え、これを動機に分析することで小さな成功体験を積み重ねる戦略でした。
デモンストレーションでは、顧客の従業員数と「Tableau」のライセンス浸透率を可視化し、「従業員数が多くてライセンスが少ない領域」を一目で特定できるダッシュボードなどを紹介しました。

株式会社セールスフォース・ジャパン
Tableau事業統括本部エンタープライズ第二営業本部 第三営業部部長
インサイドセールス部門でのTableau活用事例
熊谷が率いるインサイドセールスチームでは、「THE MODEL」に基づいた分業体制を敷いており、「Tableau」が業務の中核を担っています。新規リードのフォロー、既存顧客への最適なタイミングでのフォロー、そして効果的なアウトバウンド戦略。これら全てがデータに基づいて実行されています。
また、熊谷自身はマネージャーとしての仕事に「Tableau Pulse」を活用しています。デモンストレーションでは商談パイプラインを分析して、営業担当者のパフォーマンス課題を数クリックで特定できる様子が示されました。課題を見つけた場合には、即座に1on1ミーティングを設定して改善に向かうなど、データに基づいた迅速なマネジメントサイクルを確立しています。
熊谷は最後に「『Tableau』はレポートを見るだけのものではなく、アクションを導く武器にしていただきたい。いよいよAIが台頭してきた今、気づきをAIから受けて、行動の変化につなげなければならないタイミングです。ぜひ『Tableau』で強いチームを育てることにチャレンジしていただければ」と結びました。

株式会社セールスフォース・ジャパン
セールスディベロップメント本部 エンタープライズ第三営業部 Tableau事業部部長
【Part4 Case Study】
Salesforce営業の“リアル”:
Tableauで組織成長を加速する秘訣



【Part5 Business Discovery Dialogue】「Tableau」が解明する小惑星衝突危機とビジネスチャンス
「Tableau」は人類を救う?
クロージングセッションでは、立教大学AI研究科客員准教授でスペースデータ最高科学責任者の兵頭龍樹氏、サイエンス作家でZEN大学教授の竹内薫氏、宇宙キャスターの榎本麗美氏が登壇。「Tableau」を用いて小惑星データを分析し、地球防衛ビジネスから宇宙資源開発まで、データ分析が切り開く新たな可能性を示しました。

画面に映し出されたNASAの小惑星データベースを見て、「難しいデータが並んでいますね」と榎本氏。そこでNECソリューションイノベータの山本秀明氏が「Tableau」で「Tableau」で可視化すると、1950年代から2000年代にかけての発見数の急増が一目瞭然となりました。
「最近になって発見数がどんどん増えていることが、ぱっと見てわかりますね」と兵頭氏。この増加は観測技術の発達に伴うものです。

立教大学 AI研究科客員准教授でスペースデータ最高科学責任者の兵頭龍樹
竹内氏は、「私が生まれた1960年頃は、ほぼゼロですね。危険性に気づいていなかっただけ。事前にわかれば手を打つことができるので、安全になってきていると言えるのでしょうか」と兵藤氏に尋ねます。

サイエンス作家、ZEN大学教授
「これまで“知らぬが仏”で終わっていたものが、世界的に社会課題となっています。NASAやJAXAも研究を進めていますが、民間企業も新しいビジネスとして取り組むようになりました」(兵藤氏)
「具体的にどういったことで小惑星衝突を防ごうとしているのですか?」という榎本氏の質問に兵頭氏は、探査機をぶつけて小惑星の軌道を変えるビリヤード方式など、プラネタリーディフェンスの方法があることを紹介。さらに、「データがしっかり分析できれば、小惑星落下保険のようなビジネスが出てくるかもしれません」と可能性を示しました。
ここで榎本氏は、このセッションのタイトルである「Tableauで解明!宇宙の謎と地球の未来~恐竜絶滅の巨大隕石は再び東京に!?~」の答えを兵頭氏に求めます。兵頭氏は、人類存続に致命的な衝突は50万年に1度であるため、ひとまず安心できる確率だと解説しました。

宇宙キャスター
これに対して竹内氏は、「とはいえ恐竜が絶滅したことがあるわけです。危機に早く気づいて人類を救うツールとしても『Tableau』は重要かなと思います」と話しました。
宇宙資源としての可能性
続いてはテーマを大きく変え、小惑星の資源としての可能性を探りました。
例えば、地球から月まで1キログラムの資源を運ぶと1億円かかるため、地球にたまたま近づいてくる小惑星をうまく捕まえて資源として利用した方がコストは安価。米国の民間企業も参入し始めているビジネス領域です。
このことに注目し、小惑星まで片道で行くミッションと、往復で行くミッションをシミュレーションし、最適な出発年、到着時期、必要な燃料量、滞在日数まで具体的に計算したデータベースが公開されています。
このデータをもとに、NTTビジネスソリューションズの岡本あかね氏が「Tableau」で作成したビジュアライゼーションでは、各小惑星は資源タイプ(岩石・レアメタル、水分、金属など)で分類され、いつ出発すれば到達できるのかが一目でわかるようになっています。
「兵頭さんなら、どれを取りに行きたいですか?」という榎本氏の問いに、兵頭氏は「やっぱり一番大事な水を狙おうと思いますね」と即答。そして、「これならいつ出発するべきかがわかるため、探査機を作って打ち上げる意思決定に使えますね」と、実際のビジネスでの活用イメージを示しました。

わずか1時間半、標準機能のみで作成
このセッションで使われたViz、山本氏のものは約1時間半で作成されたといいます。「いや、それは驚異的ですよね」と竹内氏。兵藤氏も驚きをあらわにします。
しかも山本氏は、「Tableau」の標準機能だけで作成しており、ドラッグ&ドロップで大体のビジュアライゼーションを表現できると説明。岡本氏も「難しいことはしていない」と話します。
兵頭氏は「ミッションを提案する際、詳しくない方にもわかりやすく訴えかけるのに役立つだろうなと思いました」とビジュアライゼーションの価値を強調。竹内氏も「こういうツールがあるのであれば、出版物の綺麗な表紙や図版がすぐに作れるかな」と、自身のビジネスへの応用を考え始めていました。
【Part5 Business Discovery Dialogue】
Tableauで解明!宇宙の謎と地球の未来



盛りだくさんの内容で「AI×データ×ビジュアライゼーション」の可能性を示した「データの祭典」。過去最高の盛り上がりを見せた熱気をぜひ、アーカイブ映像でも感じていただければ幸いです。
DataFam Tokyo
イベントアーカイブ
基調講演を含む6つのお客様セッションやクロージングセッションなど、当日の主要プログラムをオンデマンドでご覧いただけます。






















