多くの企業が新しいシステムを導入する際に直面する課題「どうやってユーザーに使ってもらうか」。今回は、山口県に本社を置く創業81年の老舗物流機械メーカー、不二輸送機工業株式会社にお話を伺いました。
Salesforce(セールスフォース)を導入してから4年で、営業部門だけでなく設計、生産、総務、人事、情報システム部門まで約320人が活用するに至った導入ヒストリーに焦点を当てます。定着のお手本ともいえるその道のりから、実践的なヒントを探りました。
動画も用意していますので、以下より合わせてご覧ください。
Salesforce導入1年目のログイン・定着率向上のノウハウ
Salesforceの導入期を経験した先輩ユーザーの話から明日から使える取り組みのヒントをご紹介します。
登壇者:不二輸送機工業株式会社 谷浦 賢悟 氏



Speaker

不二輸送機工業株式会社 DX推進部 部長
Salesforceを活用した業務改革を推進。導入当初は、情報が部門ごとに分散し、属人的な業務が多いことが課題だったが、Salesforceを活用することで営業・製造・管理部門のデータをつなぎ、業務の効率化と意思決定のスピードアップを実現。「自動化と省人化のシステムを構築し、それを通じて社会に貢献する」ことに情熱を注ぎ、現在もDX推進部の責任者として、Salesforceを中心にデジタルプラットフォームを拡張しながら、全社的な業務改善を推進。
2021年にSalesforce導入。今では社員全員が使うインフラに
進行役:本題に入る前に、まずは会社の紹介をお願いします。
谷浦:不二輸送機工業は、山口県山陽小野田市に本社を置く物流機器・物流システムメーカーです。社員数は約320人、2025年で創業81年を迎えます。工場の生産性向上や効率化に貢献する装置やシステムを製造・販売しており、業務そのものが「現場」に根ざしているのが特徴です。
進行役:Salesforceはいつ導入したのですか。
谷浦:2021年4月で、今年で5年目です。今日は、私たちがこれまでSalesforceを社内でどのように活用してきたか、特に「現場に使ってもらう」ための工夫をお伝えできればと思っています。
進行役:ありがとうございます。では、早速詳しくお聞きしたいのですが、まずSalesforceを現在どのような部門や業務で活用していますか。
谷浦:営業部門に限らず、設計・生産、総務・人事、そして情報システムといった幅広い部門で利用しています。
たとえば、営業では顧客管理や商談・見積もりの作成、生産設計ではクレーム管理や仕様変更の依頼、総務部門では稟議申請や契約書管理など部門ごとの業務をSalesforce上で最適な形で進められるようにしています。
特に印象的だったのは、導入当初に感じていた「一部の人や機能しか使われない」という課題を業務の幅出しと工夫によって、徐々に解決したことです。

なぜSalesforceで売上と業務効率が向上するのか?
なぜSalesforceを活用すると、組織の売上と業務効率が向上するのでしょうか。このガイドでは、売上向上・業務効率化をもたらす仕組みと立場別のメリットについて、具体的に解説しています。
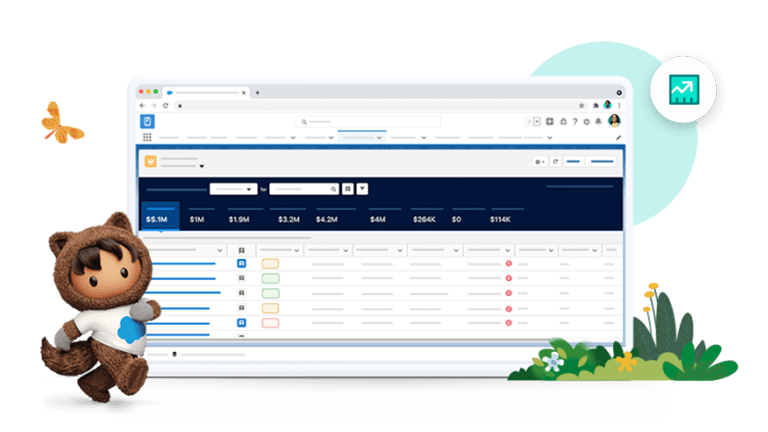
最初の壁は「使わざるをえない環境の構築」で突破
進行役:約320人の社員規模でSalesforceを導入するのは大変だったと思います。最初のステップである「ログインしてもらう」ためにどのような工夫をしたのか、教えてください。
谷浦:全社員に使ってもらうための第1歩であるログインのハードルを越えることは重要ですよね。
私たちはSalesforceを導入する時、グループウェアを新しくしたいというニーズが強まっていたので、「AppExchange」(*) にあった「 Argus(アルゴス)」というグループウェアも同時に導入したんです。
*「AppExchange」とは: Salesforceと連動するアプリケーションを購入できるマーケットプレイス。Appleでいう「AppStore」のような位置付けで、 Salesforceに便利な機能を追加し、システムを拡充できる。
そこで、考えた仕組みが「Argus」をSalesforceと連動させた基盤を作ること。つまり、社員が日常的に使うスケジュール管理や掲示板などのグループウェア機能を使うためには Salesforce にログインする必要があるという状況を作ったわけです。
進行役:日常業務に必須のツールを入り口にした、と。それは理にかなった方法ですね。結果はいかがでしたか。
谷浦:「ログインしてください」といった働きかけをしなくても、最初からログイン率 100% を達成できました。
グループウェアという全社共通のツールを入り口にしたことで、非常にスムーズなスタートが切れました。

進行役: まずは最初のハードルであるログインを見事にクリアしたわけですね。
ログインするだけでなく、その後使い続けてもらう、いわゆる「定着させる」段階では、別の工夫が必要になりますよね。この段階で、情報システム部門への問い合わせが急増し、対応に追いつかないという課題に直面したと伺いました。
谷浦:はい、その課題を解決するために構築したのが「クイック・サポート」という仕組みです。これは Salesforce の標準機能であるケースオブジェクト、問い合わせ管理機能を活用して、社内のあらゆる問い合わせを一元管理するシステムを作り上げました。
進行役:社内外からの問い合わせや依頼を集約・管理できる仕組みをSalesforceに構築したのですね。その運用で特に工夫した点はありますか。
谷浦:一番のポイントは、導入時に問い合わせ内容の細かい分類を設定しなかった点です。分類にこだわるとスピードは落ちてしまいます。そのため、初期の段階では詳細な分析よりも、まず迅速に対応して解決することを最優先にしました。
進行役:それはなかなかの割り切りですね。完璧を目指すのではなく、まずはスピードと利便性を優先した、と。その判断が現場の利用感や満足度につながったのでしょうか。
谷浦:そう思います。やっぱり問い合わせたらすぐに解決されるという体験が信頼感を生み、利用促進につながったと感じています。
完璧な分類や分析は後からでもできますから、導入初期のユーザーのつまづきにいかに早く対応するかが定着にはすごく大事だと判断しました。
ちなみに、ユーザーが使いやすいように、画面の下の方にあるユーティリティバーからすぐにクイック・サポートにアクセスできるように工夫もしています。

「10個試して1個成功すれば御の字」という心構え
進行役:細部にまで配慮しているのですね。導入から定着まで順調に見えますが、やはり波はあったのでしょうか。特に導入して2年目、3年目あたりは、推進する側と使う側のギャップで苦労された時期もあったとお聞きしました。
谷浦:もちろん波はありました。今もあります。どんな導入プロジェクトでも山あり谷ありですよね。
一連の導入・浸透過程を経験して、これから導入する人、浸透に苦労している人にアドバイスするとしたら、諦めずに社内理解を広げてサポートを手厚くすることが重要だということです。
「10個試して1個成功すれば御の字」という心構えも大事でしょう。
進行役:すごく前向きで勇気づけられる言葉ですね。具体的には、どのような取り組みが「試す」ことにあたるのでしょうか。
谷浦:ポイントは4つです。
- 他社の事例をとにかく集めること。
- 良いなと思った施策は、タイミングを見計らってまず試してみること。
- ユーザー会やコミュニティに参加して生の声を聞き、それが自社に合うか考えること。
そして、これが一番重要かもしれませんが、困ったら Salesforce の担当者に「あなたならどうしますか?」と具体的な状況を伝えてアドバイスを求めること。この直接聞くという行動が非常に役立ちました。
進行役: 他社事例の収集、良いと思ったら試す、他の導入企業の生の声を聞く、そして困ったら Salesforceに直接聞く。
不二輸送機工業の取り組みからは、「Argus」の導入など適切な技術選択と運用プロセスへの注力(クイック・サポートでのスピードを重視した社内サポートなど)に加え、「まずやってみる」「困ったら聞く」という継続的なトライと改善の姿勢が、定着のカギだとよくわかりました。
単にツールを入れて終わりではなく、日々の業務プロセスにどう組み込み、変化の中で社内ユーザーをどうサポートするかが成功の分かれ目なのですね。
谷浦:まさにその通りだと思います。
進行役:本日は貴重なお話をありがとうございました。「仕事を進めるにはSalesforceを使うのが当たり前」という状態をどう作るか。そんな定着の工夫がたくさん詰まったお話だったと思います。
Salesforce導入1年目のログイン・定着率向上のノウハウ
Salesforceの導入期を経験した先輩ユーザーの話から明日から使える取り組みのヒントをご紹介します。
登壇者:不二輸送機工業株式会社 谷浦 賢悟 氏






.jpeg?w=150)







.jpeg?w=150&quality=60)













