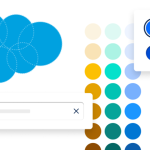目次
初の開発者向けイベントが日本でも
Salesforceが毎年開催する開発者向けの年次イベント「TDX」が、今年初めて米国を飛び出し、各国で開催されています。その第1弾となったのが、日本。2025年4月25日に開いた「Salesforce TDX Tokyo」です。
TDX Tokyo
AI時代を切り拓く
開発者カンファレンス
50以上のテクニカルセッションと実践的ハンズオン等でAgentforceを深く学び、AIエージェントを構築するスキルを習得。開発者・エンジニア・アドミンとして、あなたの会社と自身のキャリアに変革をもたらします。

CIOやCTO、CDOなどのデジタル戦略をリードする経営幹部や開発者、ITエンジニア向けのイベントでは、50以上のテクニカルセッションと実践的ハンズオンなどで、SalesforceのAIエージェント「Agentforce(エージェントフォース)」を深く学ぶ機会を提供しました。来場いただいたみなさん、誠にありがとうございました。

オンサイトでのイベントでしたが、主要セッションのオンデマンド配信を開始しました。最新機能に関するセッションでは豊富なデモンストレーションを交えて紹介しており、その全編も配信しています。本記事では、主要なセッションでオンデマンド配信しているセッションの概要を紹介します。
【Part1 Keynote】AIエージェント時代の幕開けをAgentforceで
発展・進化のための「最後の砦」
基調講演では、「Agentforce(エージェントフォース)」のビジョンと最新機能を紹介しました。
まずSalesforceのパトリック・ストークスEVP Product & Industries Marketingが登壇。ストークスは冒頭に、過去のビジネス発展における3つの障壁として「場所」「インフラ」「労働力」を挙げました。

「場所はインターネットにより、インフラはクラウドで克服できましたが、労働力はまだ『デジタルオプション』がなく最後の障壁として残っています。この障壁を打破するのが、AIエージェントという『デジタルレイバー(デジタル労働力)』です」
AIエージェントを実現するには、LLM(大規模言語モデル)だけでは不十分であり、データ連携やAPI統合、RAGなどの複数のテクノロジーを1つのプラットフォームで実現する必要があります。
Agentforceはこれらすべてを包含し、データやアプリ、エージェントを統合したプラットフォーム。ストークスは事例を紹介しながら「Agentforceカンパニー」になるように呼びかけ、それには「Agentblazer(エージェントブレイザー)」が重要であることを強調しました。これに関連して、「Agentblazer」の認定制度、無料開発環境の「Agentforce Developer Edition」の提供開始もアナウンスしました。
この後、「すべてのアプリとワークフローをAIエージェント化する」「AIエージェントを高速に開発し展開する」「AIエージェントのエコシステムを拡大する」という3つのテーマについて、プレゼンターが深掘り。大部分をデモンストレーションに割き、開発者が直感的に理解しやすい内容となっています。下記に主な内容を紹介します。
基調講演 : Become an Agentblazer. Build Agentforce Companies.
もしお客様からの問い合わせの80%を自律的に解決できるAIエージェントを開発できたらどうでしょう。もし、ファイナンシャルアドバイスや行政サービス、医療ケアのガイドを行うAIエージェントが開発できたら、企業はどれほどのデジタル労働力を得られるでしょうか。



すべてのアプリとワークフローをAIエージェント化
セールスフォース・ジャパンの深田紘平Product Management Managerは、AIエージェントによって変わるソフトウェアの「データ」「ロジック」「UI」を解説しました。データは構造化データ中心からベクトルデータベースや非構造化データの活用へ、ロジックは自然言語指示による柔軟な推論プロセスへ、AIによる自然な対話インターフェースへとシフト。
そして2024年12月にリリースした「Agentforce 2.0」の推論能力強化について触れた後、Developer Experience(開発者体験)を向上させるためのツール「Agentforce 2dx」を発表しました。
「変数」によるエージェントアクションの制限、FlowとApexの呼び出し可能アクションによるヘッドレスエージェントの実現、「Surfaces」によるユーザーとのより自然なインターフェースを実現するコンポーネントなど、主要機能が紹介されました。
その上で、セキュリティホームケア企業Vivintの斬新な事例を通じ、開発から実装までの一連の流れを実際の画面操作で詳しく示しました。
AIエージェント開発の新ライフサイクル
一方、セールスフォース・ジャパンの前野秀彰・製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマーケティングディレクターは、AIエージェントの信頼性を高めるための新たな開発ライフサイクルを紹介。
発案と計画、ビルドに続いて、非決定論的なシステムであるAIをどうテスト、デプロイ、監視・改善していくかという課題に対する新しいアプローチを解説しました。
また、Salesforce Japanの松尾吏セールスフォース・ジャパン製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部シニアディレクターは「AIエージェントのエコシステム拡大」について説明。
「AppExchange」の成功事例を紹介した後、Agentforce専用のマーケットプレイス「Agent Exchange」(英語)を発表しました。「Agent Builder」に組み込まれた「Agent Exchange」を通じて、簡単にエージェントを拡張できます。デモンストレーションでは、ワンクリックで必要な機能が追加できる様子が実演されました。
基調講演 : Become an Agentblazer. Build Agentforce Companies.
もしお客様からの問い合わせの80%を自律的に解決できるAIエージェントを開発できたらどうでしょう。もし、ファイナンシャルアドバイスや行政サービス、医療ケアのガイドを行うAIエージェントが開発できたら、企業はどれほどのデジタル労働力を得られるでしょうか。



【Part2 Case Study】アフラック生命保険のAgentforce活用術
アフラック生命保険で執行役員を務める白羽隆浩氏を迎え、セールスフォース・ジャパンの専務執行役員製品統括本部長の三戸篤とAIエージェントの実践と展望を語り合いました。
創業50周年を迎えたアフラック生命保険は、生成AIとデジタルサービス、データ利活用の3つのテクノロジーを活用したデジタル戦略を展開し、「感動的なお客様体験の提供とコスト競争力の向上」を目指しているといいます。
「Agentforce」の採用理由について、「『Service Cloud』、『Financial Services Cloud』、『Data Cloud』、『Tableau』などSalesforceのソリューションを多面的に活用していることから、自然な流れでした」と白羽氏は語りました。

アフラック生命保険ではすでに2つの業務で「Agentforce」を活用。1つ目は保険募集業務支援で、マニュアルや約款参照などの煩雑なオペレーションをチャット形式でシンプル化し、その回答をAgentforceが状況を判断して提供します。
2つ目は営業活動支援。訪問前準備の作業負荷が課題でしたが、「Agentforce」が訪問準備をサポートし、最適な訪問ルートを提案します。
将来的には「Agentforce」を最大限活用して、エンドツーエンドで顧客とのタッチポイントを増やし、保険業務の効率化・自動化を進めていく方針です。さらにはAIエージェントが顧客、ビジネスパートナー、株主、社会、社員の5大ステークホルダーをあらゆる場面で支援する世界を目指しています。
Q&Aセッションでは、自律型AIの可能性とデータ活用の重要性について議論が交わされました。
白羽氏は「人とAIの協働」がポイントだと指摘。特に保険業界ではパーソナライズの重要性が増す中で、多様化する保険商品のバリエーションに対応するためにはAIエージェントが不可欠だと説明しました。

また、「データはこれからのビジネスで一番重要」と強調し、「Data Cloud」を中心に据えてAgentforceを活用するSalesforceの取り組みを評価。同社ではゼロコピー技術や「Data Cloudコネクタ」、「MuleSoft」による外部データとのAPI連携などを活用して、シームレスかつ効率的にデータを収集し、分析して新たな価値を生み出す取り組みを進めていると話しました。
保険業界におけるAIの価値については、少ない顧客とのタッチポイントを増やすことが重要だと白羽氏は説明します。AIエージェントによって人だけでは対応しきれなかったアプローチを実現し、同時に人の役割を高度化していくことで「新たな顧客とのエンゲージメントの形を作れるのではないでしょうか」と展望を語りました。
CIOに聴く〜AIエージェントAgentforce で切り拓く、顧客体験の未来〜
パイオニア精神に基づき、保険商品・サービスを提供してきたアフラック生命保険株式会社が新たに挑むのは、「自律型AIエージェントによる顧客体験の変革」。
企業の競争力を高めるためのAI 戦略、Agentforce 導入の狙い、そして今後のAgentforce活用の展望について語り合いました。



【Part3 Future of Agentforce 怒涛の新機能リリース】
このセッションでは、セールスフォース・ジャパンで製品統括本部 プロダクトマネジメント&マーケティング本部 プロダクトマネージャーを務める永田祥平と稲葉洋幸が登壇。基調講演で紹介した「Agentforce」を深掘り。特にAIエージェントのライフサイクル全体をサポートするプラットフォームとしての進化に焦点を当てた解説を行いました。
前半では、AIエージェントの開発・改善サイクルにおけるステップおよび課題を説明。後半はこの課題に対するアプローチを、デモンストレーションを交えて紹介しました。
「発案と計画」では、基調講演でも紹介した通り、「Agentforce」と「Data Cloud」を無料で試せる「Developer Edition」を紹介。「ビルドでは、エージェント開発をサポートするAIアシスタントが今後提供を開始することをアナウンスしました。
「テスト」では、品質向上の効率化を実現するテストセンターの新機能「ワークベンチ」を取り上げ、多様な入力パターンを自動生成し、エージェントの応答をテストできることを紹介。従来は単純な設定情報からテストケースを生成していましたが、今後は過去の会話や関連データを基にしたよりリアルなテストケース生成が可能になります。

また、コマンドラインからのエージェント作成、編集、テストに対応したVisual StudioプラグインやPythonライブラリの「Salesforce Agentforce SDK」も提供予定です。
「デプロイ・利用」では、人間との会話だけではなく、APIを使ってエージェントを呼び出し、結果もそのAPIの返り値として受け取ることができるAgent APIの提供が開始されています。
最後のプロセス「監視」では、運用中のエージェントのパフォーマンスを詳細に分析するツールとして「Interaction Explorer」を開発中です。AIが会話内容をグルーピングして自動タグ付けし、課題のあるトピックを特定。各会話の詳細分析から、エージェントがどのステップで時間を要しているか、どのような改善が必要かまで具体的に提案します。
Agentforce最新ロードマップとIT戦略 〜次世代エンタープライズAIをどう活かす?
昨年9月に登場したAgentforceは、12月のAgentforce 2.0で大幅に機能強化され、AIエージェントの実用性が飛躍的に向上しました。本セッションでは、CIO・IT部門・アーキテクト・開発者向けに、エンタープライズIT戦略の観点からAgentforceの最新ロードマップを解説します。



【Part4 Strength of Agentforce】「頭脳」の中身を徹底解説
「Agentforce」が自ら考え意思決定するための「頭脳」にあたる「Atlas推論エンジン」を深掘りしたセッション。前半は、セールスフォース・ジャパンの製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマーケティングシニアマネージャーの王小芬が「Atlas推論エンジン」の全体像を中心に解説。
「Atlas推論エンジン」とは、「計画する」「道具を使う」「見直す」「検索する」という流れで、人間(ユーザー)とLLMとの間に立って、データの入出力の仲介を行いながら、自律的なアクションを行います。
例えば「返品したいです」という問い合わせに対し、注文状況検索や返品ポリシー確認などのアクションを計画・実行しながら、必要に応じて計画を見直していきます。
後半は、セールスフォース・ジャパンで製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマネージャーを務める荘茗が「検索する」について、人間に近い熟慮的な回答を生成するために重要であること解説しました。

昨年導入された基本的なRAG機能が「RAG 2.0」として大幅に強化。「非同期データ取り込みフロー」の強化では、検索前のデータチャンクにメタデータを付加し、検索精度が向上しています。
「ライブ検索フロー」の強化では、ユーザーの曖昧な質問を自動的に書き換えて検索精度を高める「クエリー書き換え」、複数のデータソースから情報を取得する「アンサンブルレトリーバー」、回答の信頼性を高める「引用元の記載」機能が追加されました。
デモンストレーションでは、43ページのPDFマニュアルを検索対象とし、RAG 2.0の「チャンク強化」機能をオンにするだけで、質問に対する検索精度が劇的に向上する様子が示されました。
解き明かせ、Agentforceの頭脳! Atlas推論エンジン Deep Dive
Agentforceの核心を担う「Atlas推論エンジン」。AIエージェントの推論能力を支えるこの技術は、一体どのような仕組みなのでしょうか?
本セッションでは、Atlas推論エンジンの内部構造を解説し、Agentforceが生み出すAIエージェントの価値を深く理解することを目指します。AIの可能性を広げる革新的技術、その本質に迫る Deep Dive セッション!



【Part5 Agentforce × Tableau Next】BIツールとの融合による新世界
本セッションでは、CRMに生成AIを掛け合わせるだけではなく、ビジネス・インテリジェンス(BI)ツール「Tableau」と組み合わせることによる進化が示されました。
まず、セールスフォース・ジャパンの製品統括本部プロダクトマネジメント&マーケティング本部プロダクトマーケティングマネージャーの杉村麟太郎が、「CRM×AI×Data」というキーワードを掲げ、CRMを導入してAIやデータを利活用する価値を、調査機関のレポートを交えながら説明しました。
そして「Tableau」の生成AI機能を2つ紹介。「Tableau Pulse」では、フォローすべきKPIをモバイルに最適化された形で閲覧することができます。誰もが簡単にデータの切り口を変えながら分析を行えることを、デモンストレーションで示しました。もう一つの「Tableau Agent」は、アナリストが会話型のユーザーインターフェースを使いながら分析を代理で行ってもらえる機能です。
3月にグローバル一般提供が開始された「Tableau Next」も紹介しました。「分析して終わり」にせず、自律的な行動をAIが行うエージェント型アナリティクスデータプラットフォームです。
後半はセールスフォース・ジャパンのTableau本部Analytics Specialistの劉潔がデモンストレーション。営業マネージャーのシナリオでは、売上減少の状況において、従来なら一日かかっていたような分析作業がAgentforceとTableau Nextの連携によって数分で完了する様子が示されました。
Agentforce × Tableau Next:AIが変えるデータ分析の未来
データ活用が企業の競争優位を決める時代。しかし、「データはあるのに、うまく活用できていない」 と感じていませんか?
Tableau Next は、Salesforce プラットフォーム上に構築され、Agentforceと統合された次世代のエージェント型分析プラットフォーム です。
AIエージェントが、データ探索・インサイトの発見・予測・アクションの提案 をシームレスに支援し、これまでにないスピードで意思決定を実現 します。



【Part6 AI Specialist Dialog】タイミーVPO ×AIエンジニア・SF作家×日本CTO協会の特別鼎談
クロージングセッションでは、タイミーVPOの赤澤剛氏をモデレーターに迎え、AIエンジニア・SF作家の安野隆博氏とレクター代表取締役・日本CTO協会理事の広木大一氏が、AIが急速に進化する世界でのエンジニアの役割と組織の在り方を議論しました。

Theme 1:エンジニアの価値と役割の再定義
安野氏は、AIによる影響はジュニアエンジニアとシニアエンジニアで大きく異なると指摘。
「AIコーディングアシスタントは、ジュニアエンジニアが慣れるきっかけとなる簡単なタスクを全部消化し切ってしまいます。一方で、経験のあるソフトウェアエンジニアはAIによってものすごくブーストされる。意思決定の比重が高まってきているので、シニアエンジニアにとってはすごくいい時代です」と述べました。
広木氏は、「若手のことはそんなに心配していません。インターネットが出始めたときと同じように、ニュータイプ的な人が出てくるでしょう。むしろ課題があるのは中間の20代や30代で、急激な変化の中でアンラーニングして自分をチェンジしていけるかが問われています。
AIという個人がハンドルできるリソースが手元にあり、そしてエンパワーされている時代ですから、自分が考えるべきことのレイヤーがどんどん変わっていくという感覚を持って、考える内容や構想する内容自体をアップデートできるかです」と語りました。
Theme 2:AIエージェントと人間の協働
広木氏は続いて組織変革について「短期的には、まず少人数でソフトウェアを開発できる前提で組織をシフトし、そこから生産性向上の方法を模索する。例えば50人のチームを5人に、10人を2人にできないかを考えるとき、先にその状況を作ってしまうのです。みんなが少人数でも開発可能だと認知してから対応したのでは出遅れます」と提言します。
安野氏はAIを活用したコミュニケーション改善に注目し、「AIが人と人の間に入ることで、誤解や対立を減らせる可能性があり、LLMの1つのキラーユースケースです。例えばSlackで送信前にメッセージを改善提案してくれるAIがあれば、チーム内の不要な摩擦が減るでしょう」と話しました。
広木氏も「感情労働的な部分こそ、AIによる代替や仲介の大きな価値があります。他には目標設定の際に、組織のミッション、ビジョン、バリューに沿っているかの評価をAIがサポートすることで、マネージャーの負担軽減も可能でしょう」と同意しました。
Talk Theme 3:日本企業のAI活用と競争力
安野氏はデジタルデバイドの問題に触れ、「例えば、車の中身を理解していなくても自動運転ロボタクシーに行き先を伝えられたら移動できますよね。それと同じようなことがAI社会ではいろいろと起きると思っています。むしろAIは、誰も取り残さないという理想に近づけてくれるのです」と、社会にとって重要なテクノロジーであると語りました。
広木氏は、「社会は人口が減っていく分、半導体に動いてもらわなければならないものが増えます。日本の得意分野であるロボティクスでもAIの活用が進みます。多くの人がよりハッピーな社会になっていく可能性が十分にあるでしょう」と話し、少子高齢化という日本の課題がAI活用の原動力になるというポジティブな考えを示しました。
続けて安野氏は、「AIを活用するという話になると、アメリカやヨーロッパでは『雇用はどうなるのか』とデモが起きてしまいますが、日本では起きない。組織としても個人としても活用していこうというインセンティブを持っています」と、AI活用において日本が有利な状況であることを付け加えました。
クロージング:個人・組織・社会で見るAIと共に歩む未来
セッションの最後に赤澤氏は、日本がAI活用先進国になっていくための要素を尋ねました。
安野氏は、「『指数関数を信じろ』。どんどんAIのモデルはよくなっていく前提で、個人も組織も社会もよくなっていく構造をうまく作れるかどうかが重要です。そして『楽しもう』。この変化によって、できることが今までの比にはならないくらい広がるのだから」と語ります。
広木氏は、「YouTubeが出たときに、『誰もが放送局になれる』と言われて、なろうとした人は少ない。でもそれを信じて行動し続けた人は、非常に大きなエンパワーメントの結果を受け取っていますよね。人間を凌ぐ場面もあるAIをほぼコストなしで使役できるようになり、今までやろうと思わなかったことがやるべきことに変わっています。でも、そのことをまだまだ受け止めきれていない。ここが最大のアンラーニングポイントだと思います。やろうと思わなかったことをやる、できると思って進む。この力が今求められています」と力強く締めくくりました。
AI時代の開発組織~エンジニアの未来を決める分岐点~
生成AIから自律型AIの進化により、エンジニアの役割と価値が再定義されつつあります。本セッションでは、AI時代の分岐点に立つエンジニアの課題と機会を分析し、進化が求められる領域と新たな価値創出の可能性を明らかにします。大企業とスタートアップのAI活用の違いから見る成功パターンや、日本企業が競争力を高める戦略についても議論します。2030年、AIと共創するエンジニアへの道筋とは。



初の開発者向けイベントとなりましたが、会場には予想を上回る開発者やテクノロジー戦略をリードする幹部が集結。ご満足いただけるアンケート結果になりました。お時間が合わなくてお越しになられなかった方、もう一度ご覧になりたい方は、録画映像をぜひご活用ください。
TDX Tokyo
AI時代を切り拓く
開発者カンファレンス
50以上のテクニカルセッションと実践的ハンズオン等でAgentforceを深く学び、AIエージェントを構築するスキルを習得。開発者・エンジニア・アドミンとして、あなたの会社と自身のキャリアに変革をもたらします。