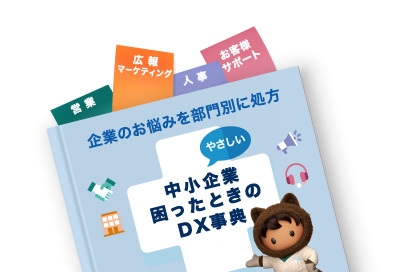業務委託やシステム導入の現場で欠かせないのが「RFP(提案依頼書)」です。
ベンダー選定を適切に進め、プロジェクトを成功させるために、何を・どこまで・どう依頼するかを明文化するのがRFPの役割です。
本記事では、RFPの基本的な定義から、目的・メリット・注意点・構成要素を網羅的に解説。
さらに後半では、注意点や金融・医療・コンサル業界におけるRFPの使われ方も紹介します。
「はじめてRFPを作成する」「他社や他業界の進め方を知りたい」という方にも役立つ内容です。
企業のお悩みを部門別に処方!中小事業者 困ったときのDX事典
Salesforceを活用した解決策はもちろん、AppExchange(Salesforceと連携可能なビジネスアプリケーション)を活用した解決方法をご紹介します。
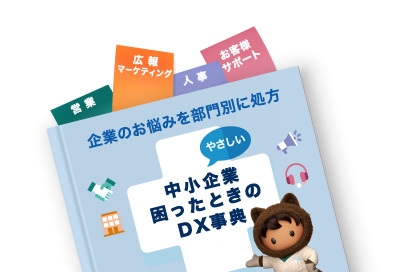
目次
RFPとは発注者から受注者に提示する提案依頼書

RFPとは、「Request For Proposal」の略で、日本語では「提案依頼書」と訳されます。
発注者がプロジェクトの実施を依頼するにあたって、候補となる複数のベンダー(受注者)に対し、提案や見積もりを求めるために作成する資料です。
RFPには、発注者が実現したい業務の背景や目的、求める要件、納期など、プロジェクト遂行において重要となる情報が詳細に記載されます。
RFPの質は、そのまま受け取る提案の精度に直結するため、プロジェクト成功の鍵を握る重要資料ともいえるでしょう。
IT業界では、システム開発や業務システムのリプレイス、インフラ構築など、技術的・金額的に複雑な案件において頻繁に活用されています。
SIer(システムインテグレーター)やソフトウェアベンダーとの契約プロセスで不可欠な存在といえるでしょう。
RFPを作成する目的
RFPを作成する最大の目的は、発注者と受注者の間で認識のズレやコミュニケーション不足を未然に防ぎ、プロジェクトを円滑に進行させることにあります。
プロジェクトの初期段階で要件が曖昧なまま発注を進めてしまうと、以下のような負のサイクルが発生しやすくなります。
- 抽象的な依頼内容 → 受注者が独自の解釈で提案
- 発注者の期待と異なる提案内容 → 調整や修正が必要に
- 想定外の追加作業・コスト発生 → スケジュールの遅延や信頼関係の悪化
トラブルを防ぐためにも、発注者は「自社が本当に求めていることは何か」「成功とするための基準は何か」を明文化し、RFPとして文書化しておくことが必要です。
RFIとの違い
RFPと似た言葉に「RFI(Request For Information)」がありますが、両者は目的や活用されるタイミングが明確に異なります。
以下に表で整理します。
| 項目 | RFP(Request For Proposal) | RFI(Request For Information) |
|---|---|---|
| 日本語表記 | 提案依頼書 | 情報提供依頼書 |
| 主な目的 | 実際に発注を見据えて、提案や見積もりを依頼する | 市場調査・情報収集のため、幅広く候補を知る |
| 利用タイミング | 選定・比較段階(発注に向けて候補を絞るフェーズ) | 調査段階(ベンダーの存在や技術力の把握) |
| 記載内容 | 要件・実施内容・体制・スケジュール・金額・提案方針など | 会社概要、技術領域、導入実績、製品概要など |
| 用途 | 実務的な提案を受け、発注先を決定するため | ベンダーの選定候補を把握・絞り込むため |
RFIは情報収集が目的で、市場の動きや会社などを知るための段階で活用されます。
一方、RFPは「選定のために本格的な提案を求める」実務フェーズで使われ、提案書・見積書の精度が直接契約に影響を与える資料となります。
つまり、RFI→RFP→契約という順序で活用されることが一般的です。
RFPを作成する5つのメリット

RFPを作成することには、単なる形式的な手続き以上の大きな意味があります。
システム開発や業務委託、マーケティング支援などの外部発注においては、RFPの有無がプロジェクトの成功可否を左右すると言っても過言ではありません。
ここでは、RFPを作成することで得られる5つの代表的なメリットについて解説します。
1. 要件の整理と社内認識の統一ができる
RFP作成のメリットのひとつは、発注側の要件や目的を明確にできることです。
単に外注先に依頼するための資料ではなく、社内にとって何を実現したいのかを整理しなおす機会にもなります。
マーケティングや情報システム、営業など複数の部署が関与するプロジェクトでは、各部門ごとに異なるニーズや前提条件をもっていることもあり、意見が食い違いやすい傾向があります。
RFP作成の過程でひとつの文書に落とし込むことで、関係者全員が共通認識をもち、発注前の準備を整えやすくなるでしょう。
また、業務課題や現行フローの問題点を洗い出し、どう改善したいのかを明文化することで、自社内の整理にもつながります。
依頼内容が曖昧なまま外部に投げるような事態を防げ、より的確な提案を引き出せます。
2. ベンダー選定の比較軸が明確になる
RFPを提示することで、複数のベンダーからの提案を同一基準で評価が可能です。
RFPには、仕様要件やスケジュール、予算などの条件が明記されており、各社が同じ条件にもとづいて提案書を作成するため、提案の粒度や方向性が揃いやすくなります。
その結果、印象や営業トークに左右されず、定量的かつ客観的な比較が可能となります。
| 会社 | 強み | 課題・リスク | 総合評価のポイント |
|---|---|---|---|
| A社 | 費用が安い | 納期がタイトで遅延リスクあり | コスト重視なら有力候補 |
| B社 | サポート体制が充実、実績も豊富 | 費用が高め | 安心感・品質重視で選ぶなら有力 |
| C社 | 柔軟な対応・開発体制がスピーディ | 実績が少ない | 将来性はあるが慎重な検討が必要 |
トレードオフを可視化することで、メリットとデメリットを俯瞰的に捉えた精度の高い意思決定が可能になります。
3. 開発・制作のトラブルを未然に防げる
多くのプロジェクトで発生する問題の原因は、認識のズレや想定外の対応によるものです。
RFPをしっかり作成しておくことで、そうしたトラブルの多くを未然に回避することが可能になります。
RFPには、以下のような内容が記載されます。
- 実施すべき機能や対応範囲
- 納期やスケジュール
- 成果物の形式やボリューム
- 合意すべき契約条件(対応外項目、費用条件など)
プロジェクト進行中に起きがちな「聞いていない内容だった」「追加費用が必要になる」といったトラブルを防ぎやすくなります。
4. 社内承認・予算申請がスムーズになる
RFP(提案依頼書)は、単なるベンダー向けの依頼資料だけでなく、社内での稟議・予算申請・部門間調整においても、大きな効力を発揮します。
とくに以下のような場面で役立ちます。
- 上層部への説明(意思決定のための判断材料として)
- 他部門との調整(予算、納期、体制の共有)
- 稟議書・事業計画書の添付資料としての活用
大規模なプロジェクトや中長期の投資案件ほど、「なぜ必要か」「どこまでの費用か」という根拠の明文化が求められます。
RFPがあれば、そのまま社内文書として転用可能です。
5. ベンダー側の理解度が高まり、提案の質が向上する
RFP(提案依頼書)によって依頼内容が明確化されることで、ベンダー側の理解度が向上し、提案の精度や実行可能性が大幅に高まります。
RFPには、以下のような要素が具体的に記載されているのが一般的です。
- プロジェクトの目的や背景
- 解決すべき課題・要件
- 期待する成果物の内容・形式
- 想定予算やスケジュール
情報が揃っていることで、ベンダーは課題の本質を捉えやすくなり、自社の強みを活かした最適な提案を行えるようになります。
RFPを作成する際の4つの注意点

RFPはプロジェクトを成功に導く有効なツールですが、作成の仕方によっては逆効果となることもあります。
ここでは、RFPを作成する際にとくに注意すべき4つのポイントについて解説します。
1. 作成に時間と手間がかかる
RFPはプロジェクトの骨格を形づくる戦略的な文書です。
そのため、作成には相応の時間とリソースが必要になります。
関係部署へのヒアリングや業務要件・背景の整理、予算の検討、目的や成果物の明確化など、準備すべき項目は多岐にわたります。
はじめてRFPを作成する企業の場合、何を書けばよいかという段階から手探りになることも少なくありません。
フォーマットの設計や関係者間の調整に時間がかかり、数日〜数週間にわたる作業になることも想定されます。
したがって、RFPの作成には早めに着手し、専任または兼任のプロジェクトメンバーを配置するなど、あらかじめリソースを確保しておくことが重要です。
2. 曖昧な表現や漏れがあると逆効果になる
RFPは、明確かつ具体的であることが求められます。
内容が曖昧なまま提出すると、むしろプロジェクトの混乱を招き、発注側・受注側双方にとって大きなリスクとなるでしょう。
「わかりやすいUIにしてほしい」「迅速な対応ができる体制」など、主観的で解釈が分かれる表現はベンダーによって捉え方が異なり、認識のズレが生じやすくなります。
また、要件に抜け漏れがあると、初期見積の段階では考慮されず、後になって追加対応・追加費用が発生するケースも多発します。
外部システムとの連携や保守・運用フェーズの要件が見落とされがちです。
RFPを作成する際は、できるだけ具体的な数値や条件で表現し、想定する業務フローや運用体制まで見据えて記述することが、精度の高い提案とスムーズな進行につながります。
3. 過剰な要求や細かすぎる指示は柔軟性を損なう
RFPを作成する際に注意したいのが、過剰な要求や細かすぎる仕様指定です。
一見すると明確な指示のようでありながら、プロジェクトの自由度や可能性を狭めてしまうリスクがあります。
指示の出し方による違いと適切なRFP記述例は以下が挙げられます。
| NGな指示例(過剰・固定的) | 問題点 | 改善されたRFP記述例(裁量を残す) |
|---|---|---|
| ボタンはすべて青色、フォントは12px、左揃えで | デザインの自由度がなく、UX改善の余地を奪う | 視認性と操作性に配慮したUI設計を提案してください |
| Reactで開発すること。AWSのみ使用すること | 技術選定の余地がなく、提案の幅が狭くなる | 将来的な拡張性と保守性を考慮した技術構成を提案してください |
| 〇〇機能はこの画面で、この順番で表示すること | ユーザーフロー全体を無視して設計を固定してしまう | この機能を実装するうえで、最適なUI構成を提案してください |
その結果、ベンダー側の創意工夫が活かされず、ただの作業者になることも。
発注側としても、「よりよい提案」や「プロの視点による改善案」を得るチャンスを逃すことになります。
4. 社内で意思決定ができていないまま出すと混乱する
RFPを、社内で意思決定ができていないまま出すと混乱する可能性があります。
プロジェクトの概要が社内で整理されていない段階でRFPを出してしまうと、ベンダーとのやりとりの中で方針変更が繰り返され、信頼関係を損ねる原因になります。
RFPを出す前には、経営層や情報システム部門、事業責任者など、社内のキーパーソンとの合意形成をしっかりと済ませておくことが大切です。
ベンダーにとっても、意思決定が統一されている発注者は、安心して提案・開発に取り組める存在となります。
RFPの書き方・構成要素

RFPを効果的に活用するためには、必要な情報を過不足なく整理し、ベンダーにとってわかりやすい形で提示することが重要です。
ここからは、RFPに盛り込むべき代表的な構成要素と、書き方のポイントを解説します。
要件定義
最初に整理すべきは、「なぜこのプロジェクトを実施するのか」という目的や背景です。
現行の業務やシステムでどのような課題が発生しており、それをどう解決したいのかを明確に記述する必要があります。
たとえば、以下のように現状の問題点と解決したい課題を具体的に示すことで、ベンダーも提案の方向性を正確に把握できます。
| 現状の課題 | 解決したい課題(ゴール) |
|---|---|
| 顧客管理システムが部門ごとに分断されている | 顧客情報を一元管理し、対応を標準化したい |
| 顧客対応が属人化しており、担当者に依存している | 誰でも一定の品質で対応できる体制を整えたい |
| システム間のデータ連携がない | シームレスに情報連携できる基盤を構築したい |
また、「実現したいこと(ゴール)」についても明文化しておくと、要件定義が不十分なまま設計が進むリスクを軽減できます。
要件定義の際には、技術的な視点だけでなく、業務改善の観点も含めることで、ベンダー側の理解が深まり、より的確な提案を受けやすくなります。
関連記事:プロジェクトマネジメントとは?意味や手法、必要なスキルをわかりやすく解説
提案依頼の範囲と期待内容
ベンダーに対して「何を、どこまで依頼するのか」を明確に定義することは、提案のズレや見積の過不足を防ぐために重要です。
まず、依頼範囲として、各フェーズのうち、発注対象となる領域を明示します。
| フェーズ | 実施主体 | 備考 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 自社 | 業務知識が必要なため自社で実施 |
| 設計 | ベンダー | UI設計含む |
| 開発 | ベンダー | システム構築全般 |
| テスト | ベンダー | 単体テスト・結合テスト含む |
| 運用 | 自社 | 社内体制で対応予定 |
| 保守 | ベンダー | 月次サポート契約を想定 |
加えて、機能提案やUI・UX改善、セキュリティ要件などの提案内容に含めてほしい視点なども明記しておくと、質の高い提案が集まりやすくなります。
提出形式・スケジュール・評価基準
ベンダーからの提案を効率的に比較検討するためには、提出方法やスケジュール・評価基準を事前に統一しておくことが重要です。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 提出形式 | Word/PDF/PowerPoint など目次や章立て構成も指定する |
| 提出方法 | メール添付、ファイル共有URL(Google Drive/Dropbox など)、専用ポータルへのアップロード |
| 提出期限 | 2025年6月10日(火)17:00 まで |
| 提案に含めてほしい要素 | ・価格見積・体制図・実績紹介・導入スケジュール案・体制・対応フローなど |
評価基準では、価格50点、技術力30点、体制・実績20点などを記載しておけば、ベンダーは重点を理解したうえで的確な資料を提出できます。
基準を明確にし、選定プロセスの透明性を高めると、要件に合ったベンダーを募りやすくなるでしょう。
【業界別】RFPの活用事例

RFPは業界を問わず幅広く活用されていますが、その活用方法や意味合いには業界特有の違いもあります。
ここでは業界別の活用事例を解説します。
金融業界
金融業界においても、RFPは他業界同様に提案依頼書として活用されています。
システム開発やアウトソーシング案件が多い分野であり、勘定系システムの刷新や、リスク管理システム、決済インフラの導入などで活用されるケースが一般的です。
この分野では、情報漏洩やセキュリティ要件の厳格さが求められるため、RFPには高い精度と明確な要件整理が求められます。
RFPの内容が曖昧だと、金融庁や監査法人からの指摘リスクが高まるため、コンプライアンス・ガバナンスの観点でも慎重な作成が必須です。
医療業界
医療業界におけるRFPは、抗生物質「リファンピシン(Rifampicin)」としての意味合いがあります。
リファンピシンは、主に呼吸器系や結核の治療薬として知られているため、医療従事者の中には“薬の名称”としての認識ケースもあるでしょう。
しかし、情報システムや病院経営の領域では、提案依頼書(Request For Proposal)としての意味でRFPが使われるケースも少なくありません。
電子カルテシステムや医事会計、画像診断管理(PACS)などの導入時に、病院側がベンダーに対して提示する資料として活用されます。
ただし、医療機関ではRFP作成のノウハウが不足していることも多く、外部のコンサルタントやSIerに支援を依頼するケースもあります。
関連記事:医療DXとは?主な取り組みと推進のポイント、成功事例を解説
コンサル業界
コンサルティング業界でもRFPはビジネスの現場で標準的に使用されており、クライアント企業が戦略立案や業務プロセス改善、IT導入支援などの外部パートナーを選定する際に用いられます。
複数のコンサル会社に対して提案を求める「コンペ形式」もあり、RFPの構成には他社との差別化に重きを置いた期待内容や納期・評価基準などが必要です。
さらに、実績や支援体制、担当者のスキルセットまで記載を求めるケースもあり、コンサル業界では、一般的な資料としてRFPが扱われています。
まとめ:RFPは「発注の質」を高めるための戦略ツール

RFPは単なる依頼文書ではなく、発注者の目的を明確にし、最適なパートナーを選定するための戦略的ツールです。
しっかりと作成されたRFPは、プロジェクトの成功確率を高め、コスト・納期・品質面でも大きなリターンを生み出します。
業界や案件の性質によってRFPの構成や表現は変わりますが、共通していえるのは「目的を明確にし、余白と判断軸を設計すること」の重要性です。
もし、RFP作成に不安がある場合は、外部の支援やテンプレートの活用を検討するのもひとつの方法です。
中小事業者 困ったときのDX事典
このガイドでわかること
・DX推進における部門別の悩みと解決方法
・Salesforce・AppExchangeを活用した悩みの解決方法