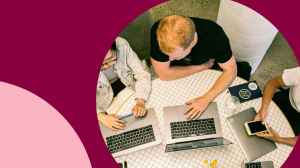ビジネスにおけるチャネルとは、集客を行う媒体や流入経路などを指す言葉です。チャネルの理解は、営業活動やマーケティング活動に欠かせません。本記事では、ビジネスにおけるチャネルの意味や種類、チャネル戦略を考える際の手順について解説します。
▶無料お役立ち資料【営業組織を強化し、売上向上に繋がる資料3点セット】をダウンロード
目次
チャネルとは?

チャネルとは、マーケティング用語で集客を行うための媒体や流入経路のことを指します。語源は英語の「channel(チャンネル)」です。媒体は多数存在し、WebサイトやSNS広告、新聞、テレビなどもチャネルの一例です。チャネルごとの集客力を分析・改善していくと、集客戦略の強化につながります。
チャネルの種類

マーケティングにおけるチャネルは、大きく3つに分けられます。それぞれの意味を解説します。
流通チャネル
流通チャネルは、商品やサービスを販売する際の経路や手段のことです。たとえば、メーカーが商品を販売する場合、流通チャネルとして卸業者や小売業者、配送業者などを活用します。流通チャネルを整えることで、顧客の利便性や満足度の向上や、流通コストの削減も期待できます。
販売チャネル
販売チャネルは、商品やサービスを販売する経路や方法を指します。具体的には、ECサイトやSNS、小売店舗、テレビショッピングなどが挙げられます。インターネットの普及により、販売チャネルの種類は多様化しました。
販売チャネルは、製品がBtoC向けかBtoB向けかによって重視される手法が異なる傾向があります。たとえばBtoB向けでは、展示会や代理店などのチャネルが活用される一方で、BtoC向けでは小売店舗やテレビショッピングなどのダイレクトなチャネルが多く用いられます。また、ECサイトやSNSなどに代表されるオンラインチャネルは、BtoBとBtoCのどちらでも活用される点が特徴です。
コミュニケーションチャネル
コミュニケーションチャネルは、企業と顧客がやり取りをする手段や接点を指します。かつてはテレビCMや新聞、雑誌、ラジオなどのマスメディアが主流でしたが、現在ではSNSやメール、チャットツールなど、多様化しています。
企業はこうしたコミュニケーションチャネルを通じて顧客にメッセージを伝えたり、顧客からのフィードバックを受け取ったりすることが可能です。製品やサービスの魅力を伝えるだけでなく、顧客との関係構築やブランド認知の向上にもつなげられます。
チャネルの形態

チャネルの形態は、企業と顧客の「接点の数」と「チャネル同士の連携の有無」によって、以下の4つに分類されます。
- シングルチャネル
- マルチチャネル
- クロスチャネル
- オムニチャネル
ここでは、4つのチャネルの形態を解説します。
シングルチャネル
シングルチャネルは、企業と顧客の接点がひとつだけの状態を指します。たとえば、実店舗のみ、またはSNSのみで販売を行う場合は、シングルチャネルに該当します。近年は新たに小売事業に参入する際、ネット販売のみでスタートするケースも増えており、低コストで運用できる点が大きなメリットです。
マルチチャネル
マルチチャネルは、実店舗とオンラインショップのように、複数のチャネルを使って商品やサービスを提供する形態です。それぞれのチャネルは独立しており、顧客情報や在庫情報は連携されていません。チャネルの数だけ顧客との接点を増やせるため、認知や購入機会の拡大が期待できます。
クロスチャネル
クロスチャネルは、複数のチャネルを持ち、さらに顧客情報や在庫管理がチャネル同士で連携されている状態です。顧客との接点を複数持つ点はマルチチャネルと同様ですが、チャネルを横断してデータを管理する点が大きく異なります。たとえば、ECサイトで注文した商品を店舗で受け取れる仕組みなどがクロスチャネルに該当します。チャネル間の連携により、一貫した顧客体験を提供できます。
オムニチャネル
オムニチャネルは「オムニ(すべて)」の名の通り、あらゆるチャネルを統合し、顧客がチャネルの違いを意識せずにシームレスな体験ができる状態です。たとえば、SNS広告を見てそのまま購入し、店舗で受け取るといった行動が可能になります。スマートフォンの普及により、現在はオムニチャネルが主流となりつつあります。
チャネル戦略とは?

チャネル戦略とは、一般にマーケティングの4P(製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion))における、流通戦略の一部として位置づけられます。製品やサービスを消費者に届けるために、最適な流通経路を設計・選定することが主な目的です。
具体的には、どのチャネルで製品を販売するか、どの経路を通じて顧客に届けるかを策定します。チャネル戦略を練ることで、今後のマーケティング活動のブラッシュアップにつながります。
▶無料お役立ち資料【営業組織を強化し、売上向上に繋がる資料3点セット】をダウンロード
チャネル戦略が売上や認知の拡大につながる理由
チャネル戦略はターゲットとなる顧客に対して、製品やサービスへのより優れたアクセス手段を提供するための施策です。適切なチャネルを選定・活用することで、従来なら接点を持てなかった消費者にも製品を届けられるようになり、結果として売上の拡大や認知向上につながります。また、効率のよいチャネルを選択することで、広告費や人件費などのコスト削減にもつながります。チャネル戦略は、企業の成長を支える重要な取り組みのひとつです。
チャネル戦略の進め方

チャネル戦略の効果を最大限に発揮するためには、以下の手順に沿って戦略を構築・展開していくことが重要です。
- ターゲットを決める
- 販売チャネルを決める
- チャネル段階を決める
- コミュニケーションチャネルを決める
とくにチャネル段階は戦略策定において欠かせない概念であるため、あわせて詳しく解説します。
1.ターゲットを決める
まず、狙う顧客の性別や年代、趣味嗜好など、自社製品のターゲットを明確にしましょう。ターゲットによって反響が見込めるチャネルは異なります。たとえば、美容に関心を持つ女性でも、30代と60代では利用するチャネルが異なる場合が多いです。
ターゲットが明確になるにつれて、チャネル戦略も立てやすくなります。
2.販売チャネルを決める
ターゲットに合わせて、販売を行うチャネルを決定します。このとき、どのくらいの数のチャネルに展開するかを「チャネルの幅」と呼びます。チャネルの数が少なければ「幅が狭い」、多ければ「幅が広い」と表現されます。
販売チャネルを決める際は、コスト面も考慮しながら戦略を立てることが重要です。コスト次第で展開できるチャネルの数や場所、後述するチャネル段階も変動します。
3.チャネル段階を決める
チャネル段階とは、商品が顧客に届くまでの流通ルートや関わる業者の数を指します。商品販売には、小売業者や仲介業者、卸業者など、複数の業者が関わるケースも多いです。チャネル段階は、0段階から3段階まであり、段階によって利益の幅や流通範囲が変わります。
0段階チャネル
生産者やメーカーが製造から販売までを自社で担う直販モデルです。中間マージンが発生しないため、利益を最大化できる点がメリットです。
ただし、流通範囲が限定されるため売上拡大には限界があります。現在はネット販売の普及により、0段階チャネルを採用するケースが増えています。
1段階チャネル
生産者が小売業者に商品を納品し、小売業者が消費者に販売するモデルです。生産者は販売業務を担わない一方で、商品管理や運搬は行います。
小売業者は、生産者から直接商品を仕入れることでコストを抑えた販売が可能となり、消費者にとっても価格面でのメリットがあります。シンプルなビジネスモデルながら、直販より広い消費者にアプローチできるのが特徴です。
2段階チャネル
生産者と小売業者の間に卸売業者が介在するモデルです。スーパーなどで多く見られ、製品ごとに専門の卸売業者が仕入れを行います。生産者にとってはさらなるビジネス拡大が叶い、また小売業者にとっても仕入れ業務を効率化できるメリットがあります。
3段階チャネル
生産者と小売業者の間に、複数の卸売業者が介在するモデルです。近年は減少傾向にありますが、食品や日用品など、流通量が多く単価が低い商品では現在も採用されています。
4.コミュニケーションチャネルを決める
最後にコミュニケーションチャネルを決定します。顧客視点に立ち、多様なチャネルの中から最適なものを選ぶことが重要です。
たとえば、ECサイトと連動したスマートフォンアプリを活用することで、商品購入以外にもキャンペーン告知や新商品の紹介、口コミの収集といった取り組みが可能になります。
また、近年は動画視聴時間の増加に伴い、動画メディアをチャネル戦略に取り入れる企業も増えています。商品説明やキャンペーン、ブランドストーリーなど、動画の目的に応じて内容を精査し、効果的に活用することが求められます。
チャネル戦略を成功させるポイント

チャネル戦略を成功させるためのポイントを解説します。
ターゲットをよく理解する
ターゲットを深く理解しなければ、チャネル戦略は成り立ちません。市場ニーズや消費者行動、顧客のセグメントや嗜好を深く理解し、適切なチャネルを選定することが重要です。顧客のセグメントを正しく理解し、もっとも効果的なチャネルを特定することが成功への近道です。
中間業者との良好な関係を目指す
中間業者が関わる場合、良好な関係を築くことで、効果の最大化が期待できます。ニーズを理解し合い、目的達成に向けて協力できる体制を整えることが重要です。インセンティブ制度を設定することで、中間業者の販売意欲を高めることもできます。
4Pとのバランスを意識する
チャネル戦略は、マーケティングの4P「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「プロモーション(Promotion)」のうち、流通戦略を指します。しかし、チャネル戦略を成功させるには、流通だけでなく、製品や価格、プロモーションの各戦略とのバランスを取ることが不可欠です。
たとえば、最適なチャネルが選択できていても、価格がターゲットに合っていなければ、購買にはつながりません。流通戦略とほかの戦略とのバランスが取れているか、あわせて確認する必要があります。
関連記事:4P分析とは?マーケティングの基礎を支える手法を解説
オムニチャネルを積極的に導入する
オムニチャネルを導入することで、複数のチャネルを効果的に組み合わせ、顧客に合わせた質の高いアプローチが可能になります。チャネル同士がシームレスにつながることで、顧客にとってストレスのない購買体験を提供できます。これにより認知拡大や売上アップだけでなく、ファン化やブランド価値の向上も期待できます。
PDCAを回しながら改善を図る
チャネル戦略は、一度実行したら終わりではありません。定期的に振り返りと評価を行い、改善を重ねましょう。売上データや顧客からのフィードバック、チャネルの効率性などの分析が重要です。継続的な改善によって最適なチャネル戦略を維持でき、企業成長にもつながります。
AIを活用したCRMでチャネル戦略の立案から改善までをサポート

CRMは、企業全体で顧客情報を一元管理できるシステムです。購買履歴や行動データ、サービスの利用状況などを集約して管理することで、顧客の傾向やニーズを効率的に把握できます。これにより、チャネル戦略の立案や最適なチャネルの選定・改善にも活用できます。
さらに、多くのCRMには営業プロセスの記録やレポートの自動生成、案件の優先度分析などの機能が備わっており、チャネル戦略のPDCAサイクルを回すうえでも役立ちます。
Salesforceが提供する「Sales Cloud」なら、AIによる見込み客の見極めが可能です。Webサイトなどから獲得したリードを分析して、営業担当者へつなげるため、マーケティング戦略と営業の連携を強化できます。豊富な学習コンテンツやサポート体制も整っているため、スムーズに実務へ活用できます。
関連記事:AIを活用したCRMとは?従来型との違いや導入ポイントを解説
チャネルの種類を理解し戦略の実行に動き出そう

チャネルとは、商品やサービスを顧客に届けるための経路や手段を指します。チャネルは多様化しており、ビジネスの成否に大きく関わる重要な要素です。
近年では、複数のチャネルを組み合わせて顧客体験を最適化する「オムニチャネル」の考え方も広がっています。こうしたチャネル戦略を効率的に進めるには、顧客情報を一元管理し、データに基づく意思決定ができる体制を構築することが重要です。
AIを活用したCRMツール「Sales Cloud」なら、購買履歴やサービス利用状況などの顧客データを統合管理でき、戦略の立案から改善までを支援します。
チャネル戦略をより効果的に進めたい方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてご活用ください。