創業から50年近くの歴史を持つ同社が、なぜそれまでの業務を大胆に見直すことができたのでしょうか。ベルニクスの代表取締役社長、鈴木健一郎さんに語っていただきました。
💡この記事で得られるインサイト
- 経営者目線で変革に挑むためのマインドセット
- 営業現場の真価を引き出す仕掛け
- 現場が自走するための自律型組織の育て方
- テクノロジー活用の真の導入条件
- 小規模企業ゆえの強みの生かし方
目次
なぜSalesforceで売上と業務効率が向上するのか?
なぜSalesforceを活用すると、組織の売上と業務効率が向上するのでしょうか。このガイドでは、売上向上・業務効率化をもたらす仕組みと立場別のメリットについて、具体的に解説しています。
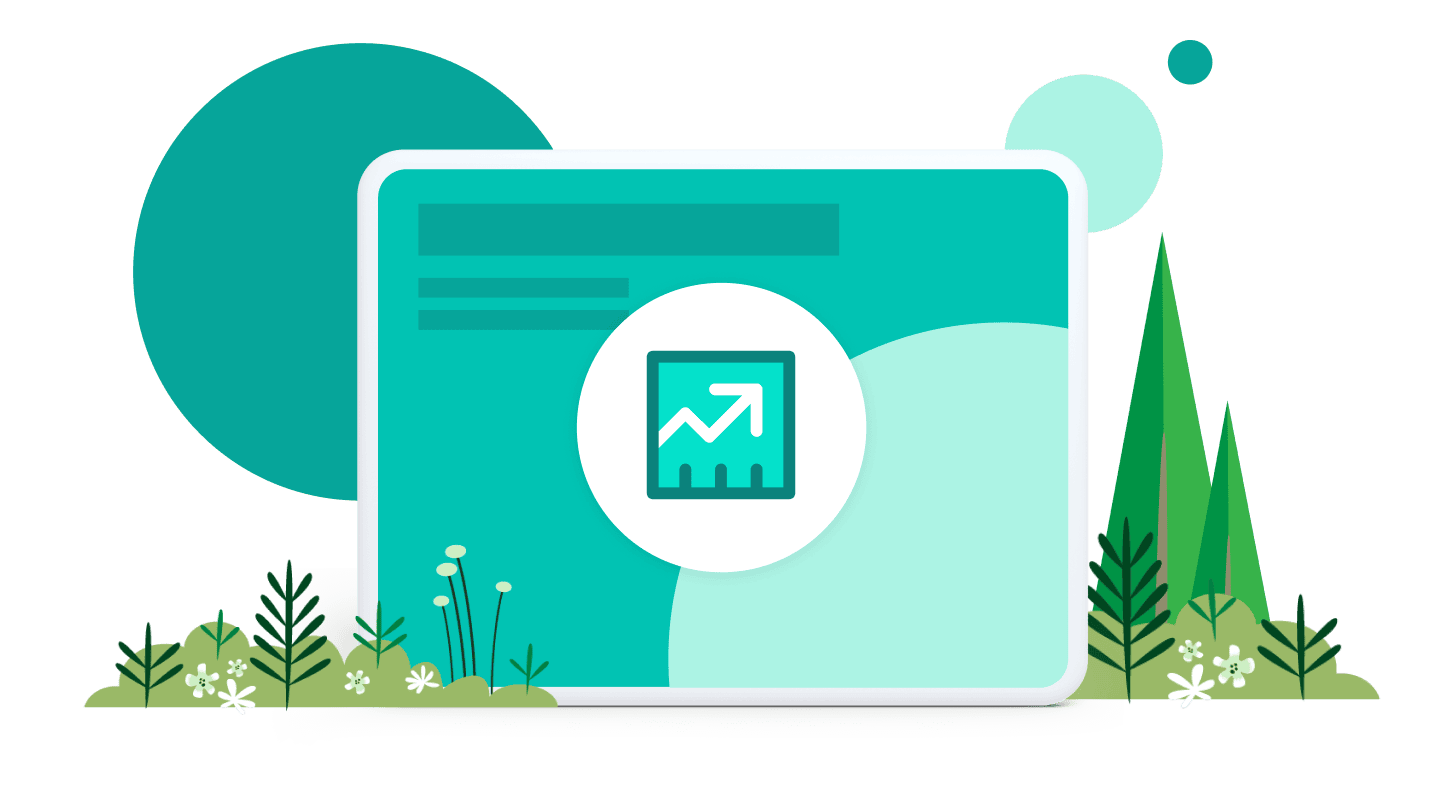
緊急事態で父の会社を承継
──ベルニクスの創業家に生まれ、2代目の社長としてビジネスをさらに発展させています。もともと家業を継ぐつもりだったのですか。
鈴木:継ぐつもりはありませんでした。父(現会長)からは「戦国時代じゃないんだから、お前が継げると思うな」と言われていましたしね(苦笑)。
ですので、自身の道を進み、半導体の時代が来ると予感して、大学卒業後は電子部品の商社に入社。技術職と営業職を経験しました。
──それなのに、なぜベルニクスに入社したのですか。
父が急病で倒れたんです。退院した時、「そう長く社長を続けられないかもしれないから、ベルニクスに来ないか」と初めて誘われました。緊急事態でしたので、私も真剣に考え、入社を決めました。
ただ、決めたのは良いものの、それまで関わっていなかったので会社のことを全く知らなくて……。そこからは勉強、勉強でした。
後継者候補として入社するので、成果を出さなければ社員の視線は冷ややかでしょうし、ついてきてくれないでしょう。
幸いにも弊社には、新しい概念のCPU向け電源製品があり、これはポテンシャルが高いと感じ、国内だけにとどまっていた販路を世界に広げようと考えました。
シリコンバレーに出向いたら、当時の産業用CPUで合計で世界シェア90%を持つ2社のリファレンスデザインとして採用。 埼玉県の100人もいない会社が作った電源が、世界中の完成品メーカーに紹介されたわけです。

株式会社ベルニクス 代表取締役社長
日本大学生産工学電気電子工学科卒。トーメンエレクトロニクス(現ネクスティエレクトロニクス)にて半導体ビジネスに従事。1999年、ベルニクス入社。ビジネス戦略室室長、常務取締役を経て、2016年代表取締役社長に就任。2019年に新規事業の子会社、株式会社ベルデザインを設立し、代表取締役社長を兼務する。
500件の案件管理のために毎週12時間の営業会議
──小説みたいな話ですね。その後、2016年に社長に就任。サービス事業の立ち上げや自社プロダクト事業の子会社を設立するなど、矢継ぎ早に新施策を打ってきた中、社長自らDXの陣頭指揮も執りました。
営業の仕組みをテクノロジーで変えなければ、立ち行かなくなるという危機感があったんです。
実は、その当時、営業全員が集まる会議を朝9時から夜9時まで合計12時間、毎週開催していたんです。営業5〜6人で合計500もの案件を抱えていて、その状況を私がチェックするんです。
──週1回、毎回12時間ですか!?
はい……(苦笑)。一つひとつの案件を営業全員が共有することには意味がありました。その場でダイレクトに指示が出せるのもメリット。当時としては、それが最も効率的な方法だと思っていたんです。
ただ、案件が増えればそれに比例して会議時間も増えていく。当然、私は営業だけが仕事ではありません。このやり方はさすがに限界だな、と。
そこで会議時間を短縮して部下に権限を委譲し、月次で確認するようにしたところ、以前は起きなかった対応漏れが見つかり始め、案件の成約率も下がっていきました。
DXに本腰を入れるのに、十分な状況だったんです。良くも悪くも、悩む余地はありませんでした。
──そこでSalesforceに注目いただいたのですが、導入までの経緯を教えてください。
最初からSalesforceではありませんでした。Salesforceが理想的だと思いましたが、コストに見合った価値を出せる自信がなく、当初は、IT部門のリーダーと相談してオープンソースソフトウェア系のCRMを入れました。
3年ぐらい使いましたが、モバイルデバイスでの操作性に難があるなど、さまざまな不都合が生じたので、Salesforceを導入したいとITリーダーに持ちかけところ、「社長がやりたいことの全ては実現できないかも」と慎重でした。
でも、これだけ世界的に有名なソリューションで、できないわけがないと思って自分でイベントに登録して参加し、セミナーや事例を聞いて「やりたいことが全部できる。むしろその先までできる」と確信。こうして2017年8月に営業部門に「Sales Cloud」を導入しました。
今思えば、自分と目と耳で確認したことが良かったと思います。

進まないSalesforceの定着。救ったのは営業担当者の声
──社内の反応はいかがでしたか。抵抗もあったのではないですか。
よく聞かれますが、導入することに抵抗はありませんでした。ただ、「導入することには」です。導入したのはいいものの、なかなか定着しなかったんです(苦笑)。
当時は「お客様の前でパソコンを開くのは失礼」という意識があって、ノートのメモをパソコンで打つことになるので、面倒ですよね。
「余計な手間が増えた」「入力するメリットがわからない」「入力時間を捻出するために営業のアポを1本減らさざるを得なかった」といった不満が続出。しかも、導入当初は個人が個人のタイミングで入力するので、リアルタイム性に欠け、そもそも正確かどうかもわからない。
そこでSalesforceの営業担当者に相談して、「振り返り」という手法を教えていただきました。チャットツール「Chatter」でやりとりしながら、営業は月曜日の朝8時半までに週報を入力し、マネジメントは火曜日の朝8時半までに必ずフィードバックを返す。
この積み重ねで、1年半ぐらいかかりましたが定着。従来の議事録は一方通行のやりとりでしたが、今度はリアルタイムで反応がある。「チェックしてもらっている」という実感が現場には良かったのだと思います。

Tableauを全社定着できないなら経営から身を引く
──「営業の見える化」から始まったDXは、その後どのように広がっていきましたか。
翌年の2018年にはSales Cloudを営業以外の技術部門長などにも展開し、Salesforceプラットフォームで稼働するグループウェア「mitoco」を全従業員に導入しました。
2020年に導入したマーケティングオートメーション(MA)の「Marketing Cloud Account Engagement」(旧Pardot)は、イベントで見て「なんて便利なんだ!」と感動して即導入。2022年には、経営層と営業部門にBIツール「CRM Analytics」を導入し、経営や営業の数字を正しく出すために、生産管理にも手を入れました。
当時、必要な部品が全て揃っていなくても、職人芸の判断と技術で生産工程を進めてしまっていることがありました。これでは工程が正しく見えないので、売り上げ予測を立てられない。そこで人間の曖昧な判断が入らないようにルール化して、フローチャートを根本から見直し。大変でしたが、これからの時代にそぐわない社内ルールを壊す良い機会でした。
──経営や営業以外でもDXが進んだわけですね。
そうですね。2024年にはSales Cloudを品質保証部にも展開。さらにBIツールをCRM Analyticsから「Tableau」へ変更しました。経営層、営業部、生産管理部、購買部が対象で、だいぶ形になってきました。
Tableauの導入には抵抗はありましたけれど、経営の見える化には絶対に定着させなければならないと覚悟を決め、「3年以内にTableauを定着させることができなければ経営を退く」と言っています。
──かなり強い覚悟ですね。
同時に「Salesforceを全て解約する」とも。営業部門も当初はやらされている感がありましたが、「Salesforceがなくなると仕事が回りません」と、目の色が変わってきました。今では全ての営業報告がTableauのダッシュボードで確認できるようになり、ようやくみんなが本気になってきたと感じています。
デジタルツールの活用は各社員の目標設定にも組み込まれており、Salesforceを使いこなせなければ、今では管理職ではいられません。

【活用事例7選】
スタートアップや中小企業にSalesforceが選ばれる理由
成長企業が選ぶクラウドプラットフォームがSalesforceです。データとAIの力でビジネスを早く軌道に乗せ、素早く成長させます。あらゆる地域・業種の7つの事例を紹介します。

Salesforceを推す3つの理由
──なぜこれほどSalesforceを推してくださっているのでしょうか。
第1に、先を見越して、現状維持でとどまらない発展性です。常に進化し続けて、新しいプロダクトや機能を提供し続けてくれ、私たちを高みに連れていってくれるという期待があります。
第2に、グローバルでの実績。絵空事ではなく、世界中で実証された信頼があります。そして第3に、営業担当者の熱意とサポート体制です。システムを導入して終わりではなく、私たちの成功まで伴走してくれることです。
──ありがとうございます。今後のベルニクスの展望と、Salesforceに期待することをお聞かせください。
コロナ禍では、日本の製造業が「買い負ける」場面が多く見られました。200円の半導体が2万円まで高騰しました。100倍ですよ。買うかどうかを確認すると、日本企業は稟議に3日かかり、その間に部品がなくなってしまう。一方で、市場を見極めて素早く買い占め、高値で転売している海外企業も。
そこで当社は、世界の産業インフラを支える会社として、安定供給のために今期から在庫を持つ経営に転換したんです。リスクを伴うため、大きな覚悟が必要でした。
だからこそ、さらにテクノロジー活用が大切。とくに人が予想するよりも精度の高いAIによる需要予測に期待しています。私たちは幅広い産業に部品を供給していますから、どの産業が動き出すと景気が上向くかがわかります。そのデータをAIに学習させれば、より精度の高い予測が可能になると考えています。

──DXを推進したいけれど、日々の業務に追われて後回しになってしまう経営者の方々が少なくありません、最後に、ベルニクスはテクノロジーによる全社改革をなぜ軌道に乗せることができたか、教えてください。
エクセルだけで、いつまで経営を続けられるでしょうか。今期の売り上げがいくらになるのか各部門に問い合わせて1週間かかるのと、ダッシュボードを開くと瞬時に見られるのとでは、経営スピードが全く違います。DXなしに事業を継続することはできない。「生き残る覚悟」が問われています。
それでも後回しになるのは、理想の姿が見えていないからでしょう。私はSalesforceのイベントでベストプラクティスを見て、「ああいう世界になったら経営が楽になる」「あの世界を目指したい」と明確にイメージできました。
時間がないとは思いますが、先を見るのが経営者の仕事。テクノロジーが経営にとって欠かせないのは自明の理です。まずは自分の足、目や耳を使って、「待ったなしという危機感」と「不退転の覚悟」を持つことが重要だと思います。
なぜSalesforceで売上と業務効率が向上するのか?
なぜSalesforceを活用すると、組織の売上と業務効率が向上するのでしょうか。このガイドでは、売上向上・業務効率化をもたらす仕組みと立場別のメリットについて、具体的に解説しています。
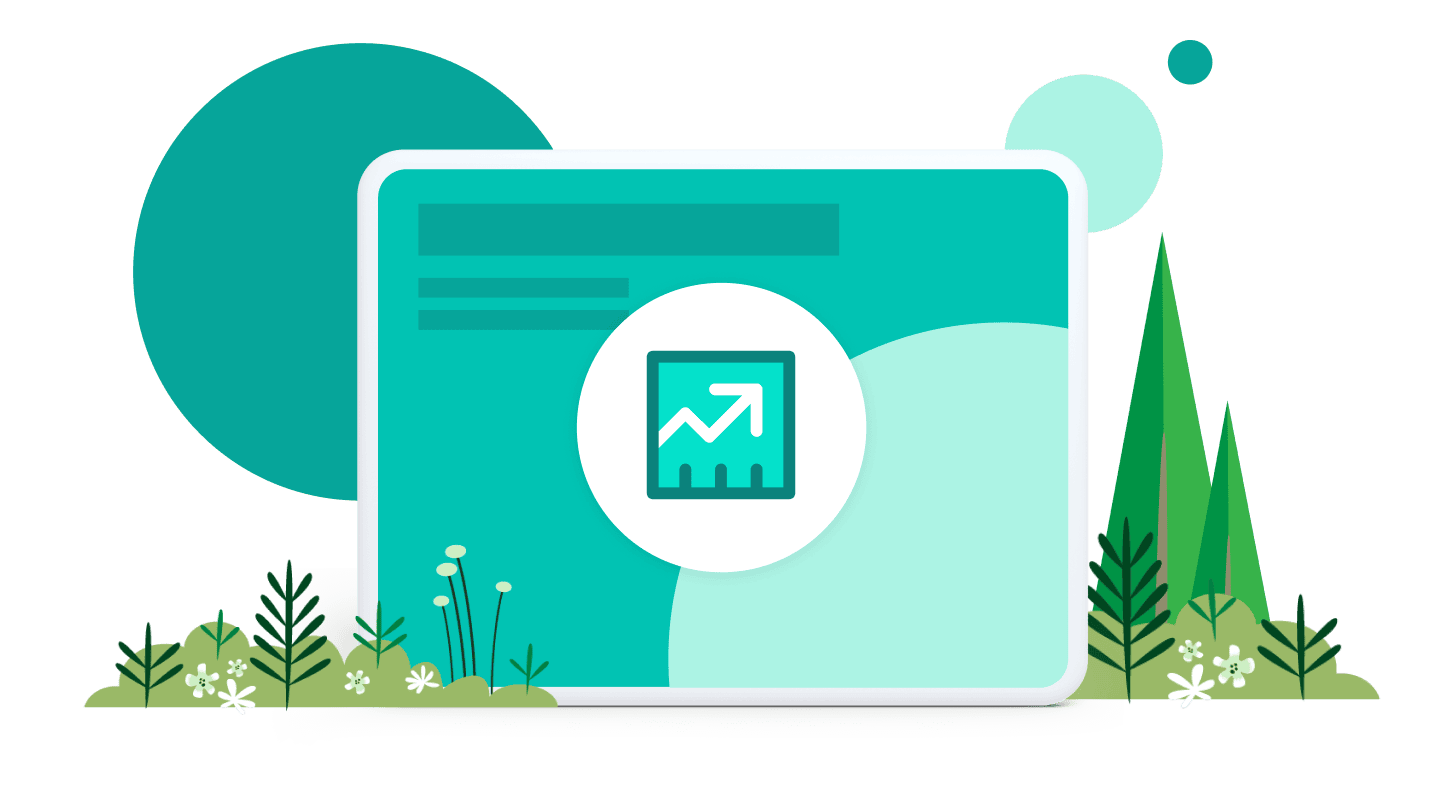
執筆:加藤学宏
撮影:遥南 碧
取材・編集:木村剛士





















